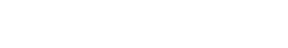EV専用のプラットフォームを開発
世界中の自動車メーカーが、「ゼロ・エミッション」、すなわち、走行中に排ガスを一切出さないクルマの普及に向けて鎬(しのぎ)を削る中、2010年の発売以来、世界中で20万台を超えるセールスを達成し、販売台数世界一を誇る電気自動車(EV)が日産リーフである。
その人気の秘密は、EV専用に開発されたクルマであるということだ。既存のエンジン車と、EVとではそのメカニズムが大きく異なるため、EV専用、または、EVを想定して設計されたクルマのほうが、エネルギーを効率的に利用できるうえに、広い室内スペースの確保や、優れた走りを実現しやすいというメリットがある。一番の課題は走行用の電気を蓄える大容量バッテリーをどこに配置するかということだが、日産はバッテリーを車両中央の床下に配置する、EV専用プラットフォームを開発。これにより、全長×全幅×全高=4445×1770×1550mmという扱いやすいボディーサイズに、大人5人がゆったりと過ごせるキャビンと、必要十分なラゲッジスペースを確保することに成功している。さらに、大容量のバッテリーを床下に積み、低い重心高を実現したことで、優れた操縦安定性を手に入れたのだ。

ボンネット下に収められる「リーフ」のパワーユニット。最高出力80kW(109ps)、最大トルク254Nm(25.9kgm)のモーターを搭載し、どんなシチュエーションでも力強い加速を味わうことができる。
EVの性能を左右するバッテリーとして、日産は長年の研究によるノウハウを注ぎ込んだリチウムイオンバッテリーをリーフに搭載した。発売当初から、24kWhの大容量バッテリーにより200km(JC08モード)という実用的な航続距離を実現していたが、2012年11月にはモーターの変更や制御の改良、パーツの軽量化などにより航続距離を228kmに伸ばしている。そして、2015年11月のマイナーチェンジでは、容量を25%アップした30kWhバッテリー搭載モデルを追加。従来のバッテリーパックと同じサイズを維持することで、キャビンスペースを犠牲にすることなく、航続距離を280km(JC08モード)に向上させた。どちらのバッテリーでも、急速充電器を用いれば、約30分で80%までの充電が可能となることから、短距離の移動はもちろんのこと、かつてEVでは難しいとされてきた長距離のドライブにも安心して出掛けられる。
そんなハードウエアの進化に加えて、充電インフラの整備もまた、リーフのある暮らしを後押ししているのも見逃せない。リーフの登場を機に、日産販売店の多くに急速充電器を設置。さらに、街を走るリーフが増えるにつれて、高速道路のSA/PAやコンビニエンスストア、ショッピングモールなどでも急速充電器の設置が進んだのだ。その立役者がリーフであることは、誰の目にも明らかだろう。

バッテリーを床下に収納するレイアウトを採用したことで、余裕のある室内空間が確保されている。後部座席には、大人3人がゆったりと座ることができる。
さらに、日産はリーフのオーナー向けに「日産ゼロ・エミッションサポートプログラム2」をスタートさせた。これは日本充電サービスが運営する、日産販売店舗や高速SA/PA、コンビニエンスストアなどに設置された全国約5600基の急速充電器が利用できる会員サービスで、中でも注目は月々わずか2000円(税別)の定額で利用できる「使いホーダイプラン」だ。充電のたびに料金を支払う月会費1000円(税別)の「つど課金プラン」も用意されるが、こちらは1分あたり15円がかかる。急速充電30分でバッテリー残量80%を目安にすると、1回450円ということになる。月会費も考慮すると、3回以上急速充電器を使うなら使いホーダイプランのほうがお得といえる。走行距離がある程度多い人なら、自宅で充電するよりも安上がりだし、ガソリン車(レギュラーで15~16リッター換算)と比較してもコスト面でかなりメリットがある。これだけリーフを利用しやすい環境が整えば、自宅で充電できないマンション暮らしの人でも、安心してリーフを所有できるのではないだろうか。

シンプルな形状のシフトセレクター。球体の真ん中を押すと「P」、球体を右に寄せると「N」、右前に押すと「R」、右後ろに引くと「D」、もう一度引くと、より強い回生ブレーキが得られる「B」となる。