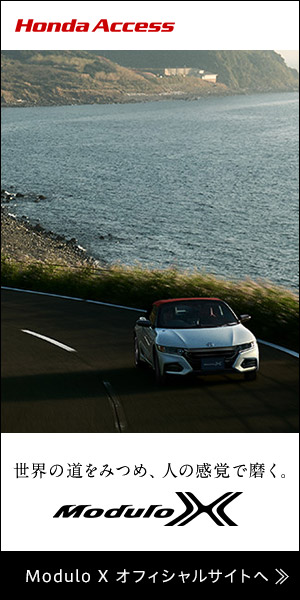今日に至る25年の時を振り返る
“上質な走り”を求めて 2018.12.21 Moduloの25年史<PR> 1994年にアルミホイールのブランドとして誕生して以来、少しずつ手がける用品の範囲を広げ、いまやコンプリートカーを開発するまでになった「Modulo(モデューロ)」。その根底には、どのような“走りの哲学”があるのか? 四半世紀の歴史とともに振り返る。誕生から間もなく25年
2018年5月、かねてより話題となっていた「ホンダS660モデューロX」が発表された。軽スポーツカー「ホンダS660」をベースに、ホンダアクセスのカスタマイズパーツを生産過程で装着したスペシャルなモデルだ。ノーマルのS660より67万円ほど高額だが、それでもS660の販売台数のうち、20%以上を占めるほどの勢いを示しているという。ユーザーは価格以上の価値があると判断しているのだろう。ホンダファンのみならず、幅広くクルマ好きから注目を集めている。
ホンダアクセスが提供するコンプリートカー「モデューロX」は、このS660が第5弾となる。2013年の「N-BOX」からスタートし、これまでに「N-ONE」「ステップワゴン」「フリード」に設定されてきた。ホンダ車を知り尽くしたエンジニアが匠(たくみ)の技を注ぎ込み、意のままに操れる操縦性と上質な乗り味を追求したクルマである。これらのモデルがどんな背景から生まれたのかを知るには、モデューロの歴史をさかのぼらなければならない。
モデューロは、ホンダ車の純正用品を手がけるホンダアクセスのカスタマイズブランドである。1994年にアルミホイールのブランドとして誕生し、1999年になると商品ラインナップをエアロパーツにも拡大していく。2007年には「シビック タイプR」のスポーツサスペンションを発売し、走行性能を追求するアフターパーツ全般のブランドへと進化を遂げた。
モデューロは、デザインでスポーティーさをイメージさせるだけでなく、ドライバーと乗員に上質な走りを提供する。ホンダスピリットを体現するコンセプトのルーツは、1990年にデビューしたピュアスポーツカーの初代「NSX」にあった。
次の記事:モデューロの歴史を彩る新旧3台を比較試乗
前の記事:モデューロの技が生きるミニバン2台を試す
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
ドイツで形作られた“理想の走り”
NSXの開発にあたり、ドイツのニュルブルクリンク北コースでテスト走行を重ねたのが本田技術研究所の玉村 誠氏だった。後にホンダアクセスにおいて、モデューロの走りの方向性を決定づけた人物である。自らレースやラリーに出場していた玉村氏は、ホンダ車のサスペンションを長年にわたって鍛え続けてきた。テストドライバーとして走り込み、バラしては設定を変えて再び組み立てることを繰り返す。自分で体感し、その感覚を生かして徹底的に作り込んでいく。現場でトライ&エラーを重ねることが重要なのだ。
開発に際してNSXが走らされたのは、サーキットだけではない。ニュルブルクリンク周辺の一般道を走り、実際にユーザーが走行する状況をシミュレートした。荒れてバンピーな路面を試し、アウトバーンでは高速での安全性を確かめる。必ずしもすべてのドライバーが正しい運転姿勢で慎重なドライビングをするわけではない。それでも安心して走れるクルマに仕上げることが必要だった。
NSXはスポーツカーだが、サスペンションをガチガチに固めたセッティングではなかった。乗り心地を犠牲にすることなく、安全で走りやすいクルマにすることを目指す。そのためには「バランス」が重要なキーワードとなった。硬さと柔らかさを両立させ、前後の平衡を保つことでドライバーも他の乗員も違和感を持たない乗り味を実現する。
“4輪で舵を取る”というのが開発の信条となった。非駆動輪も生かして、クルマ全体でスムーズに曲がっていくことを目指すのだ。それは、スポーツカーでもセダンでも変わらない。玉村氏がセッティングした足まわりは、いつしか“玉サス”と呼ばれるようになる。それはホンダが理想とする走りを実現するためのゆるぎない指針となった。
次の記事:モデューロの歴史を彩る新旧3台を比較試乗
前の記事:モデューロの技が生きるミニバン2台を試す
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
NSX開発のノウハウをモデューロに
NSXはスーパースポーツカーの概念を変えたといわれる。海外の高性能モデルに引けを取らない動力性能を持ちながら、わずか800万円という価格で提供されたことは衝撃だった。それ以上に世界を驚かせたのは、NSXが日常で使うための乗りやすさと安全性を備えていたことである。それまでは、スピードと引き換えに乗り心地や使い勝手の部分で忍耐を強いられるのが普通で、乗りこなすには高度なスキルを求められるのが当然とされていた。
NSXの開発で得られたノウハウは、モデューロにそのまま持ち込まれた。玉村氏がホンダアクセスに移り、ホンダ車に装着するカスタマイズパーツの製作を始めたのだ。サスペンションに加え、ホイールやブレーキパッド、エアロパーツの開発に取り組み、総合的にクルマの性能向上を図っていく。
その試みは、「シビック」や「CR-Z」などのチューニングパーツとして結実する。2011年にはNSXに装着する前後5段階減衰力調整機構付きスポーツサスペンションとドライカーボン製トランクスポイラーを発売する。デビューから時間が経過したNSXをリフレッシュし、長く乗り続けてほしいという願いが込められていた。
この製品を置き土産にして、玉村氏は定年退職した。NSXから始まったモデューロの精神を未来へとつないでいくには、思いを同じくするエンジニアに後を託すしかない。彼の後継者となったのが、福田正剛氏である。
次の記事:モデューロの歴史を彩る新旧3台を比較試乗
前の記事:モデューロの技が生きるミニバン2台を試す
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
3代にわたり受け継がれるクルマづくりの精神
福田氏が玉村氏とともに開発を進めたのはわずか2年。短い期間ではあるが、精神と手法はしっかりと受け継がれた。福田氏も本田技術研究所出身で、玉村氏と同様にレース活動に熱中した。同じバックボーンを持つだけに、クルマに対する姿勢は共通している。多くの言葉を費やさなくとも、モデューロが進むべき方向性は確実に伝わった。
福田氏には玉村氏のもたらした果実を受け取りながら、同時に次の世代へと橋渡しする役割も課せられた。新たな道を切り開く責務を引き受けたのは、2003年に入社した湯沢峰司氏である。福田、玉村の両名とは異なり、湯沢は最初からホンダアクセスでキャリアをスタートさせた。大学で空力を研究していたことからエアロパーツの開発を志していたが、モデューロに関わる以上はサスペンションにも習熟する必要がある。
幸いにも、湯沢氏は先輩2人から直接バトンを渡される機会があった。ニュルブルクリンクでのテストの後、フランスを経由してイギリスに渡るドライブを任されたのだ。玉村氏と福田氏が彼の運転をじっと観察しているので、一瞬たりとも気を抜くことができない。そこで湯沢氏は、後席に乗る2人を寝かせてしまおうと考えた。そのためには、急な加速減速を避け、揺れの少ないドライビングを心がけなければならない。
湯沢氏がこのロングドライブで感得した極意は、そのままモデューロの目指すクルマの姿を示していた。スポーティーなドライビングの楽しさを満喫しながら安心して運転でき、快適な乗り心地であることが大切なのだ。モデューロの理想とする乗り味は、箇条書きで表せるようなものではない。身をもって経験し、自分の体感で受け取ることによってのみ理解することができる。コンプリートカーの「モデューロX」には、世代を超えて伝えられたクルマづくりの精髄が宿っている。
(文=鈴木真人/イラスト=日野浦剛/写真=荒川正幸、本田技研工業、ホンダアクセス)
次の記事:モデューロの歴史を彩る新旧3台を比較試乗
前の記事:モデューロの技が生きるミニバン2台を試す
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |