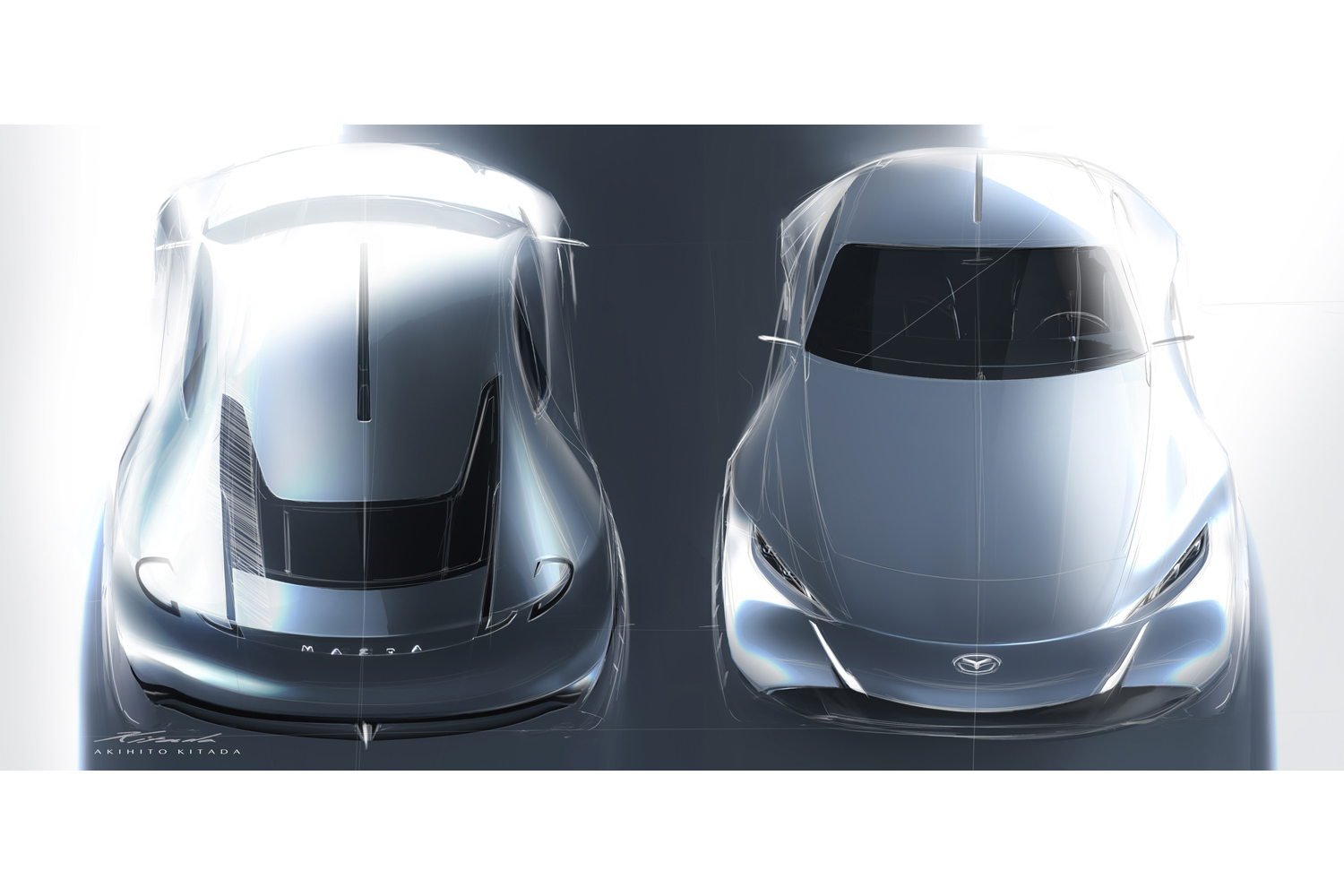いすゞオーナーズミーティング2011(前編)
2011.06.22 画像・写真2011年6月12日、愛知県岡崎市にある風光明媚(めいび)な「くらがり渓谷」の駐車場で、「いすゞオーナーズミーティング2011」が開かれた。SUVを除く乗用車生産から撤退してすでに20年近くが経過し、トラック、バスおよびディーゼルエンジンの専業メーカーとなって久しい「いすゞ」だが、かつては「ベレット」「117クーペ」「ジェミニ」「ピアッツァ」といった個性的な乗用車をもラインナップしていた。そうした「いすゞ」製の乗用車とSUV、一部の商用車をこよなく愛す人々によって、10数年前から毎年この時期に開催されているのが「いすゞオーナーズミーティング」である。当日、会場に全国から集まった約130台のなかから、リポーターの印象に残ったモデルを紹介しよう。(文と写真=沼田 亨)(後編につづく)

約130台のいすゞ車が集まった会場の一角。
-
 約130台のいすゞ車が集まった会場の一角。
約130台のいすゞ車が集まった会場の一角。
-
 エントリーした乗用車のなかで、もっとも古い年式の1966年前期「ベレット1500デラックス」。63年から73年まで約10年間にわたって作られたベレットは、マイナーチェンジの回数とバリエーションの多さでは日本車史上屈指の存在であり、その変遷を把握することは困難だが、基本形となるのがこれである。エンブレムなど細部を除いてはデビュー当初と同じ姿で、しかも新車からの「多摩5」ナンバー付きという希少車だ。
エントリーした乗用車のなかで、もっとも古い年式の1966年前期「ベレット1500デラックス」。63年から73年まで約10年間にわたって作られたベレットは、マイナーチェンジの回数とバリエーションの多さでは日本車史上屈指の存在であり、その変遷を把握することは困難だが、基本形となるのがこれである。エンブレムなど細部を除いてはデビュー当初と同じ姿で、しかも新車からの「多摩5」ナンバー付きという希少車だ。
-
 1966年後期「ベレット1300 4ドアサルーン」。64年秋に加えられた「1300」はスタンダード仕様のみで、これは2度目のフェイスリフトを受けたモデル。国産量産小型車としては初の4輪独立懸架とラック・ピニオンのステアリングを備え、 “スポーティ・サルーン”とうたってデビューしたベレットは、4段フロアシフトとセパレートシートの組み合わせが大半を占めるが、これは3段コラムシフト+ベンチシートというレアな個体。
1966年後期「ベレット1300 4ドアサルーン」。64年秋に加えられた「1300」はスタンダード仕様のみで、これは2度目のフェイスリフトを受けたモデル。国産量産小型車としては初の4輪独立懸架とラック・ピニオンのステアリングを備え、 “スポーティ・サルーン”とうたってデビューしたベレットは、4段フロアシフトとセパレートシートの組み合わせが大半を占めるが、これは3段コラムシフト+ベンチシートというレアな個体。
-
 1964年4月に日本で初めて“GT”を名乗った「ベレット1600GT」がシリーズに加わるが、これはその通称「ベレG」の最初期型。同年10月までの半年間しか作られておらず、残存車両はこれ1台きりかもしれない(現オーナーも、この会場に集ういすゞマニアもこれ以外に見たことがないという)超レアな個体である。しかも新車以来の「愛5」ナンバー付き。エンジンはSUツインキャブ付きの直4OHV1.6リッター(88ps)。
1964年4月に日本で初めて“GT”を名乗った「ベレット1600GT」がシリーズに加わるが、これはその通称「ベレG」の最初期型。同年10月までの半年間しか作られておらず、残存車両はこれ1台きりかもしれない(現オーナーも、この会場に集ういすゞマニアもこれ以外に見たことがないという)超レアな個体である。しかも新車以来の「愛5」ナンバー付き。エンジンはSUツインキャブ付きの直4OHV1.6リッター(88ps)。
-
 1966年秋に2度目のマイナーチェンジを受けた「ベレット1600GT」。直前のモデルではフロントグリルに埋め込まれていたフォグランプがバンパー上に移されるなど、顔つきが少々変わったほか、室内はインパネのデザインが一新された。エンジンも同じOHVの1.6リッターではあるが、新設計で、3ベアリングから5ベアリングになり、ボア/ストロークも変更された。懐かしい「コスミック」のアルミホイールがよく似合っている。
1966年秋に2度目のマイナーチェンジを受けた「ベレット1600GT」。直前のモデルではフロントグリルに埋め込まれていたフォグランプがバンパー上に移されるなど、顔つきが少々変わったほか、室内はインパネのデザインが一新された。エンジンも同じOHVの1.6リッターではあるが、新設計で、3ベアリングから5ベアリングになり、ボア/ストロークも変更された。懐かしい「コスミック」のアルミホイールがよく似合っている。
-
 またまた顔つきの違うベレGだが、これは1966年暮に加わった「ベレット1600GTファーストバック」。“fastback”なら「ファストバック」だろうと突っ込まれるかもしれないが、メーカー表記が「ファーストバック」なのである。とはいえ、いまだに「ファストフード」より「ファーストフード」がポピュラーなのはなぜなんだろう? それはともかく、1600GTをベースに受注生産されたモデルである。
またまた顔つきの違うベレGだが、これは1966年暮に加わった「ベレット1600GTファーストバック」。“fastback”なら「ファストバック」だろうと突っ込まれるかもしれないが、メーカー表記が「ファーストバック」なのである。とはいえ、いまだに「ファストフード」より「ファーストフード」がポピュラーなのはなぜなんだろう? それはともかく、1600GTをベースに受注生産されたモデルである。
-
 「ベレット1600GTファーストバック」の後ろ姿。Bピラーから後ろの形状が「1600GT」とは異なっており、3連テールランプも独自のデザイン。マニアに聞いたところでは前後バンパーも異なるそうだ。デビュー当時の価格は99万2000円で、中身が同じ「1600GT」(89万2000円)より10万円も高かった。ちなみにシリーズでいちばん安い「1300 2ドアサルーン」は52万円だったから、ほぼ2倍近かった。
「ベレット1600GTファーストバック」の後ろ姿。Bピラーから後ろの形状が「1600GT」とは異なっており、3連テールランプも独自のデザイン。マニアに聞いたところでは前後バンパーも異なるそうだ。デビュー当時の価格は99万2000円で、中身が同じ「1600GT」(89万2000円)より10万円も高かった。ちなみにシリーズでいちばん安い「1300 2ドアサルーン」は52万円だったから、ほぼ2倍近かった。
-
 1969年秋に追加された「ベレット1600GTR」。「117クーペ」から120psを発生する直4DOHC1.6リッターエンジンを移植した、ベレット史上最強のモデル。オレンジに黒塗りのボンネットとサイドストライプという派手なカラーは純正色である(ただし本来の黒はつや消し)。この個体は新車以来の「岡5」ナンバー付きだが、これが登場した頃には大都市圏はすでに2ケタナンバーになっていたため、シングルナンバーは希少だ。
1969年秋に追加された「ベレット1600GTR」。「117クーペ」から120psを発生する直4DOHC1.6リッターエンジンを移植した、ベレット史上最強のモデル。オレンジに黒塗りのボンネットとサイドストライプという派手なカラーは純正色である(ただし本来の黒はつや消し)。この個体は新車以来の「岡5」ナンバー付きだが、これが登場した頃には大都市圏はすでに2ケタナンバーになっていたため、シングルナンバーは希少だ。
-
 1971年秋、生涯最後のマイナーチェンジを受けた最終型の「ベレット1600GTR」。アップデートすべく樹脂を多用したフロントグリルと大きなテールランプを持つ。111万円という価格は、同じDOHC1.6リッターエンジンを積んだ新世代のライバルである「トヨタ・セリカ1600GT」(87万5000円)などと比べると割高な感が否めず、販売台数ではそれらより少ない。しかし、マニア向けだったゆえに残存率では(残存数でも?)上回る。
1971年秋、生涯最後のマイナーチェンジを受けた最終型の「ベレット1600GTR」。アップデートすべく樹脂を多用したフロントグリルと大きなテールランプを持つ。111万円という価格は、同じDOHC1.6リッターエンジンを積んだ新世代のライバルである「トヨタ・セリカ1600GT」(87万5000円)などと比べると割高な感が否めず、販売台数ではそれらより少ない。しかし、マニア向けだったゆえに残存率では(残存数でも?)上回る。
-
 「アルファ・ロメオ・ジュリアTIスーパー」のように、デュアルライトの内側に金網を張るなど、レーシングライクなモディファイを施された1971年「ベレット1600GTR」。オーナーによれば、15年ほど前にフィリピンに渡って現地でレースに出場、最近になって里帰りしたクルマだという。ホイールがアルミでなく、鉄チンのところがシブい。なお、ベレットの「GTR」は「GT type R」の略である。「タイプR」の元祖はこちらなのだ。
「アルファ・ロメオ・ジュリアTIスーパー」のように、デュアルライトの内側に金網を張るなど、レーシングライクなモディファイを施された1971年「ベレット1600GTR」。オーナーによれば、15年ほど前にフィリピンに渡って現地でレースに出場、最近になって里帰りしたクルマだという。ホイールがアルミでなく、鉄チンのところがシブい。なお、ベレットの「GTR」は「GT type R」の略である。「タイプR」の元祖はこちらなのだ。
-
 ベレット・サルーンのボディにツインキャブ仕様のGT用エンジンを載せたのが「ベレット・スポーツ」。右が1970年「1600 4ドアスポーツ」で、左が72年「1800 2ドアスポーツ」。「1800 2ドアスポーツ」は本来は最終型の顔つきだが、ひとつ前の「1600GTR」のマスクに整形している。さらにエンジンも本来のSOHC1.8リッターから「117クーペ」用のDOHC1.8リッターに換装されていた。
ベレット・サルーンのボディにツインキャブ仕様のGT用エンジンを載せたのが「ベレット・スポーツ」。右が1970年「1600 4ドアスポーツ」で、左が72年「1800 2ドアスポーツ」。「1800 2ドアスポーツ」は本来は最終型の顔つきだが、ひとつ前の「1600GTR」のマスクに整形している。さらにエンジンも本来のSOHC1.8リッターから「117クーペ」用のDOHC1.8リッターに換装されていた。
-
 カロッツェリア・ギア時代のジウジアーロが手がけた「117クーペ」。市販化されたのは1966年3月のジュネーブショーでのデビューから3年近くを経た68年12月。手作りの部分が多かった73年3月までのモデルは俗に「ハンドメイド」と総称されるが、そのなかでもマニアの間で「タイプ1」と呼ばれる69年10月までの最初期型がこれ。さらには「タイプ1」のなかでも「甲型」と「乙型」があるそうで……。アルミホイールはノン・オリジナル。
カロッツェリア・ギア時代のジウジアーロが手がけた「117クーペ」。市販化されたのは1966年3月のジュネーブショーでのデビューから3年近くを経た68年12月。手作りの部分が多かった73年3月までのモデルは俗に「ハンドメイド」と総称されるが、そのなかでもマニアの間で「タイプ1」と呼ばれる69年10月までの最初期型がこれ。さらには「タイプ1」のなかでも「甲型」と「乙型」があるそうで……。アルミホイールはノン・オリジナル。
-
 こちらは1969年10月以降の通称「タイプ2」。オリジナルのホイールを履いているが、それは別として「タイプ1」といったいどこが違うのよ? 答は次の写真にて。
こちらは1969年10月以降の通称「タイプ2」。オリジナルのホイールを履いているが、それは別として「タイプ1」といったいどこが違うのよ? 答は次の写真にて。
-
 外観上の違いはこれら2点、サイドマーカーランプとリアウィンドウ。写真上段が「タイプ1」で下段が「タイプ2」。ランプの違いは見ればわかるが、リアウィンドウは「タイプ2」が熱線プリント入りなのに対して「タイプ1」は熱線がなく、代わりにリアデフォッガーを備える(この個体ではウィンドウ上半分にフィルムが貼られている)。内装も細かい部分が異なる。なお「ハンドメイド」には、このほか「タイプ3」と「タイプ4」もあるそうだ……。
外観上の違いはこれら2点、サイドマーカーランプとリアウィンドウ。写真上段が「タイプ1」で下段が「タイプ2」。ランプの違いは見ればわかるが、リアウィンドウは「タイプ2」が熱線プリント入りなのに対して「タイプ1」は熱線がなく、代わりにリアデフォッガーを備える(この個体ではウィンドウ上半分にフィルムが貼られている)。内装も細かい部分が異なる。なお「ハンドメイド」には、このほか「タイプ3」と「タイプ4」もあるそうだ……。
-
 1973年春、「117クーペ」に大がかりな変更が施され、ボディパネルがプレス製になった。俗に「量産丸目」と呼ばれるモデルで、「ハンドメイド」に比べ全体的にラインがシャープになっている。フロントおよびリアエンドも改められてバンパーの位置が高くなり、フロントウィンカーはバンパーの上から下に移った。この個体は「ハンドメイド」用のフェンダーミラーを装着しており、ホイールはノン・オリジナル。
1973年春、「117クーペ」に大がかりな変更が施され、ボディパネルがプレス製になった。俗に「量産丸目」と呼ばれるモデルで、「ハンドメイド」に比べ全体的にラインがシャープになっている。フロントおよびリアエンドも改められてバンパーの位置が高くなり、フロントウィンカーはバンパーの上から下に移った。この個体は「ハンドメイド」用のフェンダーミラーを装着しており、ホイールはノン・オリジナル。
-
 1977年初頭のマイナーチェンジで「117クーペ」はヘッドライトが角形に改められ、通称「量産角目」に移行する。この個体は生涯最後となる79年暮のフェイスリフトの際に加わった、2リッターSOHCエンジン搭載の下級グレードをベースにした「ジウジアーロ・カスタム」。黒またはシルバーのボディにオレンジ色のストライプが入り、内装にも手が加えられている。アルミホイールは純正品。
1977年初頭のマイナーチェンジで「117クーペ」はヘッドライトが角形に改められ、通称「量産角目」に移行する。この個体は生涯最後となる79年暮のフェイスリフトの際に加わった、2リッターSOHCエンジン搭載の下級グレードをベースにした「ジウジアーロ・カスタム」。黒またはシルバーのボディにオレンジ色のストライプが入り、内装にも手が加えられている。アルミホイールは純正品。
-
 後ろ姿も美しい「117クーペ」。右から4台目までが「ハンドメイド」で、5台目以降が量産型。テールランプの形状のほか、リアバンパーの位置も異なる。
後ろ姿も美しい「117クーペ」。右から4台目までが「ハンドメイド」で、5台目以降が量産型。テールランプの形状のほか、リアバンパーの位置も異なる。
-
 「117クーペ」のベースとなった「フローリアン」は1台だけ参加。デビュー前は「いすゞ117」と呼ばれており、これもカロッツェリア・ギアの作品だが、担当したスタイリストはジウジアーロではない。発売は1967年だが、この個体は10年を経た77年のマイナーチェンジで加わったディーゼルエンジン搭載モデル。社内でデザインされた、オリジナルとは大きく異なる、俗に「獅子舞顔」などと呼ばれるアメリカ車風のマスクを着けている。
「117クーペ」のベースとなった「フローリアン」は1台だけ参加。デビュー前は「いすゞ117」と呼ばれており、これもカロッツェリア・ギアの作品だが、担当したスタイリストはジウジアーロではない。発売は1967年だが、この個体は10年を経た77年のマイナーチェンジで加わったディーゼルエンジン搭載モデル。社内でデザインされた、オリジナルとは大きく異なる、俗に「獅子舞顔」などと呼ばれるアメリカ車風のマスクを着けている。
-
 「フローリアン」の後継モデルで、1983年のデビュー当初は「フローリアン・アスカ」と称していた「アスカ」も1台だけ参加。これは85年に加えられた、直4SOHC2リッター・ターボ搭載モデルをベースに足まわりを固め、内外装をスポーティに装ったホットモデルの「アスカ・イルムシャー」。グリルはオリジナルとは異なっている。「イルムシャー」とは、当時いすゞの親会社だったGM傘下の「オペル」のチューナーである。
「フローリアン」の後継モデルで、1983年のデビュー当初は「フローリアン・アスカ」と称していた「アスカ」も1台だけ参加。これは85年に加えられた、直4SOHC2リッター・ターボ搭載モデルをベースに足まわりを固め、内外装をスポーティに装ったホットモデルの「アスカ・イルムシャー」。グリルはオリジナルとは異なっている。「イルムシャー」とは、当時いすゞの親会社だったGM傘下の「オペル」のチューナーである。
-
 本部テントには東日本大震災への寄付金箱が設置され、ショップが提供したいすゞ車用パーツのチャリティ・オークションも開催されていた。
本部テントには東日本大震災への寄付金箱が設置され、ショップが提供したいすゞ車用パーツのチャリティ・オークションも開催されていた。