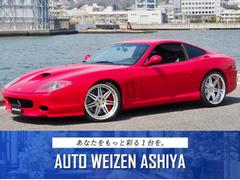「Ferrari木製モデラー 山田健二の世界」の会場から
2021.07.06 画像・写真2021年6月24日~30日、群馬県高崎市の高崎シティーギャラリーで企画展「Ferrari木製モデラー 山田健二の世界」が開かれた。作者の山田さんは御年77歳、長年勤めた百貨店を定年退職した16年前から、バルサ材を主体とするフェラーリのモデルをスクラッチビルドしている、非常にユニークなアマチュアモデラーである。
子どものころから図画工作が好きで、趣味としてプラモデルや木製の帆船模型などを作っていたという山田さん。いっぽうフェラーリとは、スーパーカーブームのときに、勤務していた百貨店で自ら企画したスーパーカーショーで出会った。
定年退職後の人生の過ごし方を考えたとき、思いついたのが大好きなフェラーリのスクラッチビルド。バルサ材を選んだのは、加工に特殊な道具や工具が不要で、材料の入手も容易でコストも安いからという。ただし小さなパーツは作りにくいので、必然的にビッグスケールとなった。処女作は1/8だったが迫力が足りず、1/5にしてみたら大きすぎ、数台作るうちに1/6に落ち着いたそうで、現在までの16年間に35点を製作している。ちなみに初期に手がけた3台は2000年代のF1マシンだったが、それ以後の製作対象はエンツォ・フェラーリ存命時のモデルに限定しているとのこと。
ある程度点数がそろったところで、2008年に最初の個展を開催。6回目となる今回の展示作品は木製モデルが16点、ワイヤモデルが1点、そして自己流というが、こちらも素晴らしい出来栄えの水彩画が約30点。その唯一無二の作品と、明るくサービス精神に富んだ山田さんの人柄に魅せられたファンで連日盛況だった会場から、魂の込められた作品群をご覧いただこう。
(文と写真=沼田 亨)
-

1/35山田さんが最も好きなフェラーリという1962年「250GTO」。今回は木製モデルとワイヤモデル、水彩画5点(ここに写っていないものもある)を展示した。
-

2/35好きなだけに、より高い完成度を求めて、作るのはこれで3台目という「250GTO」。ボディーの表面は、木工パテで目止めをした後にツヤあり白の水性ペイントをはけ塗り。それを研ぎ出した後に、フィニッシュはプラモデル用缶スプレーを5、6回重ね吹きするそうだ。
-

3/35「250GTO」のコックピット。5段MTのシフトゲートも表現されている。シートベルトはレザー素材だが、紙を使うこともあるとのこと。
-

4/35「250GTO」の3リッターV12 SOHCエンジン。コードやパイプ類などにワイヤを、ほかに金属メッシュも使っているが、あとは基本的にバルサ材。
-

5/35木製モデルと同じく1/6で作られたワイヤモデル。型に合わせたのではなく、フリーハンドで作ったというから驚く。「脳内に『250GTO』の3D CAD図面があるんですね!」と発言したところ、「そうおだてないでくれよ」と笑っていたが。
-
フェラーリ の中古車webCG中古車検索
-

6/35記念すべきフェラーリの処女作である1947年「125S」。実車の取材が難しいこの種のモデルの資料は、洋書などに掲載されている写真が基本。見逃せないのが、デアゴスティーニの組み立てモデルについてくる冊子。こうした歴史的なモデルの写真や、時に透視図などが掲載されているとのこと。あとは市販のモデルカーを参考にすることもあるという。それらの資料をベースに原寸大(1/6)の図面を手描きした後、製作工程に入る。
-

7/35「125S」の、ジョアッキーノ・コロンボ設計のV12 SOHCエンジン。数字が1気筒あたりの排気量を示す往年のフェラーリの法則に従って命名されており、つまり総排気量はわずか1.5リッターである。
-

8/351949年「166インター」。カロッツェリア・トゥーリング製ボディーに2リッターV12 SOHCエンジンを積んだロードカー。
-

9/35「166インター」のコックピット。メーターの盤面はカラープリンターやカラーコピーで製作。
-

10/351957年「250TRC」。アメリカのレースで活躍した後、現在はピーターセン自動車博物館に展示されているという「テスタロッサ」。ホイールのワイヤにはピアノ線を使っている。
-

11/35イタリア語で「赤い頭」を意味する「テスタロッサ」の車名のとおり、カムカバーが赤く塗られた「250TRC」の3リッターV12 SOHCエンジン。
-

12/35フロントエンジンの「250GTO」の後継として生まれたミドシップスポーツである1963年「250LM」。車名は250だが、生産台数32台のうち3リッターエンジンは最初の1台のみで、残りは275(3.3リッター)という。
-

13/35作り込まれた「250LM」のコックピット。この写真ではわかりにくいが、ハンドル位置は右である。
-

14/351966年のパリサロンでデビューしたコンセプトカーの「365P」。後の「マクラーレンF1」と同様、センターステアリングを採用した3座のミドシップスポーツである。
-

15/35「365P」のコックピット。ドライバーズシートが中央、その両脇にオフセットしたパッセンジャーズシートが備わるレイアウトも「マクラーレンF1」と同じだ。
-

16/35通称“デイトナ”こと「365GTB/4」。1977年のデイトナ24時間で、俳優のポール・ニューマンらのドライブにより5位に入賞したコンペティツィオーネ(レース仕様)がモデル。
-

17/35「365GTB/4」のフロントフェンダーに描かれたドライバー名。ポール・ニューマンの下は……こういうちゃめっ気が山田さんらしい。
-

18/35“テスタロッサ”仕様となった「365GTB/4」の4.4リッターV12 DOHCエンジン。ちなみに右端に見えるワイパーブレードは紙製である。
-

19/35トランクルーム内の燃料タンクも忠実に再現されている。
-

20/351976年「512BB」。より人気の高い「365GT4BB」ではなく512BBを選んだ理由は、「知り合いが所有していて実車取材ができたから」。おかげで付属工具までバッチリ再現されている。
-

21/351984年「288GTO」。来場していた山田さんの知り合いの女性が、見るなり「これ、山田さんのクルマじゃない?」。ご本人は笑いながら「だったらいいけどね~」。山田さんは縁あって10年前に1987年「328GTB」を入手し、1/1のオーナーでもあるのだ。
-

22/35「288GTO」の2.9リッターV8 DOHCツインターボユニット。写真右端の上下に見えるプレートの文字が気になり、老眼の目を細めて必死に眺めていたら「適当に描いてるんだから、そんなとこまで見ないでくれよ!」と苦笑していた。
-

23/351952年「500F2」を先頭に、年代順に並べられたフォーミュラマシン群。
-

24/35「500F2」。排気量2リッターのF2規格で実施された1952年のF1世界選手権で、ライバル不在により圧勝したマシン。
-

25/351気筒あたり500ccの2リッター直4 DOHCとなる「500F2」のエンジン。
-

26/351961年「156F1」。この年から1.5リッター規格となったF1で、フィル・ヒルをアメリカ人初のF1王座に就けたマシン。1.5リッターの6気筒を意味する車名のとおり、それまでF2に使われていたV6 DOHCのディーノユニットを積む。
-

27/351976年「312T2」。同年のドイツGPで瀕死(ひんし)の重傷を負いながらも、6週間後のイタリアGPで奇跡の復活を果たしたニキ・ラウダが駆った伝説のマシン。山田さんは2019年の5月に欧州旅行を楽しんだそうだが、「ウィーンを訪れたところ、聖ステファン教会の周辺がすごい人出なんだよ。何事かと思ったら、今日はラウダの葬儀だという。ラウダが亡くなったことはもちろん知ってたけど、その日が葬儀だなんてことはまったく知らずに訪ねたんだけどね」。呼ばれたのかもしれない。
-

28/35ボディーカウルを外した状態の1982年「126C2」。ベルギーGPの予選中の事故でエースドライバーのジル・ヴィルヌーヴを失うという悲劇に遭いながらも、同年のコンストラクターズタイトルを獲得したマシン。1.5リッターV6 DOHCツインターボユニットを積む。
-

29/35ヴィルヌーヴ以来のエースナンバーである「27」を付けた1985年「156/85」。同年に2勝を挙げたエースのミケーレ・アルボレートのマシンで、タイヤに描かれたセットナンバーがリアル。
-

30/35ほとんどのパーツがバルサ材で作られていることがよくわかる、製作過程で仮組みされた状態の1987年「F40」。各パーツは、基本的に積層したバルサ材をカッターで削り出していく。
-

31/35木製モデルと水彩画のコラボレーション。手前のモデルは1964年「275GTB」。
-

32/35F1のレースシーンを描いた作品群。
-

33/35モデルは雨にぬれた山田さんの愛車「328GTB」。
-

34/35山田健二さんと奥さまの由美子さん。山田さんは1944年3月28日生まれだそうで「(愛車である)『328』はエンツォが僕のためにつくってくれたんだよ(笑)」と語る。
-

35/35会場風景。