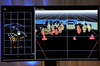高速道路での自動運転の研究に用いられるトヨタの新しい実験車。
-
 高速道路での自動運転の研究に用いられるトヨタの新しい実験車。
高速道路での自動運転の研究に用いられるトヨタの新しい実験車。
-
 説明会では予防安全システム「トヨタ・セーフティセンス」のほかにも、さまざまな先進技術の解説が行われた。こちらは「シースルー機能付きパノラミックビューモニター」のデモンストレーション。
説明会では予防安全システム「トヨタ・セーフティセンス」のほかにも、さまざまな先進技術の解説が行われた。こちらは「シースルー機能付きパノラミックビューモニター」のデモンストレーション。
-
 モニターには、車体を透過したように見えるよう画像処理された映像が表示される。運転席からは見えない位置にいる子供や自転車などの存在を、より分かりやすくドライバーに知らせることができるという。
モニターには、車体を透過したように見えるよう画像処理された映像が表示される。運転席からは見えない位置にいる子供や自転車などの存在を、より分かりやすくドライバーに知らせることができるという。
-
 ペダルの踏み間違えなどによる事故を予防、もしくは被害を軽減する誤発進抑制制御のデモ。これまでにもあった技術だが、新型はクリープによる前進でも作動するよう、改良されている。
ペダルの踏み間違えなどによる事故を予防、もしくは被害を軽減する誤発進抑制制御のデモ。これまでにもあった技術だが、新型はクリープによる前進でも作動するよう、改良されている。
-
 ITS専用の通信回線を利用した、協調型運転支援システムのデモ。交差点に備えられたセンサーが歩行者を検知。情報を受信した車両がモニター表示などでドライバーに注意を促すというものだ。
ITS専用の通信回線を利用した、協調型運転支援システムのデモ。交差点に備えられたセンサーが歩行者を検知。情報を受信した車両がモニター表示などでドライバーに注意を促すというものだ。
-
 自動操舵(そうだ)技術を用いたパーキングアシスト機能も、駐車スペースの選択を可能としたり、切り返し時の前進操作も自動でできるようになったりと、進化を遂げていた。
自動操舵(そうだ)技術を用いたパーキングアシスト機能も、駐車スペースの選択を可能としたり、切り返し時の前進操作も自動でできるようになったりと、進化を遂げていた。
-
 プリクラッシュブレーキのデモを行う、「セーフティセンスC」を搭載した「カローラ フィールダー」。ブレーキ作動前に警報を発する点が、他車のシステムにはない特徴となっている。
プリクラッシュブレーキのデモを行う、「セーフティセンスC」を搭載した「カローラ フィールダー」。ブレーキ作動前に警報を発する点が、他車のシステムにはない特徴となっている。
-
 歩行者検知機能を備えた「セーフティセンスP」のプリクラッシュブレーキ。車速が30km/h以下の場合は衝突前の停車が可能だが、トヨタでは利用者の過信を避けるため「停車する」という表現を避けている。
歩行者検知機能を備えた「セーフティセンスP」のプリクラッシュブレーキ。車速が30km/h以下の場合は衝突前の停車が可能だが、トヨタでは利用者の過信を避けるため「停車する」という表現を避けている。
-
 「セーフティセンスC」のセンサー。モノラルカメラとレーザーがひとまとめにされ、フロントウィンドウに装備される。
「セーフティセンスC」のセンサー。モノラルカメラとレーザーがひとまとめにされ、フロントウィンドウに装備される。
-
 こちらは「セーフティセンスP」のセンサー。カメラはフロントウィンドウに、ミリ波レーダーはフロントグリルのバッジ内に装備される。
こちらは「セーフティセンスP」のセンサー。カメラはフロントウィンドウに、ミリ波レーダーはフロントグリルのバッジ内に装備される。
-
 同じ発表会で披露された「LEDアレイAHS(Adaptive High beam System)」のデモの様子。遮蔽板によって光をさえぎるのではなく、LED球の点灯そのものを制御することで、より精密な制御を実現している。2015年に発売する新型車より採用を予定。
同じ発表会で披露された「LEDアレイAHS(Adaptive High beam System)」のデモの様子。遮蔽板によって光をさえぎるのではなく、LED球の点灯そのものを制御することで、より精密な制御を実現している。2015年に発売する新型車より採用を予定。
-
 トヨタの自動運転実験車。奥の「レクサスLS」は北米での実験車をベースに、日本の一般道での自動運転を実現するために開発したもの。手前の「レクサスGS」が、高速道路での自動運転を想定した、新開発の実験車となる。
トヨタの自動運転実験車。奥の「レクサスLS」は北米での実験車をベースに、日本の一般道での自動運転を実現するために開発したもの。手前の「レクサスGS」が、高速道路での自動運転を想定した、新開発の実験車となる。
-
 トヨタ自動車において、安全技術開発を統括する吉田守孝専務。
トヨタ自動車において、安全技術開発を統括する吉田守孝専務。
-
 新しい実験車に加え、自動運転技術の進化に貢献する新技術も披露された。こちらはレーザーの反射で対象物を認識する「SPAD LIDER」という装置。
新しい実験車に加え、自動運転技術の進化に貢献する新技術も披露された。こちらはレーザーの反射で対象物を認識する「SPAD LIDER」という装置。
-
 「SPAD LIDER」の認識情報を可視化したもの。これまでは照射器そのものを回転させて周囲にレーザーを照射していたが、新開発の機器はポリゴンミラーによってレーザーを拡散。従来比6分の1という、大幅なコンパクト化を実現している。
「SPAD LIDER」の認識情報を可視化したもの。これまでは照射器そのものを回転させて周囲にレーザーを照射していたが、新開発の機器はポリゴンミラーによってレーザーを拡散。従来比6分の1という、大幅なコンパクト化を実現している。
『第269回:いよいよトヨタも本気モード 最新の予防安全システムと自動運転技術の現状を探る』の記事ページへ戻る