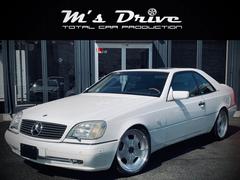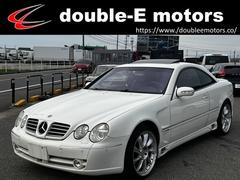メルセデス・ベンツCL550(FR/7AT)【試乗記】
無駄を楽しむ 2007.03.07 試乗記 メルセデス・ベンツCL550(FR/7AT)……1595万6000円
7年振りにフルモデルチェンジされた、ベンツのラクシャリークーペ「CLクラス」。快適で豪華な新型に乗ってみると……。
ラクシュリーの頂点
「Sクラス」の贅沢さと最新技術を受け継ぎながら、Sクラスよりもさらにパーソナルなイメージを打ち出すラクシュリーカーがCLクラスである。Sクラスのフルモデルチェンジに続き、このCLクラスも2006年後半に新世代を迎え、日本でも販売がスタートした。
旧型に比べて、全長で75mm、全幅で15mm、全高で20mm拡大したCLクラスは、物理的なサイズアップ以上に大きく見える。張り出した前後のフェンダーや大きな弧を描くルーフライン、そして、スリーポインテッドスターを中心に納めた押し出しの強いグリルのデザインがそう思わせるのだろうか? 堂々たる姿はラクシュリーの頂点にふさわしいが、クーペとしてのエレガントさがやや不足気味なのが、個人的には気になるが……。
しかし、室内に目をやれば、上質なレザーやウッドで覆われたパネルに、光り輝くスイッチ類があしらわれた様子は贅沢の一言で、Sクラスと細部が異なるデザインには、クーペらしいスポーティさが感じ取れた。
インパネは、中央に配置される大きな速度計がデザインを特徴づけている。しかもこの部分は8インチディスプレイに表示される映像である。ステアリングコラム右側から伸びる「ダイレクトセレクト」と呼ばれるシフトレバーや、センターコンソール部のコントローラーに各種スイッチを統合した「COMMANDシステム」とともに、すでにSクラスでもお馴染みの装備だ。
このうち、速度計だけはいまだに違和感を拭えないが、CLクラスに標準装着される暗視システム「ナイトビューアシスト」を使って、夜間の映像を速度計の代わりに表示させ、その明瞭な画像を見せつけられると、「バーチャルな速度計も時代の流れか」と思えてしまう。
至れり尽くせり
そんな最新技術盛りだくさんのCLクラスから、今回は5.5リッターV8を搭載するCL550を試乗に引っ張り出した。車検証を見ると、車両重量は2000kgと、クーペとしては重量級だ。しかし、最高出力387ps/6000rpm、最大トルク54.0kgm/2800-4800rpmを誇る自然吸気のV8DOHCユニットは余裕の塊である。
CLクラスでは、センターコンソールの「S/C/M」の切り替えスイッチにより、オートマチックや「アクティブ・ボディ・コントロール」と呼ばれる電子制御ダンパーの設定が変えられるが、最も使用頻度が高いと思われるC(=コンフォート)モードを選ぶと、オートマチックは自動的に2速発進を選択するにもかかわらず、出足の鈍さとはまるで無縁。走り出しても、せいぜい2000rpmも回っていれば一般道なら事足りる余裕である。
その一方で、中回転域から上に向かう力強さもこのエンジンの美点で、4000rpmあたりからレブリミット手前の6000rpmにかけてのスムーズでリニアな加速感は、自然吸気エンジン好きにはたまらない感触なのである。
オートマチックに関して、ダイレクトセレクトそのものにはさほど感銘は受けなかったものの、ステアリング裏のシフトスイッチが、左側でダウン、右側でアップと独立した機能を持つようになり、S/C/Mのいずれを選んでも機能するのは、高速道路でエンジンブレーキを必要とするときなど実に便利だ。ちなみに、Sはスポーツ、Mはマニュアルを意味し、センターコンソールのスイッチを押すごとにモードが切り替わる。
どこまでも快適に速く
それと同時に、アクティブ・ボディ・コントロールのセッティングも変わるのがCLクラスの特徴だ。エアサスペンションを備えるSクラスに対し、CLは機械式スプリングを採用し、クルマの性格の違いも手伝って、同じコンフォートモードでもCLクラスのほうがやや硬めの乗り心地を示す。それでも路面の荒れを直接ドライバーに伝えることはなく、しなやかさと快適さが実に心地いい。
高速では、コンフォートのままでは小さな上下動が気になる場面があり、そんなときにはスポーツまたはマニュアルを選ぶことで、フラットな乗り心地を手に入れることができる。直進性は極めて高く、高速コーナーでの安定感もまた高いので、長時間の運転もまるで苦にならない。
ワインディングロードでは、サスペンションをハード側に切り替えても、それなりにロールを許してしまうが、それでも5m強のボディサイズからすれば十分にスポーティだ。
さらにスポーティな性格を望むなら、SLクラスという選択肢が用意されているわけで、スポーティさよりも快適さや豪華さが重視されるCLクラスとの間で、うまく棲み分けが図られているということである。
実際、CL550を運転していると、最初のうちこそそのパワーを楽しんだりしたが、次第にジェントルなドライビングスタイルに変わっていった。性能の余裕がドライバーの心に余裕をもたらすのだろう。「それじゃ、有り余るパワーなんて無駄じゃないか?」という話になるが、そもそもラクシュリークーペは、その無駄を楽しむ存在なのである。
(文=生方聡/写真=峰昌宏/2007年3月)

生方 聡
モータージャーナリスト。1964年生まれ。大学卒業後、外資系IT企業に就職したが、クルマに携わる仕事に就く夢が諦めきれず、1992年から『CAR GRAPHIC』記者として、あたらしいキャリアをスタート。現在はフリーのライターとして試乗記やレースリポートなどを寄稿。愛車は「フォルクスワーゲンID.4」。
-
BYDシールAWD(4WD)【試乗記】 2026.1.17 BYDのBEVサルーン「シール」の機能アップデートモデルが登場。強化のポイント自体はそれほど多くないが、4WDモデルの「シールAWD」は新たに電子制御式の可変ダンパーを装備したというから見逃せない。さまざまなシーンでの乗り心地をチェックした。
-
マツダCX-60 XDドライブエディション ナッパレザーパッケージ(4WD/8AT)【試乗記】 2026.1.14 「マツダCX-60」に新グレードの「XDドライブエディション ナッパレザーパッケージ」が登場。スポーティーさと力強さ、上質さを追求したというその中身を精査するとともに、国内デビューから3年を経た“ラージ商品群第1弾”の成熟度をチェックした。
-
カワサキKLX230シェルパS(6MT)【レビュー】 2026.1.13 その出来には“セロー乗り”も太鼓判!? カワサキのトレイルバイク「KLX230シェルパ」に、ローダウン仕様の「シェルパS」が登場。安心の足つき性で間口を広げた一台だが、実際に走らせてみると、ストリートでも楽しめるオールラウンダーに仕上がっていた。
-
メルセデス・ベンツC220dラグジュアリー(FR/9AT)【試乗記】 2026.1.12 輸入車における定番の人気モデル「メルセデス・ベンツCクラス」。モデルライフ中にも年次改良で進化し続けるこのクルマの、現在の実力はいかほどか? ディーゼルエンジンと充実装備が魅力のグレード「C220dラグジュアリー」で確かめた。
-
日産ルークス ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション(FF/CVT)【試乗記】 2026.1.10 日産の軽スーパーハイトワゴン「ルークス」がフルモデルチェンジ。「見えない危険が……」のテレビCMでお茶の間をにぎわせているが、走る、曲がる、止まるをはじめとしたクルマ全体としての仕上がりはどうか。最上級グレードをテストした。
-
![フェラーリ12チリンドリ(後編)]() NEW
NEW
フェラーリ12チリンドリ(後編)
2026.1.18思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「フェラーリ12チリンドリ」に試乗。前編では伝家の宝刀であるV12エンジンを絶賛した山野。後編ではコンビを組むシャシーの印象を余すところなく聞いてみた。 -
![BYDシールAWD(4WD)【試乗記】]()
BYDシールAWD(4WD)【試乗記】
2026.1.17試乗記BYDのBEVサルーン「シール」の機能アップデートモデルが登場。強化のポイント自体はそれほど多くないが、4WDモデルの「シールAWD」は新たに電子制御式の可変ダンパーを装備したというから見逃せない。さまざまなシーンでの乗り心地をチェックした。 -
![新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る]()
新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る
2026.1.16デイリーコラム英国のモーターサイクル史にあまたの逸話を残してきた名門、ノートンが、いよいよ再始動! その数奇な歴史を振り返るとともに、ミラノで発表された4台の次世代モデルを通して、彼らが思い描く未来像に迫った。 -
![第858回:レースの技術を市販車に! 日産が「オーラNISMO RSコンセプト」で見せた本気]()
第858回:レースの技術を市販車に! 日産が「オーラNISMO RSコンセプト」で見せた本気
2026.1.15エディターから一言日産が「東京オートサロン2026」で発表した「オーラNISMO RSコンセプト」。このクルマはただのコンセプトカーではなく、実際のレースで得た技術を市販車にフィードバックするための“検証車”だった! 新しい挑戦に込めた気概を、NISMOの開発責任者が語る。 -
![ルノー・グランカングー クルール]()
ルノー・グランカングー クルール
2026.1.15画像・写真3列7座の新型マルチパーパスビークル「ルノー・グランカングー クルール」が、2026年2月5日に発売される。それに先駆けて公開された実車の外装・内装を、豊富な写真で紹介する。 -
![市街地でハンズオフ運転が可能な市販車の登場まであと1年 日産の取り組みを再確認する]()
市街地でハンズオフ運転が可能な市販車の登場まであと1年 日産の取り組みを再確認する
2026.1.15デイリーコラム日産自動車は2027年に発売する車両に、市街地でハンズフリー走行が行える次世代「ProPILOT(プロパイロット)」を搭載する。その発売まであと1年。革新的な新技術を搭載する市販車の登場は、われわれにどんなメリットをもたらすのか。あらためて考えてみた。