第46回:『唯一無二』日野コンマース(1960-62)(その1)
2006.09.13 これっきりですカー第46回:『唯一無二』日野コンマース(1960-62)(その1)

|
積載量4トン以上の中型・大型トラック市場で、1973年以来32年連続でナンバーワンの座を占めている日野自動車。
大型車のトップメーカーであるその日野が、かつては乗用車もラインナップしていたことはご存知の方もおられることだろう。では、そのいっぽうでこうした進歩的なモデルも存在していたことについてはいかがだろうか?
 拡大 拡大
|
 拡大 拡大
|
■元祖FFワンボックス
……駆動方式がFFだったことも、商用車では非常に珍しかった。ライフバンなど軽乗用車ベースのボンネット型バンを除くと、当時の日本で前輪駆動の商用車といえば、同じ年の4月に発売された小型トラック「いすゞエルフ・マイパック」のみ。前例としても、60年代初頭に日野自動車がリリースした小型ワンボックスバン「コンマース」があるだけだった。
乗用車の世界でも、日本はヨーロッパに比べFF化が遅かったこともその理由のひとつではあるが、そもそも商用車は貨物を積載すると前輪荷重が小さくなってしまうため、FFは適していないのだ。その証拠にステップバン以降も今日に至るまで、ワンボックスあるいはそれに準ずるスタイルの商用バンにはFFは採用されていない……
これは「これっきりですカー」の「第20回『生まれてくるのが早すぎた』ホンダライフ・ステップバン(1972〜74)(その1)」より抜粋したものであるが、ここでただ1台の前例として車名が挙がっていた「日野コンマース」が、今回の主役である。
ちなみにこの文章が書かれたのは2003年8月だが、それから2年以上を経過した今も、ワンボックスあるいはそれに準ずるスタイルのFF商用バンというものは存在しない。しかも「ステップバン」はセミキャブオーバー型だったのに対して、「コンマース」は画像をご覧になればおわかりのとおり完全なキャブオーバー型。その意味では、日本車史上唯一無二の存在なのである。
より正確に言えば、「コンマース」は商用バンのみではなかった。日野自身は「低床式万能商業車」と称していたが、10人乗りの乗用ワゴン(5ナンバー)、11人乗りの小型バス(2ナンバー)もラインナップされていたのだ。つまりエンジン搭載位置や駆動方式こそ異なるものの、この種の多目的トランスポーターの先輩格である「フォルクスワーゲン・タイプ2」に近い成り立ちを持っていたことがわかるが、実際にコンマースはタイプ2を参考に企画されたものだという。
その「コンマース」は1959年10月に発表され、翌60年2月に発売されたのだが、日野にとって独自設計による初の小型四輪車でもあった。では「コンマース」登場前後の日野はいったいどんな状況にあったのか、ざっと紹介してみよう。
 拡大 拡大
|
 拡大 拡大
|
■ルノーに学んだ小型車づくり
そもそも日野自動車の歴史は、古くは1918年に「東京瓦斯電気工業株式会社」の自動車部がトラック製造に乗り出したことに遡る。その後30年代後半から戦時下の国策のもと他の自動車会社との合併や分離独立を経て42年に「日野重工業株式会社」となり、軍用車両を生産していたが、戦後は大型トラック・バスの専門メーカー「日野ヂーゼル工業株式会社」として再出発した。
大型車部門の業績が安定すると、急速に拡大しつつあった乗用車市場への進出を決定したが、この分野での経験が皆無なことから、外国の先進メーカーから技術導入を図った。ほぼ同時期に同じ目的から、日産は英オースチンと、いすゞは英ルーツ・グループと技術提携を結んだが、日野がパートナーに選んだのは仏ルノー公団。1953年4月から同社の「ルノー4CV」のライセンス生産を開始したのである。
4CVは戦後ルノーの復興の礎となったモデルで、1947年のデビューながら軽量モノコックボディ、4輪独立懸架、ラック・ピニオンのステアリングなど進歩的な機構を備えた小型大衆車だった。最高出力21ps/4000rpmを発生する水冷直4OHV748ccエンジンをリアに積み、3段ギアボックスを介して後輪を駆動するリアエンジン・リアドライブ(RR)で、車重わずか560kgの4ドアボディを最高速度100km/hまで引っ張ると公表されていた。
「日野ルノー(PA型)」と名付けられた国産4CVは、当初は本国から部品を輸入して組み立てるいわゆるノックダウン生産だったものの、徐々に国産化比率を高め、57年9月には完全国産化を達成していた。
話は前後するが、コンマースの発売から約1年後の61年4月、日野はルノー4CVの国産化を通じて学んだノウハウをベースに独自開発した乗用車「コンテッサ」を発表する。
「コンテッサ」は4CVよりひとまわり大きいボディ、エンジンを持つRRのセダンだったが、そのスタイリングには当時の日本車の多くがそうだったように、アメリカ車の影響が見られる。蛇足になるが、本国フランスで4CVの上級モデルとして57年に登場した「ドーフィン」と比べると、なかなか興味深い。
日本車史上唯一のキャブオーバー型FFトランスポーターである「コンマース」は、こうした状況にあったメーカーから送り出されたのだった。(つづく)
(文=田沼 哲/2006年1月)
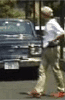
田沼 哲
NAVI(エンスー新聞)でもお馴染みの自動車風俗ライター(エッチな風俗ではない)。 クルマのみならず、昭和30~40年代の映画、音楽にも詳しい。
-
第53回:「これっきりモデル」in カローラ・ヒストリー〜その4「謎のスプリンター」〜 2006.11.23 トヨタ・スプリンター1200デラックス/1400ハイデラックス(1970-71)■カローラからの独立1970年5月、カローラが初めて迎えたフルモデルチェンジに際して、68年に初代カローラのクーペ版「カローラ・スプリンター」として登場したスプリンターは、新たに「トヨタ・スプリンター」の名を与えられてカローラ・シリーズから独立。同時にカローラ・シリーズにはボディを共有する「カローラ・クーペ」が誕生した。基本的に同じボディとはいえ、カローラ・セダンとほとんど同じおとなしい顔つきのカローラ・クーペに対して、独自のグリルを持つスプリンターは、よりスポーティで若者向けのムードを放っていた。バリエーションは、「カローラ・クーペ」「スプリンター」ともに高性能版の「1200SL」とおとなしい「1200デラックス」の2グレード。エンジンは初代から受け継いだ直4OHV1166ccで、「SL」にはツインキャブを備えて最高出力77ps/6000rpmを発生する3K-B型を搭載。「デラックス」用のシングルキャブユニットはカローラとスプリンターで若干チューンが異なり、カローラ版は68ps/6000rpm(3K型)だが、スプリンター版は圧縮比が高められており73ps/6600rpm(3K-D型)を発生した。また、前輪ブレーキも双方の「SL」と「スプリンター・デラックス」にはディスクが与えられるのに対して、「カローラ・クーペ・デラックス」ではドラムとなっていた。つまり外観同様、中身も「スプリンター」のほうがよりスポーティな味付けとなっていたのである。しかしながら、どういうわけだか「スプリンター1200デラックス」に限って、そのインパネには当時としても時代遅れで地味な印象の、角形(横長)のスピードメーターが鎮座していたのだ。
-
第52回:「これっきりモデル」in カローラ・ヒストリー〜その3「唯一のハードトップ・レビン」〜 2006.11.15 トヨタ・カローラ・ハードトップ1600レビン(1974-75)■レビンとトレノが別ボディに1974年4月、カローラ/スプリンターはフルモデルチェンジして3代目となった。ボディは2代目よりひとまわり大きくなり、カローラには2/4ドアセダンと2ドアハードトップ、スプリンターには4ドアセダンと2ドアクーペが用意されていた。このうち4ドアセダンは従来どおり、カローラ、スプリンターともに基本的なボディは共通で、グリルやリアエンドなどの意匠を変えて両車の差別化を図っていた。だが「レビン」や「トレノ」を擁する2ドアクーペモデルには、新たに両ブランドで異なるボディが採用されたのである。カローラはセンターピラーのない2ドアハードトップクーペ、スプリンターはピラー付きの2ドアクーペだったのだが、単にピラーの有無ということではなくまったく別のボディであり、インパネなど内装のデザインも異なっていた。しかしシャシーはまったく共通で、「レビン」(型式名TE37)および「トレノ」(同TE47)についていえば、直4DOHC1.6リッターの2T-G/2T-GR(レギュラー仕様)型エンジンはじめパワートレインは先代から踏襲していた。ボディが大型化したこと、および双方とも先代ほど簡素でなくなったこともあって車重はレビン930kg、トレノ925kgと先代より60〜70kg前後重くなった。
-
第51回:「これっきりモデル」in カローラ・ヒストリー〜その2「狼の皮を被った羊(後編)」〜 2006.11.10 トヨタ・カローラ・レビンJ1600/スプリンター・トレノJ1600(1973-74)■違いはエンブレムのみ1972年3月のレビン/トレノのデビューから半年に満たない同年8月、それらを含めたカローラ/スプリンターシリーズはマイナーチェンジを受けた。さらに翌73年4月にも小規模な変更が施されたが、この際にそれまで同シリーズには存在しなかった、最高出力105ps/6000rpm、最大トルク14.0kgm/4200rpmを発生する直4OHV1.6リッターツインキャブの2T-B型エンジンを積んだモデルが3車種追加された。うち2車種は「1600SL」と「1600SR」で、これらはグレード名から想像されるとおり既存の「1400SL」「1400SR」のエンジン拡大版である。残り1車種には「レビンJ1600/トレノJ1600」という名称が付けられていたが、これらは「レビン/トレノ」のボディに、DOHCの2T-Gに代えてOHVの2T-B型エンジンを搭載したモデルだった。なお、「レビンJ1600/トレノJ1600」の「J」は「Junior(ジュニア)」の略ではないか言われているが、公式には明らかにされていない。トランクリッド上の「Levin」または「Trueno」のエンブレムに追加された「J」の文字を除いては、外から眺めた限りでは「レビン/トレノ」とまったく変わらない「レビンJ/トレノJ」。だがカタログを眺めていくと、エンジンとエンブレムのほかにも「レビン/トレノ」との違いが2点見つかった。
-
第50回:「これっきりモデル」in カローラ・ヒストリー〜その1「狼の皮を被った羊(前編)」〜 2006.11.6 誕生40周年を迎えた2006年10月に、10代目に進化したトヨタ・カローラ。それを記念した特別編として、今回は往年のカローラおよびその兄弟車だったスプリンター・シリーズに存在した「これっきりモデル」について紹介しよう。かなりマニアックな、「重箱の隅」的な話題と思われるので、読まれる際は覚悟のほどを……。トヨタ・カローラ・レビンJ1600/スプリンター・トレノJ1600(1973-74)■スパルタンな走りのモデル型式名TE27から、通称「27(ニイナナ)レビン/トレノ」と呼ばれる、初代「カローラ・レビン1600/スプリンター・トレノ1600」。英語で稲妻を意味する「LEVIN」、いっぽう「TRUENO」はスペイン語で雷鳴と、パンチの効いた車名を冠した両車は、2代目カローラ/スプリンター・クーペのコンパクトなボディに、セリカ/カリーナ1600GT用の1.6リッターDOHCエンジンをブチ込み、オーバーフェンダーで武装した硬派のモデルとして、1972年の登場から30余年を経た今なお、愛好家の熱い支持を受けている。「日本の絶版名車」のような企画に必ずといっていいほど登場する「27レビン/トレノ」のベースとなったのは、それらが誕生する以前のカローラ/スプリンターシリーズの最強モデルだった「クーペ1400SR」。SRとは「スポーツ&ラリー」の略で、カローラ/スプリンター・クーペのボディに、ツインキャブを装着して最高出力95ps/6000rpm、最大トルク12.3kgm/4000rpmを発生する直4OHV1407ccエンジンを搭載したスポーティグレードだった。ちなみにカローラ/スプリンター・クーペには、1400SRと同じエンジンを搭載した「1400SL」というモデルも存在していた。「SL」は「スポーツ&ラクシュリー」の略なのだが、このSLに比べるとSRは装備が簡素で、より硬い足まわりを持った、スパルタンな走り重視のモデルだったのである。
-
第49回:『唯一無二』日野コンマース(1960-62)(その4) 2006.9.13 新しいコンセプトのトランスポーターとして、1960年2月に発売された日野コンマース。だがそのセールスははかばかしくなかった。
-
![クルマの乗り味の“味”って何だ?]() NEW
NEW
クルマの乗り味の“味”って何だ?
2026.1.20あの多田哲哉のクルマQ&A「乗り味」という言葉があるように、クルマの運転感覚は“味”で表現されることがある。では、車両開発者はその味をどう解釈して、どんなプロセスで理想を実現しているのか? 元トヨタのエンジニア、多田哲哉さんに聞いた。 -
![プジョー208 GTハイブリッド(FF/6AT)【試乗記】]() NEW
NEW
プジョー208 GTハイブリッド(FF/6AT)【試乗記】
2026.1.20試乗記「プジョー208」にマイルドハイブリッド車の「GTハイブリッド」が登場。仕組みとしては先に上陸を果たしたステランティス グループの各車と同じだが、小さなボディーに合わせてパワーが絞られているのが興味深いところだ。果たしてその乗り味は? -
![ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】]()
ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】
2026.1.19試乗記ベントレーのラグジュアリークーペ「コンチネンタルGT」のなかでも、ウェルビーイングにこだわったという「アズール」に試乗。控えめ(?)な680PSのハイブリッドがかなえる走りは、快適で満ち足りていて、ラグジュアリーカーの本分を感じさせるものだった。 -
![第327回:髪もクルマもナイスファイト!]()
第327回:髪もクルマもナイスファイト!
2026.1.19カーマニア人間国宝への道清水草一の話題の連載。日産の新型「ルークス」で夜の首都高に出撃した。しっかりしたシャシーとターボエンジンのパワフルな走りに感心していると、前方にスーパーカーの姿を発見。今夜の獲物は「フェラーリ・ローマ」だ! -
![日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!]()
日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!
2026.1.19デイリーコラムアメリカからの外圧による制度変更で、北米生産モデルの国内導入を決めたトヨタ。同様に、今後日本での販売が期待できる「海外生産の日本車」には、どんなものがあるだろうか? 清水草一が検証してみた。 -
![フェラーリ12チリンドリ(後編)]()
フェラーリ12チリンドリ(後編)
2026.1.18思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「フェラーリ12チリンドリ」に試乗。前編では伝家の宝刀であるV12エンジンを絶賛した山野。後編ではコンビを組むシャシーの印象を余すところなく聞いてみた。

















