第43回:『トリノの風薫る』プリンス・スカイラインスポーツ(1962-63)(その2)
2006.09.13 これっきりですカー第43回:『トリノの風薫る』プリンス・スカイラインスポーツ(1962-63)(その2)
 拡大 拡大
|
 拡大 拡大
|
 拡大 拡大
|
■デザインはミケロッティ
「スカイラインスポーツ」のプロジェクトは、1955年に欧米の自動車および航空機産業を視察旅行した、当時プリンスの取締役設計部長だった中川良一氏が、イタリアのカロッツェリアとそこでつくられるスポーツカーの美しさに感銘を受けたことに端を発したと言われている。
最初の項で述べたように、先進的なメーカーであったプリンスは、いち早くデザイン/スタイリングの重要性にも目を向けていたが、その旅でカーデザインの本場はイタリアであることを確信したようで、59年に当時デザイン課長だった井上猛氏をイタリアに派遣、約2年にわたって氏をイタリアで学ばせていた。そして、いつかわが社でもすばらしいイタリアンデザインのスポーツカーを、という中川氏の夢も、井上氏の渡伊を機に具体化することになる。
プリンスでは、スカイラインスポーツ開発の狙いとして三つの理由を掲げていた。一つ目はこれから先、純粋にドライブを楽しめるクルマの需要が予測されたこと。二つ目は向上しつつある国産車デザインのさらなる飛躍のための刺激剤となること。そして三つ目は、対米輸出戦略の切り札となることだった。それらを実現するために、イタリアのカロッツェリアにデザインを発注することを決定したのだった。その命を受けた井上氏は、スタディのかたわらプロジェクトにふさわしい人材を調査した結果、トリノ在住の「ジョバンニ・ミケロッティ」に白羽の矢を立てた。
TR4、スピットファイア、ヘラルドや2000などのトライアンフ各車、BMW700、同1500、そして日野コンテッサ1300などを手がけたスタイリストとして知られるミケロッティは当時39歳。すでに20年以上のキャリアを持ち、脂の乗りきった時期だった。
一説によると、プリンスでは当初「ピニンファリーナ」に打診したそうだが、デザイン料が桁違いに高かったためにあきらめ、ミケロッティに依頼したともいわれているが、真偽のほどは不明である。
ちなみにデザイン・コンサルタントを行うのは一国一社に限っていたピニンファリーナは、それから数年後に日産と契約、2代目ブルーバードとセドリックを手がけた。
 拡大 拡大
|
 拡大 拡大
|
 拡大 拡大
|
■製作期間半年足らず
60 年5月、プリンスは「ミケロッティ」とデザインの、そして「アレマーノ」と2台のプロトタイプ製作の契約を締結する。ミケロッティは純粋なデザインスタジオだったため、ミケロッティと旧知の関係にあり、主にコーチワークを行っていたカロッツェリアであるアレマーノが製作を担当したのである。
そして今日ではありえないことだが、プリンスでは両社に支払う金額を公表していた。その「公称値」によれば、ミケロッティへのデザイン料が500万リラ(邦貨約290万円)、アレマーノへの製作費が1台あたり800万リラ(同約464万円)の合計2100万リラ(同約1218万円)とのこと。またデザイン料は買い取りのため、生産台数ごとのロイヤリティは発生しない、ということまで公にされていた。
その後の進行はじつにスピーディで、同年 10月末には日本から送られた2台の「初代グロリア」用ベアシャシーに5座クーペと4座コンバーチブル・ボディを架装したプロトタイプが完成、11月3日から開かれた第42回トリノショーに「スカイラインスポーツ」として出展され、好評を博した。
今日でいうところの、もちろん日本車としては初の海外ショーにおける「ワールドプレミア」であり、ブースには和服をまとったイタリア女性のコンパニオンが寄り添っていたという。
契約締結からデビューまで半年足らずという短期間、しかも互いに初めて組んだパートナーであるにもかかわらず、デザインの本場で認められるほどクオリティの高い仕事をなしえた理由には、ミケロッティの才能、そしてアレマーノおよび周辺産業の腕の確かさ、懐の深さが挙げられるだろう。加えて前出の井上氏がデザイナー/スタイリストとしてはもちろんのこと、各方面でプロデューサーあるいはコーディネーターとして尽力したであろうことは、想像に難くない。

|
肝心のミケロッティによるスタイリングは、俗に「チャイニーズ・アイ」と呼ばれる斜めに配置されたデュアル・ヘッドライトが最大の特徴。実用車のシャシーに架装されたためやや腰高な感じは否めないが、それでもベースカーに比べれば格段にスマートに変身しており、全体の雰囲気はアルファ・ロメオ2000スパイダーやランチア・フラミニアクーペなど、同時代のイタリア製高級パーソナルカーに通じるものがあった。メカニズム関係はグロリア用をそのまま流用していたが、エンジンはGB4型と呼ばれる直4OHV1862ccを、吸排気系を改良して最高出力を80psから90psまで高めて搭載していた。(つづく)(文=田沼 哲/2005年11月)
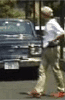
田沼 哲
NAVI(エンスー新聞)でもお馴染みの自動車風俗ライター(エッチな風俗ではない)。 クルマのみならず、昭和30~40年代の映画、音楽にも詳しい。
-
第53回:「これっきりモデル」in カローラ・ヒストリー〜その4「謎のスプリンター」〜 2006.11.23 トヨタ・スプリンター1200デラックス/1400ハイデラックス(1970-71)■カローラからの独立1970年5月、カローラが初めて迎えたフルモデルチェンジに際して、68年に初代カローラのクーペ版「カローラ・スプリンター」として登場したスプリンターは、新たに「トヨタ・スプリンター」の名を与えられてカローラ・シリーズから独立。同時にカローラ・シリーズにはボディを共有する「カローラ・クーペ」が誕生した。基本的に同じボディとはいえ、カローラ・セダンとほとんど同じおとなしい顔つきのカローラ・クーペに対して、独自のグリルを持つスプリンターは、よりスポーティで若者向けのムードを放っていた。バリエーションは、「カローラ・クーペ」「スプリンター」ともに高性能版の「1200SL」とおとなしい「1200デラックス」の2グレード。エンジンは初代から受け継いだ直4OHV1166ccで、「SL」にはツインキャブを備えて最高出力77ps/6000rpmを発生する3K-B型を搭載。「デラックス」用のシングルキャブユニットはカローラとスプリンターで若干チューンが異なり、カローラ版は68ps/6000rpm(3K型)だが、スプリンター版は圧縮比が高められており73ps/6600rpm(3K-D型)を発生した。また、前輪ブレーキも双方の「SL」と「スプリンター・デラックス」にはディスクが与えられるのに対して、「カローラ・クーペ・デラックス」ではドラムとなっていた。つまり外観同様、中身も「スプリンター」のほうがよりスポーティな味付けとなっていたのである。しかしながら、どういうわけだか「スプリンター1200デラックス」に限って、そのインパネには当時としても時代遅れで地味な印象の、角形(横長)のスピードメーターが鎮座していたのだ。
-
第52回:「これっきりモデル」in カローラ・ヒストリー〜その3「唯一のハードトップ・レビン」〜 2006.11.15 トヨタ・カローラ・ハードトップ1600レビン(1974-75)■レビンとトレノが別ボディに1974年4月、カローラ/スプリンターはフルモデルチェンジして3代目となった。ボディは2代目よりひとまわり大きくなり、カローラには2/4ドアセダンと2ドアハードトップ、スプリンターには4ドアセダンと2ドアクーペが用意されていた。このうち4ドアセダンは従来どおり、カローラ、スプリンターともに基本的なボディは共通で、グリルやリアエンドなどの意匠を変えて両車の差別化を図っていた。だが「レビン」や「トレノ」を擁する2ドアクーペモデルには、新たに両ブランドで異なるボディが採用されたのである。カローラはセンターピラーのない2ドアハードトップクーペ、スプリンターはピラー付きの2ドアクーペだったのだが、単にピラーの有無ということではなくまったく別のボディであり、インパネなど内装のデザインも異なっていた。しかしシャシーはまったく共通で、「レビン」(型式名TE37)および「トレノ」(同TE47)についていえば、直4DOHC1.6リッターの2T-G/2T-GR(レギュラー仕様)型エンジンはじめパワートレインは先代から踏襲していた。ボディが大型化したこと、および双方とも先代ほど簡素でなくなったこともあって車重はレビン930kg、トレノ925kgと先代より60〜70kg前後重くなった。
-
第51回:「これっきりモデル」in カローラ・ヒストリー〜その2「狼の皮を被った羊(後編)」〜 2006.11.10 トヨタ・カローラ・レビンJ1600/スプリンター・トレノJ1600(1973-74)■違いはエンブレムのみ1972年3月のレビン/トレノのデビューから半年に満たない同年8月、それらを含めたカローラ/スプリンターシリーズはマイナーチェンジを受けた。さらに翌73年4月にも小規模な変更が施されたが、この際にそれまで同シリーズには存在しなかった、最高出力105ps/6000rpm、最大トルク14.0kgm/4200rpmを発生する直4OHV1.6リッターツインキャブの2T-B型エンジンを積んだモデルが3車種追加された。うち2車種は「1600SL」と「1600SR」で、これらはグレード名から想像されるとおり既存の「1400SL」「1400SR」のエンジン拡大版である。残り1車種には「レビンJ1600/トレノJ1600」という名称が付けられていたが、これらは「レビン/トレノ」のボディに、DOHCの2T-Gに代えてOHVの2T-B型エンジンを搭載したモデルだった。なお、「レビンJ1600/トレノJ1600」の「J」は「Junior(ジュニア)」の略ではないか言われているが、公式には明らかにされていない。トランクリッド上の「Levin」または「Trueno」のエンブレムに追加された「J」の文字を除いては、外から眺めた限りでは「レビン/トレノ」とまったく変わらない「レビンJ/トレノJ」。だがカタログを眺めていくと、エンジンとエンブレムのほかにも「レビン/トレノ」との違いが2点見つかった。
-
第50回:「これっきりモデル」in カローラ・ヒストリー〜その1「狼の皮を被った羊(前編)」〜 2006.11.6 誕生40周年を迎えた2006年10月に、10代目に進化したトヨタ・カローラ。それを記念した特別編として、今回は往年のカローラおよびその兄弟車だったスプリンター・シリーズに存在した「これっきりモデル」について紹介しよう。かなりマニアックな、「重箱の隅」的な話題と思われるので、読まれる際は覚悟のほどを……。トヨタ・カローラ・レビンJ1600/スプリンター・トレノJ1600(1973-74)■スパルタンな走りのモデル型式名TE27から、通称「27(ニイナナ)レビン/トレノ」と呼ばれる、初代「カローラ・レビン1600/スプリンター・トレノ1600」。英語で稲妻を意味する「LEVIN」、いっぽう「TRUENO」はスペイン語で雷鳴と、パンチの効いた車名を冠した両車は、2代目カローラ/スプリンター・クーペのコンパクトなボディに、セリカ/カリーナ1600GT用の1.6リッターDOHCエンジンをブチ込み、オーバーフェンダーで武装した硬派のモデルとして、1972年の登場から30余年を経た今なお、愛好家の熱い支持を受けている。「日本の絶版名車」のような企画に必ずといっていいほど登場する「27レビン/トレノ」のベースとなったのは、それらが誕生する以前のカローラ/スプリンターシリーズの最強モデルだった「クーペ1400SR」。SRとは「スポーツ&ラリー」の略で、カローラ/スプリンター・クーペのボディに、ツインキャブを装着して最高出力95ps/6000rpm、最大トルク12.3kgm/4000rpmを発生する直4OHV1407ccエンジンを搭載したスポーティグレードだった。ちなみにカローラ/スプリンター・クーペには、1400SRと同じエンジンを搭載した「1400SL」というモデルも存在していた。「SL」は「スポーツ&ラクシュリー」の略なのだが、このSLに比べるとSRは装備が簡素で、より硬い足まわりを持った、スパルタンな走り重視のモデルだったのである。
-
第49回:『唯一無二』日野コンマース(1960-62)(その4) 2006.9.13 新しいコンセプトのトランスポーターとして、1960年2月に発売された日野コンマース。だがそのセールスははかばかしくなかった。
-
![ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】]() NEW
NEW
ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】
2026.1.19試乗記ベントレーのラグジュアリークーペ「コンチネンタルGT」のなかでも、ウェルビーイングにこだわったという「アズール」に試乗。控えめ(?)な680PSのハイブリッドがかなえる走りは、快適で満ち足りていて、ラグジュアリーカーの本分を感じさせるものだった。 -
![第327回:髪もクルマもナイスファイト!]() NEW
NEW
第327回:髪もクルマもナイスファイト!
2026.1.19カーマニア人間国宝への道清水草一の話題の連載。日産の新型「ルークス」で夜の首都高に出撃した。しっかりしたシャシーとターボエンジンのパワフルな走りに感心していると、前方にスーパーカーの姿を発見。今夜の獲物は「フェラーリ・ローマ」だ! -
![日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!]() NEW
NEW
日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!
2026.1.19デイリーコラムアメリカからの外圧による制度変更で、北米生産モデルの国内導入を決めたトヨタ。同様に、今後日本での販売が期待できる「海外生産の日本車」には、どんなものがあるだろうか? 清水草一が検証してみた。 -
![フェラーリ12チリンドリ(後編)]()
フェラーリ12チリンドリ(後編)
2026.1.18思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「フェラーリ12チリンドリ」に試乗。前編では伝家の宝刀であるV12エンジンを絶賛した山野。後編ではコンビを組むシャシーの印象を余すところなく聞いてみた。 -
![BYDシールAWD(4WD)【試乗記】]()
BYDシールAWD(4WD)【試乗記】
2026.1.17試乗記BYDのBEVサルーン「シール」の機能アップデートモデルが登場。強化のポイント自体はそれほど多くないが、4WDモデルの「シールAWD」は新たに電子制御式の可変ダンパーを装備したというから見逃せない。さまざまなシーンでの乗り心地をチェックした。 -
![新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る]()
新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る
2026.1.16デイリーコラム英国のモーターサイクル史にあまたの逸話を残してきた名門、ノートンが、いよいよ再始動! その数奇な歴史を振り返るとともに、ミラノで発表された4台の次世代モデルを通して、彼らが思い描く未来像に迫った。

















