レジェンドデザイナーだけが知っている! 1960年代の日産自動車秘史
2021.05.12 デイリーコラム初代ローレルのエクステリアデザイナー
初代「日産ローレル(型式名:C30)」が誕生50周年を迎えた2018年、そのワンメイククラブであるクラブC30が、ローレルの生まれ故郷である日産村山工場跡地にある日産ディーラー、東京日産 新車のひろば 村山店で里帰りイベントを実施した。以来、同クラブは初代ローレル ハードトップ誕生50周年、そして日産の901運動にちなんだモデルといったテーマを掲げた小規模イベントを同会場で開催している。
2021年4月18日にはその4回目が開かれた。今回のイベント名は「初代ローレル㊥デザイントーク/プリンスの丘パレード2021」で、初代ローレルのエクステリアデザインを担当した元日産のデザイナーで、現在は北海道旭川市に本拠を置くデザイン事務所「北のデザイン研究所」主宰にして東海大学名誉教授である澁谷邦男さんをゲストとして招聘(しょうへい)。メインイベントはもちろん澁谷さんのトークショーである。
澁谷さんは1963年に日産に入社、初代「プレジデント(150)」や初代ローレルのエクステリアデザインに関わった後、1970年に独立。自らデザイン事務所を立ち上げ実務に携わるいっぽうで大学や専門学校で教鞭(きょうべん)を執るという二刀流を長年にわたって続けてきた方である。
トークショーを実施するにあたって、長年教育に携わってきた方だけに、澁谷さんはすべての資料を自らご用意。参加者にトークのレジュメと、初代ローレルの開発タイムラインを中心とした日産在籍時代の詳細な年表を配布してくださった。これらだけでも非常に貴重な資料なのだが、トークショーの話題は初代ローレルのデザインプロセスのみならず、1960年代の日産のデザイン環境や他車種を含めたデザインワークにまで及んだ。質疑応答を含めてたっぷり1時間半近く展開されたトークのなかから、特に印象的だった話題を紹介させていただこう。
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
若手を積極的に登用
1940年生まれで現在81歳という澁谷さんは、デザインの名門といわれた千葉大学工学部工業意匠科を1963年に卒業。日産に入社して企画室造形課の高級車スタジオに配属された。
当時の日産のデザイン環境はというと、戦前に入社し、戦後は「ダットサン110/210」、初代「ブルーバード(310)」や初代「セドリック(30)」などを手がけたリーダーにして、日本のカーデザイナーのパイオニアだった佐藤章蔵氏が1959年に退社。新たな方向に進むと思われたのもつかの間、1960年代に入るとイタリアのピニンファリーナと契約、主力車種であるブルーバードとセドリックのデザインを依頼してしまった。
それで宙に浮いてしまったのが、社内で進められていた2代目セドリックのデザイン。ボツにするのはもったいないということで、それを拡大して初代プレジデント(150)に生かしたことは比較的知られているが、そのプレジデントの外装部品のデザインが、澁谷さんの初仕事だったという。
「フロントグリルや前後バンパー、ドアハンドル、オーナメント、モール類、ホイールキャップなど外装部品すべてですね。難しかったのは(国産初だった)リモコン式フェンダーミラー。ワイヤを使ったロールス・ロイスの機構を参考にしたのですが、メカ部分がかさばってしまって」
入社して研修が終わった1963年の9月からほぼ1年かけて取り組んだそうだが、いくら大学でデザインを学んだとはいえ、入社したばかりの新人に最高級車の部品を任せるとは、ずいぶん大胆な判断である。主力車種のデザインを外注したいっぽうで、当時の日産には若手にもどんどん仕事をやらせようという空気がみなぎっていたそうだ。
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
プロジェクト名はマルチュー
プレジデントの外装部品デザインを終えた澁谷さんが初代ローレルのエクステリアデザインを担当することになったのは、入社2年目の1965年1月。ちなみに初代ローレルの開発はさかのぼること1年以上、1963年秋から始まっていた。ブルーバードとセドリックの中間クラスということで、プロジェクトの通称は中の文字を丸で囲んだ㊥(マルチュー)、発売は1966年秋と定められていた。
㊥の開発コンセプトはすべての面において優れた、営業車や商用車需要を考えない理想の乗用車。すなわち初代ローレルのキャッチフレーズとなった“ハイオーナーセダン”である。そのために国際ラリーで入賞はしても総合優勝はできない理由のひとつと考えられた、バネ下重量の重い後輪リジッドのサスペンションや反応の鈍いボールナットのステアリングに代えて、前:ストラット、後ろ:セミトレーリングアームの4輪独立懸架やラック&ピニオンのステアリング、そして高速性能に優れたSOHCエンジンを採用することは、当初から決まっていたという。
開発スタートから1年を経た1965年初頭から試作車がテストを開始していたが、「気品」をデザインコンセプトに掲げた㊥のスタイリングはなかなか決まらなかった。先輩デザイナーによって1964年中にランチア風の第1号が、会社からの課題で6ライトウィンドウを採用した第2号のフルサイズクレイモデルが出来上がっていたが、決定には至らず。そして冒頭に記したように、入社2年目の澁谷さんに第3号の命が下ったのだった。
1965年1月に始まった、澁谷さんによる第3号が社長プレゼンを通って決定案となったのは同年4月。デザインスケッチ着手からフルサイズのクレイモデル完成まで、わずか3カ月という超早業だった。
「試作車はテストコースをバンバン走っていて、ボディー設計はデザイン決定を待ちかまえている状況でしたから、それから3カ月後の7月初めまでにすべての線図と部品図を毎日残業して仕上げました。いわゆる突貫工事ですね」
本人もそう語っていたが、今では考えられない、高度経済成長期ならではの話であろう。
 拡大 拡大 |
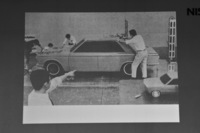 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
忍び寄る合併の足音
澁谷さんによると、㊥こと初代ローレルのエクステリアデザインに関して参考にしたのは、英国フォードの「コルチナ」や独フォードの「タウナス17M」などの欧州製サルーン。性能比較用として日産が購入したのはミケロッティデザインの「BMW 1800」で、ピニンファリーナデザインの「プジョー404」も参考車両として存在したという。
初代ローレルは前:ストラット/後ろ:セミトレーリングアームの4輪独立懸架やヘミヘッドのSOHCエンジンといったメカニズムの近似性から“和製BMW”の異名をとったが、やはり参考にしていたわけだ。またプジョー404は後輪リジッドながら乗り心地がすばらしかったという。
ちなみに彼が所属していた高級車スタジオのスタッフが憧れていたモデルは「ジャガー・マークX(テン)」。当時のジャガーのフラッグシップサルーンだが、高級車といえどもスポーティーでアクティブなモデルをつくりたいと考えていた彼らの理想像だったのだ。
「気品」をデザインコンセプトとした初代ローレルは、きれいな面を作ることに留意し、Aピラーを思い切って後傾させ、フロントドアの三角窓を取り去りスポーティーなフォルムを打ち出した。それは、その時点では日本で初の試みだったのだ。
だが、デザイン案が決定し、澁谷さんが線図と部品図の作成に集中していたころ、裏では2つの大きな事態が進行していた。ひとつは1965年5月に調印された日産とプリンスの合併。もうひとつは主力車種であるブルーバード(410)が、目玉だったはずのピニンファリーナデザインが不評で販売不振だったことから、次期型へのフルモデルチェンジ計画が当初の予定より早められたことだった。この2つの事態によって、㊥こと初代ローレルの開発計画は大幅な変更を余儀なくされるのである。
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
プロジェクト中止は免れたものの……
1966年8月に日産とプリンスは正式に合併した。必然的に車種が増えたことから、すでに試作車も完成していたにもかかわらず、㊥プロジェクトは中止という声も社内でささやかれ始めた。いっぽう国内のみならず海外市場でも主力商品である次期ブルーバードの開発は最優先事項とされた。
そのあおりを食らった㊥こと初代ローレルだが、結論から言えばプロジェクト中止は免れた。ただしプリンスのフラッグシップだった「グロリア」が、将来的に3代目セドリックと双子車になって追浜工場でつくられるようになることを想定して、代わりにラインが空くであろう旧プリンスの村山工場で生産されることになった。それに伴い、エンジンは当初の予定だった日産設計のL型から旧プリンス設計のG型に変更された。
日産とプリンス、設計手法も生産方式もまったく異なる2つのメーカーが、合併したからといって、そう簡単に融通を利かせられるものではない。澁谷さんによれば、ローレルの設計スタッフが村山に寝泊まりして生産準備を進めたが、結果的にそのデビューは当初の予定だった1966年秋から1年半遅れの1968年4月までズレ込むこととなってしまった。
いっぽう510型となる次期型ブルーバード。㊥プロジェクトで開発された4輪独立懸架のシャシーを小型化すればブルーバードにも使えるということで、当初からその方針で進められていた。だが基幹車種とあって船頭が多く、デビュー予定が当初の1967年秋から同年春に早められたにもかかわらず(最終的には同年8月発売)、デザインがなかなか決まらない。そのあげく、先行していた澁谷さんらのチームがデザイン・設計したローレル用の部品図をそっくり510チームに渡すことになったのだった。
「同じ会社なんだからいいじゃないか、と思われるかもしれませんが、ひとつの部品をつくるのには、さまざまな思考とプロセスがあるわけで……仕方ないと納得はしましたけどね」
510ブルーバードとC30ローレルに共通部品や似たような部品が見受けられるのは、こういうわけなのである。
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
廉価版の拡大版という扱いに
澁谷さんをはじめ㊥こと初代ローレルのデザインチームの協力もあって、1967年8月に3代目となるブルーバード(510)がデビューした。日本車で初めて三角窓を廃した、「スーパーソニックライン」と称するシャープなスタイリングのボディーに、前:ストラット、後ろ:セミトレーリングアームの4輪独立懸架にSOHCエンジンといった、量産小型車としては異例に高級かつ進歩的なメカニズムを搭載した、「技術の日産」の面目躍如たるモデルだった。
それから8カ月の1968年4月、当初の予定より1年半遅れて初代ローレル(C30)が発売される。うたい文句は純オーナードライバー向けの“ハイオーナーセダン”で、営業車(タクシー)仕様や商用車(ライトバン)を用意しないのは、当時としては異例だった。しかし、セリングポイントだった三角窓のないスタイリングや4輪独立懸架の採用は、残念ながら弟分のブルーバードに先を越されてしまった。
「メディア、特に男性週刊誌あたりでは、やれ510にそっくりだ、510とここが似ている、あそこが似ているなどと書かれてしまいました。確かに510の後では、新鮮味が感じられなかったのは事実でしょうが」
本来ならC30ローレルを縮小した廉価版が510ブルだったのだが、登場順が逆転したことで、C30が510の拡大版と見られてしまったのだった。
旧プリンス設計のクロスフロー、ヘミヘッドのSOHC 1.8リッターエンジンやラック&ピニオンのステアリングなど、ブルーバードにはないローレルの魅力は、クルマにうるさい層にはアピールしたが、絶対的には少数派である。同年9月にトヨタから、ローレルとは反対にワイドバリエーションをそろえた「コロナ マークII」が登場すると、営業的には主導権を握られてしまった。
後年、“販売の神様”と呼ばれたトヨタ自動車販売の初代社長である神谷正太郎氏が、「もしローレルが当初の予定どおり発売されていたら、(対抗馬のなかった)トヨタはかなりあせったことだろう」と語ったそうだが、実際はそうはならなかったのである。
かように1960年代の日産の社内事情に命運を左右されてしまった初代ローレル。だが1960年代後半から70年代初頭にかけての日産車の魅力であり、その後も日産デザインが混迷する度に何度も復活したクリーンでシャープなスタイリングの元祖は、澁谷さんが手がけた初代ローレルではないかと思うのだ。「気品」をデザインコンセプトとしたモデルだけに、関係者も愛好家も、そのことを声高に主張したりはしないが。
(文=沼田 亨/写真=日産自動車、トヨタ自動車、フォード、BMW、ステランティス、沼田 亨/編集=藤沢 勝)
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |

沼田 亨
1958年、東京生まれ。大学卒業後勤め人になるも10年ほどで辞め、食いっぱぐれていたときに知人の紹介で自動車専門誌に寄稿するようになり、以後ライターを名乗って業界の片隅に寄生。ただし新車関係の仕事はほとんどなく、もっぱら旧車イベントのリポートなどを担当。
-
日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!NEW 2026.1.19 アメリカからの外圧による制度変更で、北米生産モデルの国内導入を決めたトヨタ。同様に、今後日本での販売が期待できる「海外生産の日本車」には、どんなものがあるだろうか? 清水草一が検証してみた。
-
新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る 2026.1.16 英国のモーターサイクル史にあまたの逸話を残してきた名門、ノートンが、いよいよ再始動! その数奇な歴史を振り返るとともに、ミラノで発表された4台の次世代モデルを通して、彼らが思い描く未来像に迫った。
-
市街地でハンズオフ運転が可能な市販車の登場まであと1年 日産の取り組みを再確認する 2026.1.15 日産自動車は2027年に発売する車両に、市街地でハンズフリー走行が行える次世代「ProPILOT(プロパイロット)」を搭載する。その発売まであと1年。革新的な新技術を搭載する市販車の登場は、われわれにどんなメリットをもたらすのか。あらためて考えてみた。
-
30年の取材歴で初めてのケースも 2025年の旧車イベントで出会った激レア車 2026.1.14 基本的に旧車イベントに展示されるのは希少なクルマばかりだが、取材を続けていると時折「これは!」という個体に遭遇する。30年超の取材歴を誇る沼田 亨が、2025年の後半に出会った特別なモデルを紹介する。
-
東京オートサロンでの新しい試み マツダのパーツメーカー見学ツアーに参加して 2026.1.13 マツダが「東京オートサロン2026」でFIJITSUBO、RAYS、Bremboの各ブースをめぐるコラボレーションツアーを開催。カスタムの間口を広める挑戦は、参加者にどう受け止められたのか? カスタムカー/チューニングカーの祭典で見つけた、新しい試みに密着した。
-
![ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】]() NEW
NEW
ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】
2026.1.19試乗記ベントレーのラグジュアリークーペ「コンチネンタルGT」のなかでも、ウェルビーイングにこだわったという「アズール」に試乗。控えめ(?)な680PSのハイブリッドがかなえる走りは、快適で満ち足りていて、ラグジュアリーカーの本分を感じさせるものだった。 -
![第327回:髪もクルマもナイスファイト!]() NEW
NEW
第327回:髪もクルマもナイスファイト!
2026.1.19カーマニア人間国宝への道清水草一の話題の連載。日産の新型「ルークス」で夜の首都高に出撃した。しっかりしたシャシーとターボエンジンのパワフルな走りに感心していると、前方にスーパーカーの姿を発見。今夜の獲物は「フェラーリ・ローマ」だ! -
![日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!]() NEW
NEW
日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!
2026.1.19デイリーコラムアメリカからの外圧による制度変更で、北米生産モデルの国内導入を決めたトヨタ。同様に、今後日本での販売が期待できる「海外生産の日本車」には、どんなものがあるだろうか? 清水草一が検証してみた。 -
![フェラーリ12チリンドリ(後編)]()
フェラーリ12チリンドリ(後編)
2026.1.18思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「フェラーリ12チリンドリ」に試乗。前編では伝家の宝刀であるV12エンジンを絶賛した山野。後編ではコンビを組むシャシーの印象を余すところなく聞いてみた。 -
![BYDシールAWD(4WD)【試乗記】]()
BYDシールAWD(4WD)【試乗記】
2026.1.17試乗記BYDのBEVサルーン「シール」の機能アップデートモデルが登場。強化のポイント自体はそれほど多くないが、4WDモデルの「シールAWD」は新たに電子制御式の可変ダンパーを装備したというから見逃せない。さまざまなシーンでの乗り心地をチェックした。 -
![新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る]()
新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る
2026.1.16デイリーコラム英国のモーターサイクル史にあまたの逸話を残してきた名門、ノートンが、いよいよ再始動! その数奇な歴史を振り返るとともに、ミラノで発表された4台の次世代モデルを通して、彼らが思い描く未来像に迫った。















































