第3回:「死して名を残す」トヨペット・マスター(1955〜56)
2006.09.13 これっきりですカー第3回:「死して名を残す」トヨペット・マスター(1955〜56)

|
1955年に初代クラウンと同時にデビューした「トヨペット・マスター」。自家用のクラウンに対して、営業用のマスターは、イタリア風のシンプルなデザインで、タクシーキャブとして活躍したのだが・・・。
 拡大 拡大
|
 拡大 拡大
|
■自家用と営業用
今回のサンプルである「トヨペット・マスター」は、厳密な意味では「これっきりですカー」とはいえないかもしれない。「マスター」自体はたしかに一代限りだが、そこから派生したモデルは、本家が消滅したのち10年以上も命脈を保ったからだ。だが、このたび非常に貴重な現存車両を発見したため、取り上げることにした次第である。
マスター(型式名RR)が誕生したのは1955年1月。この年月を見てピンとくる人はかなりの国産旧車マニアだろう。トヨタそして国産初の本格的な量産乗用車として、後世に語り継がれる存在である「トヨペット・クラウン(型式名RS)」と同時にデビューしたのだ。クラウンRSとは、昨年その復刻版である「オリジン」が発売されて話題を呼んだ観音開きドアを持つ初代クラウンである。
RRやRSといった型式名の最初の“R”は、排気量1500cc以下という当時の小型車(5ナンバー)規格に合わせて作られた、トヨタの誇る最新鋭エンジンだったR型(直 4OHV1453cc・48ps)を意味する。同じエンジンを搭載していたことから推測されるように、クラウンとマスターは同じ5ナンバー“フルサイズ” のセダンだった。
なぜ同クラスのモデルを同時に2車種発表したかといえば、そこにはいわゆるバッジ・エンジニアリングなどではない、当時ならではの実質的な理由があった。端的にいえば純自家用のクラウンに対して、営業すなわちタクシー用のマスター。いってみればマスターは、クラウン・コンフォートの先祖のような存在だったのだ。
 拡大 拡大
|
 拡大 拡大
|
■“イタリア風”のシンプルなスタイリング
事情をもう少し詳しく説明すると、まず、クラウン出現以前の国産乗用車というのは、みなトラックと同じシャシーフレームにセダンボディを架装したものだった。技術的な問題もさることながら、マイカーなど夢のまた夢、その需要のほとんどがタクシー向けという状況においては、乗用車専用設計など採算からいって不可能だったのである。
そこに華々しく登場したクラウンは、当初から純然たる乗用車として設計されており、数々の新機軸が導入されていた。なかでもダブルウィッシュボーン/コイルの前輪独立懸架、後輪はリジッドだが柔らかい3枚リーフのスプリングを用いたサスペンションは、国産車としては画期的なもので、クラウンに外車に劣らぬ快適な乗り心地をもたらした。
しかし、この「進歩的」な前輪独立懸架の耐久性がタクシーの過酷な使用状況に耐えうるかどうか疑問視されたため、従来どおりタフなトラックシャシーを流用したモデルを併売することにした。いかにもトヨタらしい慎重なやりかただが、それがマスターだったのである。基本的にはトラックシャシーだから、マスターのサスペンションは前後とも5枚リーフで吊ったリジッドで、タイヤもクラウンよりひとまわり大径の16インチだった。しかし、R型エンジンをはじめ、油圧式クラッチ、2、3速にシンクロメッシュを導入したギアボックス、リモートコントロール式のシフトレバー(コラムシフト)、ハイポイドギアを採用したファイナルドライブといった「国際水準を行く」新機構はクラウンと共通だった。
そのシャシーに載るボディは、系列会社である関東自動車工業で設計から架装まで一貫して行われた。クラウンのアメリカン・スタイルに対して、イタリア風と称していた無駄な装飾のないシンプルなスタイリングは、個人的には観音開きクラウンより好ましく思う。
 拡大 拡大
|
 拡大 拡大
|
 拡大 拡大
|
■マスターライン
クラウンより10万円安い89万5000円で発売されたマスターは、タクシーキャブとして着実な実績を残した。が、やがてクラウンの耐久性が営業用としても問題ないことがわかり、また日増しに高まるその評価にタクシー業界からもクラウンを求める声が強くなったため、発売から約2年後の56年12月をもって生産中止された。総生産台数は7403台だった。
前近代的なトラックベースのモデルから純乗用車のクラウンへと移行する期間において、いわばワンポイント・リリーフのような役割を果たしたマスター。だが、じつはそこから派生した車種が、母体を上回る成功を収めたのだ。55年12月に登場した「マスターライン」がそれである。マスターのシャシーに、ライトバン、シングルピックアップ、またはダブルピックアップという3種のボディを架装した4ナンバーの商用車であるマスターラインは、乗用車ムードの「貨客兼用車」としてヒット作となったのだ。
初代マスターラインは59年2月に生産が打ち切られ、翌3月には観音開きクラウン・ベースの新型が登場したが、その新シリーズも好評だった「マスターライン」の名を引き継いだ。62年10月にクラウンがフルチェンジを迎えてもその名は残され、結局、マスターラインの名が消えたのは、クラウンが3代目に進化した67年9月のことだった。マスターは死しても、その名を10余年にわたって残したのである。
なお、今回取材したマスターは、都内にある某ディーラーのサービス工場の片隅に「わけあり」で置かれていたもので、フロントグリルのデザインがデビュー当初とは微妙に異なる56年型である。現在は不動の状態だが、見たところ欠品もほとんどなく、コンディションはこの種のクルマとしてはかなりいい。聞くところによれば10年ほど前まで走っていた車両らしく、その気になれば復活はそう難しくなさそうだ。
前述したように総生産台数は7403台、しかもそもそもがタクシーキャブだから、残存数はごく少ないはず。ちなみに私自身は、トヨタ博物館と石川県小松市にある日本自動車博物館所蔵のもの、そしてさるコレクター氏が所有しているものの3台しか現存車を知らない。つまりこの個体は、きわめて貴重なサバイバーなのである。
(文=田沼 哲/2001年5月2日)
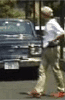
田沼 哲
NAVI(エンスー新聞)でもお馴染みの自動車風俗ライター(エッチな風俗ではない)。 クルマのみならず、昭和30~40年代の映画、音楽にも詳しい。
-
第53回:「これっきりモデル」in カローラ・ヒストリー〜その4「謎のスプリンター」〜 2006.11.23 トヨタ・スプリンター1200デラックス/1400ハイデラックス(1970-71)■カローラからの独立1970年5月、カローラが初めて迎えたフルモデルチェンジに際して、68年に初代カローラのクーペ版「カローラ・スプリンター」として登場したスプリンターは、新たに「トヨタ・スプリンター」の名を与えられてカローラ・シリーズから独立。同時にカローラ・シリーズにはボディを共有する「カローラ・クーペ」が誕生した。基本的に同じボディとはいえ、カローラ・セダンとほとんど同じおとなしい顔つきのカローラ・クーペに対して、独自のグリルを持つスプリンターは、よりスポーティで若者向けのムードを放っていた。バリエーションは、「カローラ・クーペ」「スプリンター」ともに高性能版の「1200SL」とおとなしい「1200デラックス」の2グレード。エンジンは初代から受け継いだ直4OHV1166ccで、「SL」にはツインキャブを備えて最高出力77ps/6000rpmを発生する3K-B型を搭載。「デラックス」用のシングルキャブユニットはカローラとスプリンターで若干チューンが異なり、カローラ版は68ps/6000rpm(3K型)だが、スプリンター版は圧縮比が高められており73ps/6600rpm(3K-D型)を発生した。また、前輪ブレーキも双方の「SL」と「スプリンター・デラックス」にはディスクが与えられるのに対して、「カローラ・クーペ・デラックス」ではドラムとなっていた。つまり外観同様、中身も「スプリンター」のほうがよりスポーティな味付けとなっていたのである。しかしながら、どういうわけだか「スプリンター1200デラックス」に限って、そのインパネには当時としても時代遅れで地味な印象の、角形(横長)のスピードメーターが鎮座していたのだ。
-
第52回:「これっきりモデル」in カローラ・ヒストリー〜その3「唯一のハードトップ・レビン」〜 2006.11.15 トヨタ・カローラ・ハードトップ1600レビン(1974-75)■レビンとトレノが別ボディに1974年4月、カローラ/スプリンターはフルモデルチェンジして3代目となった。ボディは2代目よりひとまわり大きくなり、カローラには2/4ドアセダンと2ドアハードトップ、スプリンターには4ドアセダンと2ドアクーペが用意されていた。このうち4ドアセダンは従来どおり、カローラ、スプリンターともに基本的なボディは共通で、グリルやリアエンドなどの意匠を変えて両車の差別化を図っていた。だが「レビン」や「トレノ」を擁する2ドアクーペモデルには、新たに両ブランドで異なるボディが採用されたのである。カローラはセンターピラーのない2ドアハードトップクーペ、スプリンターはピラー付きの2ドアクーペだったのだが、単にピラーの有無ということではなくまったく別のボディであり、インパネなど内装のデザインも異なっていた。しかしシャシーはまったく共通で、「レビン」(型式名TE37)および「トレノ」(同TE47)についていえば、直4DOHC1.6リッターの2T-G/2T-GR(レギュラー仕様)型エンジンはじめパワートレインは先代から踏襲していた。ボディが大型化したこと、および双方とも先代ほど簡素でなくなったこともあって車重はレビン930kg、トレノ925kgと先代より60〜70kg前後重くなった。
-
第51回:「これっきりモデル」in カローラ・ヒストリー〜その2「狼の皮を被った羊(後編)」〜 2006.11.10 トヨタ・カローラ・レビンJ1600/スプリンター・トレノJ1600(1973-74)■違いはエンブレムのみ1972年3月のレビン/トレノのデビューから半年に満たない同年8月、それらを含めたカローラ/スプリンターシリーズはマイナーチェンジを受けた。さらに翌73年4月にも小規模な変更が施されたが、この際にそれまで同シリーズには存在しなかった、最高出力105ps/6000rpm、最大トルク14.0kgm/4200rpmを発生する直4OHV1.6リッターツインキャブの2T-B型エンジンを積んだモデルが3車種追加された。うち2車種は「1600SL」と「1600SR」で、これらはグレード名から想像されるとおり既存の「1400SL」「1400SR」のエンジン拡大版である。残り1車種には「レビンJ1600/トレノJ1600」という名称が付けられていたが、これらは「レビン/トレノ」のボディに、DOHCの2T-Gに代えてOHVの2T-B型エンジンを搭載したモデルだった。なお、「レビンJ1600/トレノJ1600」の「J」は「Junior(ジュニア)」の略ではないか言われているが、公式には明らかにされていない。トランクリッド上の「Levin」または「Trueno」のエンブレムに追加された「J」の文字を除いては、外から眺めた限りでは「レビン/トレノ」とまったく変わらない「レビンJ/トレノJ」。だがカタログを眺めていくと、エンジンとエンブレムのほかにも「レビン/トレノ」との違いが2点見つかった。
-
第50回:「これっきりモデル」in カローラ・ヒストリー〜その1「狼の皮を被った羊(前編)」〜 2006.11.6 誕生40周年を迎えた2006年10月に、10代目に進化したトヨタ・カローラ。それを記念した特別編として、今回は往年のカローラおよびその兄弟車だったスプリンター・シリーズに存在した「これっきりモデル」について紹介しよう。かなりマニアックな、「重箱の隅」的な話題と思われるので、読まれる際は覚悟のほどを……。トヨタ・カローラ・レビンJ1600/スプリンター・トレノJ1600(1973-74)■スパルタンな走りのモデル型式名TE27から、通称「27(ニイナナ)レビン/トレノ」と呼ばれる、初代「カローラ・レビン1600/スプリンター・トレノ1600」。英語で稲妻を意味する「LEVIN」、いっぽう「TRUENO」はスペイン語で雷鳴と、パンチの効いた車名を冠した両車は、2代目カローラ/スプリンター・クーペのコンパクトなボディに、セリカ/カリーナ1600GT用の1.6リッターDOHCエンジンをブチ込み、オーバーフェンダーで武装した硬派のモデルとして、1972年の登場から30余年を経た今なお、愛好家の熱い支持を受けている。「日本の絶版名車」のような企画に必ずといっていいほど登場する「27レビン/トレノ」のベースとなったのは、それらが誕生する以前のカローラ/スプリンターシリーズの最強モデルだった「クーペ1400SR」。SRとは「スポーツ&ラリー」の略で、カローラ/スプリンター・クーペのボディに、ツインキャブを装着して最高出力95ps/6000rpm、最大トルク12.3kgm/4000rpmを発生する直4OHV1407ccエンジンを搭載したスポーティグレードだった。ちなみにカローラ/スプリンター・クーペには、1400SRと同じエンジンを搭載した「1400SL」というモデルも存在していた。「SL」は「スポーツ&ラクシュリー」の略なのだが、このSLに比べるとSRは装備が簡素で、より硬い足まわりを持った、スパルタンな走り重視のモデルだったのである。
-
第49回:『唯一無二』日野コンマース(1960-62)(その4) 2006.9.13 新しいコンセプトのトランスポーターとして、1960年2月に発売された日野コンマース。だがそのセールスははかばかしくなかった。
-
![右も左もスライドドアばかり ヒンジドアの軽自動車ならではのメリットはあるのか?]() NEW
NEW
右も左もスライドドアばかり ヒンジドアの軽自動車ならではのメリットはあるのか?
2026.2.25デイリーコラム軽自動車の売れ筋が「ホンダN-BOX」のようなスーパーハイトワゴンであるのはご承知のとおりだが、かつての主流だった「スズキ・ワゴンR」のような車型に復権の余地はないか。ヒンジドアのメリットなど、(やや強引ながら)優れている点を探ってみた。 -
![第950回:小林彰太郎氏の霊言アゲイン あの世から業界を憂う]() NEW
NEW
第950回:小林彰太郎氏の霊言アゲイン あの世から業界を憂う
2026.2.25マッキナ あらモーダ!かつて『SUPER CG』の編集者だった大矢アキオが、『CAR GRAPHIC』初代編集長である小林彰太郎との交霊に挑戦! 日本の自動車ジャーナリズムの草分けでもある天国の上司に、昨今の日本の、世界の自動車業界事情を報告する。 -
![ルノー・グランカングー クルール(FF/7AT)【試乗記】]() NEW
NEW
ルノー・グランカングー クルール(FF/7AT)【試乗記】
2026.2.25試乗記「ルノー・グランカングー」がついに日本上陸。長さ5m近くに達するロングボディーには3列目シートが追加され、7人乗車が可能に。さらに2・3列目のシートは1脚ずつ取り外しができるなど、極めて使いでのあるMPVだ。ドライブとシートアレンジをじっくり楽しんでみた。 -
![第862回:北極圏の氷上コースでマクラーレンの走りを堪能 「Pure McLaren Arctic Experience」に参加して]() NEW
NEW
第862回:北極圏の氷上コースでマクラーレンの走りを堪能 「Pure McLaren Arctic Experience」に参加して
2026.2.25エディターから一言マクラーレンがフィンランド北部で「Pure McLaren Arctic Experience」を開催。ほかでは得られない、北極圏のドライビングエクスペリエンスならではの特別な体験とは? 氷上の広大な特設コースで、スーパースポーツ「アルトゥーラ」の秘めた実力に触れた。 -
![ボルボEX30クロスカントリー ウルトラ ツインモーター パフォーマンス(4WD)【試乗記】]()
ボルボEX30クロスカントリー ウルトラ ツインモーター パフォーマンス(4WD)【試乗記】
2026.2.24試乗記ボルボの電気自動車「EX30クロスカントリー」に冬の新潟・妙高高原で試乗。アウトドアテイストが盛り込まれたエクステリアデザインとツインモーターからなる四輪駆動パワートレイン、そして引き上げられた車高が織りなす走りを報告する。 -
![エンジニアが「車検・点検時に注意すべき」と思う点は?]()
エンジニアが「車検・点検時に注意すべき」と思う点は?
2026.2.24あの多田哲哉のクルマQ&Aすっかりディーラー任せにしている車検・点検について、ユーザーが自ら意識し、注視しておくべきチェックポイントはあるだろうか? 長年トヨタで車両開発を取りまとめてきた多田哲哉さんに意見を聞いた。
















