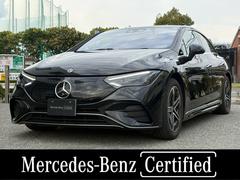メルセデス・ベンツEQE350+(RWD)
移り行く時代 2023.02.06 試乗記 電気自動車(BEV)にも「A」から「S」までのラインナップを整備しつつあるメルセデス。「EQE」はその名のとおり「Eクラス」相当の位置づけだ。姿かたちと成り立ちは「EQS」とよく似ているが、運転感覚や装備内容はだいぶ違う。ロングドライブに連れ出した印象をリポートする。BEV専用シャシーを採用
2030年までにメルセデス・ベンツはBEV販売100%のブランドになる。
コロナ禍の最中となる2021年に、ダイムラーが示したビジネスプランは世界に衝撃をもって伝えられた。ただし、そこには仕向け地に意向があれば応える……などとマーケットイン的な文言も加えられていて、未来を見極め完全に退路を断ったプランというわけではないこともうかがえる。
が、表向きでは2019年の「EQC」に始まり、BEV化されたプロダクトが続々とメルセデスのラインナップには組み込まれている。それでも既存車の居抜きが大半だったところにきて、2022年からはいよいよBEV専用設計を用いたモデルが矢継ぎ早に4タイプ発表された。その1つがこのEQEだ。
EQEのプラットフォームは型式名称「EVA2」と呼ばれるもの。バッテリーユニットとソリッドに結合されたフロアパンに4輪を配する、その姿をスケートボードになぞらえられる、BEVではおなじみのアーキテクチャーだ。
ちなみにEVA2はEQEのほかに「EQS」「EQS SUV」「EQE SUV」の3モデルが採用。うち、EQSとEQS SUVはホイールベースも共通化されているが、EQE SUVのホイールベースはEQEより90mm短い。そしてEQEのホイールベースもEQSより90mm短く設定されている。
そのホイールベースとも相関関係となるバッテリー容量は90.6kWh。EQSが12モジュールで107.8kWhだから、10モジュールを搭載するということだろう。WLTCモードでの一充電走行距離はEQSの700kmに対して624kmと、1割余り短くなっている。
Eセグメントの存在理由
EQEの日本計測値でのボディーサイズは全長×全幅×全高=4955×1905×1495mm。EQSに対して270mm短く、20mm狭く、25mm低い。が、並んでみると、横から見ない限りはその差はほとんどないようにも感じられる。日本にいると、果たしてこのつくり分けは必要だったのだろうかと「?」が浮かびそうだが、そこは欧州のフリートニーズの事情をくんでのことだろう。EQSがトップである以上、役員職に与えられるクルマがそれということはない。ドイツが牛耳るEセグメントの存在理由の少なからずが、そんな事情だ。
四隅のキワにタイヤを置いてオーバーハングを極端に詰めるなど、BEVならではのプロポーションを実現。弓を一筆書きで描いたような「ワンボウフォルム」もまた、EQSと見まがうようだ。ただしこちらはリアにハッチゲートでなくトランクスペースを持つ純粋な3ボックスとなる。Cd値は0.22と、全長も利するEQSの0.20には及ばずとも十分に低く、中高速域での巡航電費に奏功していることは間違いない。
パッケージ面では、車体の全面が絞り込まれることもあり、荷室容量は430リッターと「Cクラス」より小さい。ロングホイールベースを生かして後席のレッグスペースはしっかり確保されるが、室内高や頭上区間に「Eクラス」のようなゆとりは感じられない。EQSもしかりだが、後席のくつろぎ感としては「CLS」的な4ドアクーペの側にほど近いといったところだろうか。
最小回転半径は4.9m
内装はデザイン面でEQSとの共通性が高い。一方で造形や素材、工法などでは絶妙に差別化が図られている。まぁ、このあたりのつくり分けはお手の物だろう。インフォテインメント系は標準仕様が12.8インチのOLEDタッチスクリーンを中央に備えた昨今のメルセデスではおなじみの構成だ。全幅141cmのガラスパネル内に一体で3つの画面を収めるハイパースクリーンはAMGモデルの「53」のみ、オプションで選択が可能となっている。眼前で感じる目新しさという点では優位な装備だが、助手席でのコンテンツ再生等の独自機能を要さないのであれば標準仕様でも不満を抱くことはないのも確かだ。
今回の試乗車である「350+」は、永久磁石同期モーター「EM0027」をリアアクスル側に搭載している。「EQS450+」と同じ型式名称だが、最高出力は292PS(215kW)と1割強小さい。一方で最大トルクは565N・mとほとんど変わらない。0-100km/h加速が6.4秒、最高速が210km/hといえば、Eクラスになぞらえれば「300」にほど近い動力性能ということになるだろうか。
EQSの450+ではアプリ経由での有償アップデートとなる逆相最大10度のリアアクスルステアがEQE350+は標準装備ということで、最小回転半径はBセグメント並みの4.9mに抑えられる。この小回り性能と「アクティブパーキングアシスト」の合わせ技は強烈で、狭所での駐車もまったく苦にならない。作動の手数やスムーズさはトヨタの「アドバンストパーク」と同等で、自ら駐車する術を忘れてしまいそうなくらいに便利だ。
このリアアクスルステアが中高速域ではスタビリティーや旋回安定性にも大きく寄与していることは、ジャンクションやランプでの合流といった有料道路の走行時にも実感できるだろう。ともにライントレース性は抜群だが、EQSに比べるとその挙動に無理がない。同じ後輪駆動であるEQS450+との重量差は170kgだが、物理的な優位性がそれ以上に感じられる。リアアクスルステアに加えて足まわりそのものの設定も自然にまとまっていて、姿勢変化をある程度は許容しているところがそういった印象の一因なのだろう。
デジタルとアナログの境目
EQEは動力性能面でもナチュラルさが光る。アクセルを意図的に深く踏み込まない限りは、操作に対する応答は至って穏やかだ。滑らかさは言うに及ばずで、このパワートレイン、そしてしつけがもたらす上質感はやはり内燃機とは一線を画する。
パワートレインや空力ボディーによる高速巡航域での静粛性が際立つ一方で、どうしても目立ってくるのが風切り音だ。大きなドアミラーが音源なのは明らかだが、これほどデジタライズにご執心なメルセデスではあるが、ミラーのカメラ化には慎重なように映る。
この点、2022年にEQS SUVの試乗機会に本国のエンジニアに問うてみたら、従来の鏡型のほうが距離感を認識しやすいという話だった。思えばメルセデスは「アクティブノイズキャンセリング」にも消極的で、マイバッハのように明らかなショーファードリブンカーにしかそれを用いていなかったように記憶している。彼らが攻め立てるデジタル的領域と守るべきアナログ的領域との境目は、人間の生理的感覚に委ねられているのだろうか。そんなことを考えながら乗るEQEに、時代が動くその端境の面白さをちょっと重ねてしまった。
(文=渡辺敏史/写真=向後一宏/編集=藤沢 勝)
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
テスト車のデータ
メルセデス・ベンツEQE350+
ボディーサイズ:全長×全幅×全高=4970×1905×1495mm
ホイールベース:3120mm
車重:2390kg
駆動方式:RWD
モーター:交流同期電動機
最高出力:292PS(215kW)/3559-1万5913rpm
最大トルク:565N・m(57.6kgf・m)/0-3559rpm
タイヤ:(前)255/45R19 104Y/(後)255/45R19 104Y(ブリヂストン・トランザT005)
一充電走行距離:624km(WLTCモード)
交流電力量消費率:176kWh/km(WLTCモード)
価格:1248万円/テスト車=1375万円
オプション装備:AMGラインパッケージ(39万8000円)/エクスクルーシブパッケージ(50万2000円)/パノラミックスライディングルーフ(25万5000円)/エナジャイジングパッケージ(11万5000円)
テスト車の年式:2022年型
テスト開始時の走行距離:224km
テスト形態:ロードインプレッション
走行状態:市街地(2)/高速道路(7)/山岳路(1)
テスト距離:538.2km
消費電力量:--kWh
参考電力消費率:4.0km/kWh

渡辺 敏史
自動車評論家。中古車に新車、国産車に輸入車、チューニングカーから未来の乗り物まで、どんなボールも打ち返す縦横無尽の自動車ライター。二輪・四輪誌の編集に携わった後でフリーランスとして独立。海外の取材にも積極的で、今日も空港カレーに舌鼓を打ちつつ、世界中を飛び回る。
-
BYDシールAWD(4WD)【試乗記】 2026.1.17 BYDのBEVサルーン「シール」の機能アップデートモデルが登場。強化のポイント自体はそれほど多くないが、4WDモデルの「シールAWD」は新たに電子制御式の可変ダンパーを装備したというから見逃せない。さまざまなシーンでの乗り心地をチェックした。
-
マツダCX-60 XDドライブエディション ナッパレザーパッケージ(4WD/8AT)【試乗記】 2026.1.14 「マツダCX-60」に新グレードの「XDドライブエディション ナッパレザーパッケージ」が登場。スポーティーさと力強さ、上質さを追求したというその中身を精査するとともに、国内デビューから3年を経た“ラージ商品群第1弾”の成熟度をチェックした。
-
カワサキKLX230シェルパS(6MT)【レビュー】 2026.1.13 その出来には“セロー乗り”も太鼓判!? カワサキのトレイルバイク「KLX230シェルパ」に、ローダウン仕様の「シェルパS」が登場。安心の足つき性で間口を広げた一台だが、実際に走らせてみると、ストリートでも楽しめるオールラウンダーに仕上がっていた。
-
メルセデス・ベンツC220dラグジュアリー(FR/9AT)【試乗記】 2026.1.12 輸入車における定番の人気モデル「メルセデス・ベンツCクラス」。モデルライフ中にも年次改良で進化し続けるこのクルマの、現在の実力はいかほどか? ディーゼルエンジンと充実装備が魅力のグレード「C220dラグジュアリー」で確かめた。
-
日産ルークス ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション(FF/CVT)【試乗記】 2026.1.10 日産の軽スーパーハイトワゴン「ルークス」がフルモデルチェンジ。「見えない危険が……」のテレビCMでお茶の間をにぎわせているが、走る、曲がる、止まるをはじめとしたクルマ全体としての仕上がりはどうか。最上級グレードをテストした。
-
![クルマの乗り味の“味”って何だ?]() NEW
NEW
クルマの乗り味の“味”って何だ?
2026.1.20あの多田哲哉のクルマQ&A「乗り味」という言葉があるように、クルマの運転感覚は“味”で表現されることがある。では、車両開発者はその味をどう解釈して、どんなプロセスで理想を実現しているのか? 元トヨタのエンジニア、多田哲哉さんに聞いた。 -
![プジョー208 GTハイブリッド(FF/6AT)【試乗記】]() NEW
NEW
プジョー208 GTハイブリッド(FF/6AT)【試乗記】
2026.1.20試乗記「プジョー208」にマイルドハイブリッド車の「GTハイブリッド」が登場。仕組みとしては先に上陸を果たしたステランティス グループの各車と同じだが、小さなボディーに合わせてパワーが絞られているのが興味深いところだ。果たしてその乗り味は? -
![ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】]()
ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】
2026.1.19試乗記ベントレーのラグジュアリークーペ「コンチネンタルGT」のなかでも、ウェルビーイングにこだわったという「アズール」に試乗。控えめ(?)な680PSのハイブリッドがかなえる走りは、快適で満ち足りていて、ラグジュアリーカーの本分を感じさせるものだった。 -
![第327回:髪もクルマもナイスファイト!]()
第327回:髪もクルマもナイスファイト!
2026.1.19カーマニア人間国宝への道清水草一の話題の連載。日産の新型「ルークス」で夜の首都高に出撃した。しっかりしたシャシーとターボエンジンのパワフルな走りに感心していると、前方にスーパーカーの姿を発見。今夜の獲物は「フェラーリ・ローマ」だ! -
![日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!]()
日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!
2026.1.19デイリーコラムアメリカからの外圧による制度変更で、北米生産モデルの国内導入を決めたトヨタ。同様に、今後日本での販売が期待できる「海外生産の日本車」には、どんなものがあるだろうか? 清水草一が検証してみた。 -
![フェラーリ12チリンドリ(後編)]()
フェラーリ12チリンドリ(後編)
2026.1.18思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「フェラーリ12チリンドリ」に試乗。前編では伝家の宝刀であるV12エンジンを絶賛した山野。後編ではコンビを組むシャシーの印象を余すところなく聞いてみた。