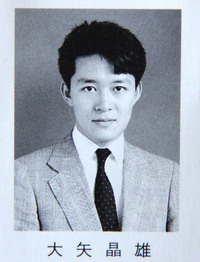第603回:駆けぬけた歓び!?
イタリア在住・大矢アキオが振り返る「平成」
2019.05.10
マッキナ あらモーダ!
伊仏メディアがとらえた「令和」
「令和」時代が始まった。筆者個人としては、選考の過程で別候補にあった「万保」のほうが楽しそうでよかった。読み方は「マンボ」にしたい。だからひそかに今年は「マンボ元年」であると思っている。
そのようなたわごとはともかく、2019年5月1日、イタリアやフランスのメディアでも、日本の元号が令和に変わったことが伝えられた。
イタリアの主要紙『コリエッレ・デッラ・セーラ電子版』は、国際欄での扱いだった。スペイン総選挙で社会労働党が第一党になったニュースの次に扱っていた。タイトルは「誰も見ることができない三種の神器」である。経済紙『イル・ソーレ24オーレ電子版』は、トップページの一角に動画付きでの扱いだった。こちらは「自分は平成生まれだから、どこか寂しい」といった日本の少年の声などを伝えていた。
同日の『フランス24』は、新天皇に関して「人気のある父、明仁(上皇)のように」日本の20世紀初頭の軍国主義を軽視することなく、「第2次世界大戦を正しく認識することを大切にしている」といった分析をしていた。ちなみにフランスのクラシック音楽専門FM局ラジオ・クラシックのプレゼンターは、トピックとして紹介したあと、「サヨナラ」と言って同席の出演者と盛り上がっていた。ひとときの日本ブームである。
筆者の記憶の範囲でイタリア人やフランス人が歴史の節目として盛り上がったものといえば「西暦2000年」と、21世紀の始まりである翌「2001年」である。いずれも祝いのムードの傍らで、終末思想のようなものも流布したものだ。それからすると平成から令和へのチェンジは、外国のものとはいえ、好意的にとらえられている。
筆者は、昔話をするにはまだ早すぎる。それにイタリアに住んでいると、日ごろ元号を意識することはまったくない。それでも、こちらのメディアでこれだけ取り上げられると、やはり意識せざるを得ない。そこで今回は、筆者個人の「平成のはじめ」を振り返ってみることにした。
「だめだこりゃ」と思ったけれど
平成元年(1989年)は、筆者が音楽大学を卒業し、当時東京・神田神保町にあった出版社、二玄社に就職した年であった。つまり社会人1年生だ。
入社試験は前年の1988年9月だった。当時、二玄社が刊行していた『NAVI』と『カーグラフィック(CG)』双方の誌面で「編集部員募集」の告知を発見。書類選考の作文課題を出した。“併願”である。すると双方から筆記試験の通知が来た。
グーグルマップなどない時代である。試験会場である神楽坂の出版クラブ会館は、初めて訪れる者には極めてわかりにくい場所だった。追い打ちをかけるように雨も降りだした。筆者は、試験を受けずに帰ろうと思った。しかし、最後の瞬間に会館を見つけ、ずぶぬれになりながら建物に駆け込んだ。階段を飛んで上がり、試験会場に入った途端に扉が閉められた。
見ると、広い会議場を無数の受験者たちが埋め尽くしていた。自動車誌の編集記者志望者は、世の中にこんなにいたのか。その様子を見てとっさに、いかりや長介の名句「だめだこりゃ」が浮かんだ。
最初はNAVIの試験だ。机の上を見ると、NAVIの縦書き原稿用紙が置いてある。どうせ受かるはずはない。記念にこれだけ持って帰ろう。そう考えて試験に臨んだ。
休憩時間、他の受験生は仲間と「1224万台、1224万台」とぶつぶつ言いながら暗記を試みている。前年(1987年)の日本国内自動車生産台数らしい。そのようなことも出題されるかもしれないんだ、と感心しながらはたで聞いていた。参考までに、2018年は約972万台であるから、当時の日本の自動車産業の勢いがわかる。
後半のCGの試験は、英文和訳・和文英訳や時事問題があったように記憶している。なかなか手ごわい。しかしよく見ると、自動車史に関する出題があった。これで挽回するしかない。
ピエール・ブーランジェに関する設問があった。愛読書だった大川 悠著・二玄社刊「世界の自動車 8 シトローエン」の内容を思い出し、ブーランジェが第2次大戦前にミシュランから派遣されてきたシトロエンの社長であること。シルクハットをかぶって乗車できる室内高を開発陣に要求し、“ブーランジェのハットテスト”と呼ばれるようになったこと。そして卵が割れない乗り心地を求めたこと。その結果誕生したのが1948年のパリサロンで発表された「2CV」であったことなどを、原稿用紙からあふれんばかりに書き連ねたのを覚えている。
その不気味なほどの書きっぷりが目にとまったのだろう。後日同じく出版クラブ会館に、今度は面接のため呼ばれた。CGのほうで生き残ったらしい。行ってみると、普段は誌面でしかお目にかかれないCG誌の長期テスト車がずらりと並んでいた。それらが見られただけでいいや、という気持ちで面接会場に向かった。部屋に入ると、当時CG編集長だった小林彰太郎氏と同副編集長だった高島鎮雄氏、そしてCG2代目編集長となる熊倉重春氏らが並んでいた。
さらに後日、今度は神田三崎町にあった編集部のビルに呼ばれ、再び面接を受けると、採用通知が届いた。
都内のとある女子高の音楽講師へと教授推薦を受けていた筆者だが、それを断って編集記者になることにした。
平成サラリーマンからイタリアへ
配属先は二玄社が新たに刊行することになった季刊誌『SUPER CG』編集部であった。
入社日の社長あいさつのときに、NAVI編集部にはどんな新人が合格したのかと思って見てみれば、長髪で筆者よりも数倍都会的な青年だった。誰あろう、今日自動車ジャーナリストとして多方面で筆を奮っている森 慶太氏である。
SUPER CG編集部は『カーグラフィックTV』と同じ部屋だった。僕の真向かいの席は、番組で今日までプレゼンターを務めている田辺憲一氏だった。これまでテレビで見ていた人が毎日目の前にいるというのは、不思議な気がしたものだった。
筆者の上司であり、SUPER CGの編集長となった高島鎮雄氏は、日本でトップクラスの自動車史家であるだけでなく、世界史や美術、音楽などあらゆる文化に精通していた。したがって、筆者にとっては会社に行くというより、大学の講義に出席するような感があった。本来なら新人は即戦力とならねばならないところ、なかなか会社の役に立たない筆者を気長に育ててくれた高島氏には今も頭が下がる。
しかし平成4年、母が突然病死し、その結果実家の家業も畳むという、人生にとって不測の事態に見舞われた。
ここで人生をリセットする必要があると筆者は考えた。思えば、米軍基地のそばで育った筆者は、子供時代から外国生活が夢だった。このまま勤めると10年、そして20年と頑張ってしまいそうな気がした。そこで入社8年目の平成8年(1996年)、「八」は末広がりということで二玄社を後にした。そして6日後に結婚し、その3日後にシエナの外国人大学で学ぶべく、イタリアへと旅立った。
それから2年。いざ仕事を始めようと思っても、そう簡単には見つからなかった。それでも、イタリアをベースにしたかった筆者は、現地の料理学校の広報兼通訳の仕事を女房とすることにし、イタリア人経営者とのコラボレーションを始めた。
自動車とは直接つながりがなかったものの、そのときに数々のイタリア人と接した経験は、のちの執筆活動において貴重なものとなった。
やがて、イタリア生活の思い出のつもりでつづった手記を東京時代の知人が出版社に持ち込んでくれた。それが平成12年(2000年)に本となり、少しずつ著述の仕事ができるようになっていった。こうして今日まで続くイタリア生活が始まった。
すでに述べたように、国外に住む筆者にとって元号は、日常で特に用いるシーンがない。しかし、平成という区切りを自分の歩みに当てはめて振り返ったとき、昭和以上に刺激に満ちた時代だったといえる。
目指すは「免許返上」?
昨今、筆者自身は「『iPhone100』が発売されるまで生きてやる」と決意し、食生活を含む生活習慣に対して従来以上に気をつかっている。まあ、その頃には、通信機器はもっとウエアラブルになり、スマートフォンというデバイス自体が消滅しているに違いないが。
スマートフォンよりも先に考えなくてはいけないのは、「クルマ」だ。自動車の進化は、すでにロードマップが見えてしまった。自動運転レベル5がゴールだとすると、少なくとも筆者個人には、それ以前のクルマは過渡期にしか見えなくなってくるのだ。もちろん、美術史や音楽史を見ればわかるように、過渡期にも文化は生まれ得る。だが、筆者個人には、時間的にもおカネ的にもそれを楽しむ余裕はない。
ライドシェアも、これからさらに加速してゆくだろう。だから個人的には「運転免許を早く返上してもよい」と考えている。
幸い、高齢者講習の対象年齢となるまでには、乳児が思春期になるくらいの年数がまだある。だが、山田洋次監督の映画『家族はつらいよ』で橋爪 功演ずる高齢者のように、ぶつけて傷だらけの「トヨタ・マークII」を乗り続けるような格好悪いおやじになりたくないのだ。それにドヤ顔で高級車に乗るより、京王井の頭線に乗っていてもサマになるおじさまになったほうがいい。音楽と美術と、高級でなくてもいいからうまい料理、そして美しい女性をめでることができれば、人生それでいいのである。
何も恐れることなく駆けぬけた平成を考えれば、免許を返上することくらい怖くないはずだ……と勇ましいことをつづったが、イタリアの現実も直視しなければならない。
筆者が住む地方都市シエナにおいて、公共交通機関は、「平成」の間にまったく改善がみられなかった。わが家から旧市街へのバスは夜8時30分過ぎが最終である。郊外のキャンティ地方行きバスは、日に数本しかない。ライドシェアも始まっていない。そうした地域で暮らす限り、運転免許や自動車がないと不便であり、取材もまともにできない。
自動車に感謝!
そもそも自動車が嫌いになったわけではない。いや、クルマには感謝している。クルマがなければ、今の筆者はいなかったであろう。なぜなら、自動車に興味を抱いていたからこそ出版社で優秀な人々と出会えた。ヨーロッパの産業史を学ぶうえで、格好の糸口にもなった。そもそも学生時代に関わりがなかったイタリア語やフランス語を学んだのも自動車への関心が原点であり、数々の取材で実践できたからだった。
イタリアに住んでからも、自動車をなかだちとした人々との交流が、文化を知るきっかけになった。筆者の3冊目の本で平成14年(2002年)に刊行した『イタリア式クルマ生活術』は、中古で買った12年落ち「ランチア・デルタ」を取り巻くイタリア人とのふれあいを描いたものだった。
平成から令和という時代の区切りを、自らの心の仕切りとするなら?
これからはやみくもに新車を追うことはしない。それよりも自動車という人類が生んだ素晴らしいツールの歴史やデザイン、そしてそれに携わるすてきな人々を中心に、より筆者らしい視点から、共感していただける方に向けて発信してゆきたい。よろしくおつきあいのほど。
(文=大矢アキオ<Akio Lorenzo OYA>/写真=大矢アキオ・アーカイブ/編集=藤沢 勝)

大矢 アキオ
Akio Lorenzo OYA 在イタリアジャーナリスト/コラムニスト。日本の音大でバイオリンを専攻、大学院で芸術学、イタリアの大学院で文化史を修める。日本を代表するイタリア文化コメンテーターとしてシエナに在住。NHKのイタリア語およびフランス語テキストや、デザイン誌等で執筆活動を展開。NHK『ラジオ深夜便』では、24年間にわたってリポーターを務めている。『ザ・スピリット・オブ・ランボルギーニ』(光人社)、『メトロとトランでパリめぐり』(コスミック出版)など著書・訳書多数。近著は『シトロエン2CV、DSを手掛けた自動車デザイナー ベルトーニのデザイン活動の軌跡』(三樹書房)。イタリア自動車歴史協会会員。
-
第950回:小林彰太郎氏の霊言アゲイン あの世から業界を憂う 2026.2.25 かつて『SUPER CG』の編集者だった大矢アキオが、『CAR GRAPHIC』初代編集長である小林彰太郎との交霊に挑戦! 日本の自動車ジャーナリズムの草分けでもある天国の上司に、昨今の日本の、世界の自動車業界事情を報告する。
-
第949回:「戦場のスパゲッティ」は実在するのか? イタリア陸軍ショップで聞いた 2026.2.19 世界屈指の美食の国、イタリア。かの国の陸軍は、戦場でもスパゲッティを食べるのか? 30℃でも溶けにくいチョコレートに、イタリア伝統のコース構成にのっとったレーション(戦闘糧食)などなど、エゼルチト(イタリア陸軍)のミリメシ事情に大矢アキオが迫る。
-
第948回:変わる時代と変わらぬ風情 「レトロモビル2026」探訪記 2026.2.12 フランス・パリで開催されるヒストリックカーの祭典「レトロモビル」。客層も会場も、出展内容も変わりつつあるこのイベントで、それでも変わらぬ風情とはなにか? 長年にわたりレトロモビルに通い続ける、イタリア在住の大矢アキオがリポートする。
-
第947回:秒殺で当確? 新型「ルノー・クリオ」が販売店にやってきた! 2026.2.5 欧州で圧巻の人気を誇る「ルノー・クリオ(日本名:ルーテシア)」がついにフルモデルチェンジ! 待望の新型は市場でどう受け止められているのか? イタリア在住の大矢アキオが、地元のディーラーにやってきた一台をつぶさにチェック。その印象を語った。
-
第946回:欧州に「277万円以下」のクルマなし! キューバ化を覚悟した冬 2026.1.29 欧州でお値段1万5000ユーロ未満の大衆車が壊滅状態に! 自動車の価格高騰はなぜ起き、そしていつまで続くのか? 一般の自動車ユーザーは、この嵐をいかにしてやり過ごそうとしているのか? イタリア在住の大矢アキオがリポートする。
-
![BYDシーライオン7 AWD(4WD)]() NEW
NEW
BYDシーライオン7 AWD(4WD)
2026.3.5JAIA輸入車試乗会2026堂々たるスタイルにライバルの上をいくパワーと一充電走行距離、そしてざっくり2割はお得なプライスを武器とする電気自動車「BYDシーライオン7」。日本市場への上陸から1年がたち、少しずつ存在感が増してきた電動クーペSUVの走りやいかに。 -
![ついにハードウエアの更新も実現 進化した「スバルアップグレードサービス」の特徴を探る]() NEW
NEW
ついにハードウエアの更新も実現 進化した「スバルアップグレードサービス」の特徴を探る
2026.3.5デイリーコラムスバルが車両の機能や性能の向上を目的とした「スバルアップグレードサービス」の第3弾を開始する。初めてハードウエアの更新も組み込まれた最新サービスの特徴や内容を、スバル車に乗る玉川ニコがオーナー目線で解説する。 -
![第951回:日本が誇る名車を再解釈 「ホンダNSXトリビュートby Italdesign」の開発担当者に聞く]() NEW
NEW
第951回:日本が誇る名車を再解釈 「ホンダNSXトリビュートby Italdesign」の開発担当者に聞く
2026.3.5マッキナ あらモーダ!2026年の「東京オートサロン」で来場者の目をくぎ付けにした「ホンダNSXトリビュートby Italdesign」。イタルデザインの手になる「ホンダNSX」の“再解釈”モデルは、いかにして誕生したのか? イタリア在住の大矢アキオが、開発関係者の熱い思いを聞いた。 -
![メルセデス・マイバッハSL680モノグラムシリーズ(4WD/9AT)【試乗記】]()
メルセデス・マイバッハSL680モノグラムシリーズ(4WD/9AT)【試乗記】
2026.3.4試乗記メルセデス・マイバッハから「SL680モノグラムシリーズ」が登場。ただでさえ目立つワイド&ローなボディーに、マイバッハならではのあしらいをたっぷりと加えたオープントップモデルだ。身も心もとろける「マイバッハ」モードの乗り味をリポートする。 -
![始まりはジウジアーロデザイン、終着点は広島ベンツ? 二転三転した日本版「ルーチェ」の道のり]()
始まりはジウジアーロデザイン、終着点は広島ベンツ? 二転三転した日本版「ルーチェ」の道のり
2026.3.4デイリーコラムフェラーリ初の電気自動車が「ルーチェ」と名乗ることが発表された。それはそれで楽しみな新型車だが、日本のファンにとってルーチェといえばマツダに決まっている。デザインが二転三転した孤高のフラッグシップモデルのストーリーをお届けする。 -
![第863回:3モーター式4WDの実力やいかに!? 「ランボルギーニ・テメラリオ」で雪道を目指す]()
第863回:3モーター式4WDの実力やいかに!? 「ランボルギーニ・テメラリオ」で雪道を目指す
2026.3.3エディターから一言電動化に向けて大きく舵を切ったランボルギーニは、「ウラカン」の後継たる「テメラリオ」をプラグインハイブリッド車としてリリースした。前に2基、リアに1基のモーターを積む4WDシステムの実力を試すべく、北の大地へと向かったのだが……。