第633回:ポスト・コロナ時代を技術の力で切り開け! 先進技術の総合展示会「CEATEC 2020」取材記(後編)
2020.10.30 エディターから一言 拡大 拡大 |
コロナ禍の影響により、初めて完全オンラインで行われたIT・エレクトロニクスの総合見本市「CEATEC(シーテック)」(主催:CEATEC 実施協議会)。各出展者が発表したさまざまな情報・技術の中から、モビリティーの未来に関するものを紹介する。
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
車内空間全体がインターフェイス
2020年10月20日から23日まで、4日間にわたって開催されたCEATEC 2020が閉幕した。開催初日の午前中はアクセス集中によるアクシデントがあったものの、その後は大きなトラブルはなかったようだ。
主催発表によれば、会期中の登録来場者数は8万5650人、延べ来場者数は13万人超であった。コロナ禍という特殊な状況を考慮すれば致し方ないところだが、2019年は登録来場者数が14万4491人、2018年は同15万6063人と、その差はあまりに大きい。
ただし、今年はオンライン開催ゆえに公式サイトは2020年12月31日まで閲覧でき、資料のダウンロードも可能。一部の個別企業のプレゼンテーション動画など閲覧できないものもあるが、主催団体によるカンファレンスはオンデマンドで配信されているので、ぜひチェックしてみてほしい。
なかでも、特にモビリティー関連の情報が充実していた企業としておすすめしたいのが、アルプスアルパインだ。昨今の自動車ではディスプレイやタッチスクリーンをインターフェイスとして使う例が少なくない。そこで今回、アルプスアルパインが打ち出したのが「デジタルキャビン」というコンセプトだ。
スマートフォンを使ってドアをアンロックし、シートに収まる。インストゥルメントパネルは全面が「視線の移動を最小限に抑えるよう設計された」という大型の曲面ディスプレイとなっており、交通情報や速度などといった、ドライブに必要な情報が表示される。その左右端に置かれているのは「Eミラー」だ。リアカメラやサイドビューカメラなど、複数の車載カメラがとらえた車両後方の映像をリアルタイムで合成処理して表示するもので、サイドミラーの役割を果たしている。
これに加え、ドアトリムにも操作デバイスが搭載されており、一見すると木目にしか見えないパネルに、オーディオやエアコン、シートポジションなどの操作スイッチが、必要な場合にのみ表示される仕組みとなっている。
触覚で機器と意思疎通を図る
ここで技術的に注目すべきは、操作内容を多彩な振動で手元にフィードバックする「ハプティック」だ。ディスプレイを使ったスイッチは多種多様な機能を盛り込める反面、メカニカルスイッチと違って触覚だけで操作することが難しい。特にドライバーが操作する類いのものは、わき見運転の原因にもなり得る。今後ますます自動車のIT化が進む中で、ハプティクス(触覚)は安全性と快適性のために欠かせない、非常に重要な技術なのだ。
アルプスアルパインは半世紀前から触覚の技術に取り組んでおり、2001年には世界で初めて自動車に同社の触感デバイスが採用されたことでも知られる。2021年1月から量産開始予定の「ハプティック リアクタ Heavy Type」は本体サイズが33mm×23mm×13mmと小型ながら、強い振動力を誇り、さまざまな車載操作機器の操作フィードバックに活用可能。ディスプレイの裏に隠れた黒子的存在だが、安全に大きく貢献することが期待される。
キャビン内に話を戻すと、先述の曲面ディスプレイなどと並んで大きな存在感を放っているのが、天井の大型ディスプレイだ。エンターテインメント系のコンテンツを楽しんだり、カーナビを見ながら同乗者と行き先を相談したり、さまざまな使い方ができる。またデジタルキャビンでは光や音の多彩な演出も可能で、移動体験を充実したものにしてくれるという。
このように、将来自動車には多種多様なIT機器が盛り込まれ、また自動運転/運転支援装置に関連するセンサー類も増加していくものと思われる。当然ながら、情報処理の負荷は大きくなる一方だ。今日のクルマには一台あたり100個から200個ものECU(Electronic Control Unit)が搭載されているというが、今後はますます設計が煩雑になることから、これらを集約するためにアルプスアルパインでは統合ECU「HPRA(High Performance Reference Architecture)」の開発に取り組んでいる。この統合ECUであれば、一台あたり数個の搭載で済むという。今回の発表はプロトタイプだが、ローンチまでにどこまで技術的進化を遂げるのか。今後の情報を待ちたい。
いま最も注目を集めている自動車技術の分野とは?
ほかにもモビリティー関連の情報をいくつかご紹介しよう。
タイコ エレクトロニクス ジャパン(TE)は、コネクターやケーブルなどといったエレクトロニクス機器のメーカーで、CEATECには車載用コネクターなどの製品を出展。またウェビナー(オンラインセミナー)も充実していた。なかでも同社トランスポーテーション・ソリューションズ事業本部CTOのアラン・アミーチ氏による「バッテリー・コネクティビティ~ニューノーマル社会における未来のモビリティーを支えるテクノロジートレンドとは?~」は、これからのモビリティーに直結するコンテンツだった。
アミーチ氏は現在の自動車業界のメガトレンドとして、「電動化」「先進安全機能」「自動運転」の3点を挙げる。ここ数年ですっかり浸透した「CASE」(Connected、Autonomous/Automated、Shared、Electric)と違って、「コネクト」や「シェア&サービス」に類する言葉は含まれないが、技術の観点からみれば当然といえるだろう。これからの時代、“つながらないクルマ”などあり得ないし、新たなサービスの創出は自動車技術の役割ではないからだ。
また、アミーチ氏はコロナ禍によるユーザーのニーズの変化も指摘した。以前はUberに象徴される新しいモビリティーサービスが話題を集め、「自動車は所有からシェアに移行する」と言われてきたが、ここ最近は日本でもマイカー回帰の流れが顕在化している。特にウェビナーにおいてアミーチ氏が注目したのが、オンラインでのクルマの購入が加速したこと。また購入に際して比重が置かれる項目として、衛生的な内装や換気機能の高さといった、これまであまり重要視されてこなかった点が注目を集めるようになったことも紹介した。
さらにウェビナー後半では、これから伸びるだろう技術の領域について、「EV(電気自動車)か、自動運転か」という話題に踏み込む。TEではEVが優勢だとみており、アミーチ氏は「バッテリーのコストが下がれば、2024年までに内燃機関車と同等のコストになると予測」としている。なぜEVなのか? そのためにどういった技術開発が進んでいるのか? 詳しくは8分38秒のウェビナー本編でぜひ確認してほしい。
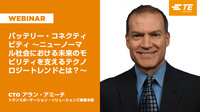 拡大 拡大 |
「みちびき」が実現するセンチメートル単位の測位
このほかにも、NEXCO東日本グループは「高速道路の雪と氷のテクノロジー ~Snow and ice control technology in highway~」と題した、“近未来における高速道路の雪氷対策のアニメ動画”と現在の雪氷対策技術の開発状況をまとめたプレゼンテーションを公開している。
ここで紹介される技術の一つが、準天頂衛星システム「みちびき」を活用した除雪車運転支援システムだ。みちびきとは、準天頂軌道の衛星が主体となって構成される日本の衛星測位システムのことで、現在は4基の衛星で運用されている。複数の衛星の情報を組み合わせることで、GPSでは難しかった山間部などの情報も得ることができ、またGPSよりもメッシュの細かい、それこそセンチメートル単位での測位が可能となっている。NEXCO東日本が発表した除雪車運転支援システムは、この技術を用いることで、路面の白線が目視できない状態でも、あるいは猛吹雪による視界不良の下でも、高速道路を安全に除雪できるという。
今年はコロナ禍でいつもと違う冬になりそうだが、政府のGoToキャンペーンを生かしてレジャーや帰省を楽しむ人もいるだろう。降雪は例年並みか、例年以上と予想されている。本格的な冬の到来までに、道路の安全対策を動画で見ておくのも一興ではないだろうか。
(文=林 愛子/写真=アルプスアルパイン、タイコ エレクトロニクス ジャパン、東日本高速道路/編集=堀田剛資)

林 愛子
技術ジャーナリスト 東京理科大学理学部卒、事業構想大学院大学修了(事業構想修士)。先進サイエンス領域を中心に取材・原稿執筆を行っており、2006年の日経BP社『ECO JAPAN』の立ち上げ以降、環境問題やエコカーの分野にも活躍の幅を広げている。株式会社サイエンスデザイン代表。
-
第858回:レースの技術を市販車に! 日産が「オーラNISMO RSコンセプト」で見せた本気 2026.1.15 日産が「東京オートサロン2026」で発表した「オーラNISMO RSコンセプト」。このクルマはただのコンセプトカーではなく、実際のレースで得た技術を市販車にフィードバックするための“検証車”だった! 新しい挑戦に込めた気概を、NISMOの開発責任者が語る。
-
第857回:ドイツの自動車業界は大丈夫? エンジニア多田哲哉が、現地再訪で大いにショックを受けたこと 2026.1.14 かつてトヨタの技術者としてさまざまな車両を開発してきた多田哲哉さん。現役時代の思い出が詰まったドイツに再び足を運んでみると、そこには予想もしなかった変化が……。自動車先進国の今をリポートする。
-
第856回:「断トツ」の氷上性能が進化 冬の北海道でブリヂストンの最新スタッドレスタイヤ「ブリザックWZ-1」を試す 2025.12.19 2025年7月に登場したブリヂストンの「ブリザックWZ-1」は、降雪地域で圧倒的な支持を得てきた「VRX3」の後継となるプレミアムスタッドレスタイヤ。「エンライトン」と呼ばれる新たな設計基盤技術を用いて進化したその実力を確かめるべく、冬の北海道・旭川に飛んだ。
-
第855回:タフ&ラグジュアリーを体現 「ディフェンダー」が集う“非日常”の週末 2025.11.26 「ディフェンダー」のオーナーとファンが集う祭典「DESTINATION DEFENDER」。非日常的なオフロード走行体験や、オーナー同士の絆を深めるアクティビティーなど、ブランドの哲学「タフ&ラグジュアリー」を体現したイベントを報告する。
-
第854回:ハーレーダビッドソンでライディングを学べ! 「スキルライダートレーニング」体験記 2025.11.21 アメリカの名門バイクメーカー、ハーレーダビッドソンが、日本でライディングレッスンを開講! その体験取材を通し、ハーレーに特化したプログラムと少人数による講習のありがたみを実感した。これでアナタも、アメリカンクルーザーを自由自在に操れる!?
-
![プジョー208 GTハイブリッド(FF/6AT)【試乗記】]() NEW
NEW
プジョー208 GTハイブリッド(FF/6AT)【試乗記】
2026.1.20試乗記「プジョー208」にマイルドハイブリッド車の「GTハイブリッド」が登場。仕組みとしては先に上陸を果たしたステランティス グループの各車と同じだが、小さなボディーに合わせてパワーが絞られているのが興味深いところだ。果たしてその乗り味は? -
![ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】]()
ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】
2026.1.19試乗記ベントレーのラグジュアリークーペ「コンチネンタルGT」のなかでも、ウェルビーイングにこだわったという「アズール」に試乗。控えめ(?)な680PSのハイブリッドがかなえる走りは、快適で満ち足りていて、ラグジュアリーカーの本分を感じさせるものだった。 -
![第327回:髪もクルマもナイスファイト!]()
第327回:髪もクルマもナイスファイト!
2026.1.19カーマニア人間国宝への道清水草一の話題の連載。日産の新型「ルークス」で夜の首都高に出撃した。しっかりしたシャシーとターボエンジンのパワフルな走りに感心していると、前方にスーパーカーの姿を発見。今夜の獲物は「フェラーリ・ローマ」だ! -
![日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!]()
日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!
2026.1.19デイリーコラムアメリカからの外圧による制度変更で、北米生産モデルの国内導入を決めたトヨタ。同様に、今後日本での販売が期待できる「海外生産の日本車」には、どんなものがあるだろうか? 清水草一が検証してみた。 -
![フェラーリ12チリンドリ(後編)]()
フェラーリ12チリンドリ(後編)
2026.1.18思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「フェラーリ12チリンドリ」に試乗。前編では伝家の宝刀であるV12エンジンを絶賛した山野。後編ではコンビを組むシャシーの印象を余すところなく聞いてみた。 -
![BYDシールAWD(4WD)【試乗記】]()
BYDシールAWD(4WD)【試乗記】
2026.1.17試乗記BYDのBEVサルーン「シール」の機能アップデートモデルが登場。強化のポイント自体はそれほど多くないが、4WDモデルの「シールAWD」は新たに電子制御式の可変ダンパーを装備したというから見逃せない。さまざまなシーンでの乗り心地をチェックした。
























