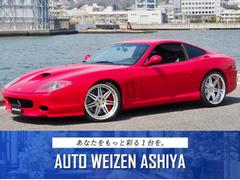第686回:フェラーリCEO突然の辞任に思う「イタリア人のフェラーリ離れ」
2020.12.17 マッキナ あらモーダ!わずか2年半でリタイア
フェラーリは2020年12月10日、ルイス・カミレーリCEOの辞任を発表した。
個人的理由としているが、欧州の一部メディアは健康上の理由、かつ過去数週間以内に新型コロナウイルスに感染したため、その治療を目的とした入院期間を経て目下自宅療養中と伝えている。
暫定CEOにはジョン・エルカン会長(1976年生まれ)が就任する。
ルイス=キャリー・カミレーリ氏はマルタ人家族のもと、1955年にエジプトのアレクサンドリアで生まれた。ローザンヌ大学のビジネススクールで経営学を専攻。卒業後は現地企業のアナリストを経て、1978年にタバコ会社であるフィリップ・モリスに入社した。一時食品メーカーのクラフトフーズで会長を務めたが2002年に戻り、フィリップ・モリス・インターナショナル(PMI)の会長に就任した。
2017年にはPMIの会長職と兼任するかたちで、フェラーリの経営に取締役として参画。2018年7月のセルジオ・マルキオンネCEO急逝にともない、後継としてCEOに指名された。
今回、カミレーリ氏はフェラーリCEOとともにフィリップ・モリス会長も辞任した。
カミレーリ氏がCEOを務めた約2年半のフェラーリの業績は好調だった。本稿執筆にあたりミラノ証券取引所におけるデータを確認してみると、彼の就任直後である2018年7月31日の株価は116.81ユーロであったのに対し、2020年12月10日には176.75ユーロと、51%も上昇している。
新型コロナウイルスが世界の自動車業界を震撼(しんかん)させた2020年も、業績を維持した。
2020年第3四半期の純利益は1億7100万ユーロで、前年同期比1%増にとどまったが、主力事業である自動車の営業売上高は「モンツァSP1」「モンツァSP2」の好調に支えられて2.6%増を記録した。
ほとんど報道されなかった
第672回でリポートした「フェラーリ・ローマ」は、やみくもにハイパフォーマンスやスポーティネスをアピールしない、知的なスーパースポーツカーへの脱皮を感じさせた。筆者としては、フェラーリがこれから進むべき正しき道として、極めて好意的に捉えた。
フェラーリは2019年に2007年比で35%のCO2エミッション低減を達成している。初の量産プラグインハイブリッドモデル「SF90ストラダーレ」も、それを加速させる意欲的な取り組みといえる。それらのけん引役を果たしたカミレーリ氏の辞任は、残念である。
しかし、イタリアにおいてカミレーリ氏の電撃辞任は、公営放送「RAI」も民放メディアセットも、ヘッドラインどころかニュースの中でもほとんど報じなかった。
経済紙やスポーツ紙、そして一部のペイテレビも、トップ扱いではなかった。
代わりにヘッドラインを飾ったものといえば、政局であった。
EUの新型コロナ復興基金の対応をめぐり、連立与党「イタリア・ヴィーヴァ」を率いるマッテオ・レンツィ元首相が政府案に強く異議を唱え、連立離脱を示唆したニュースである。
それ以上にカミレーリCEO辞任をかき消したのは、12月9日に死去したサッカー元イタリア代表のパオロ・ロッシ氏に関する続報だった。なにしろ先月のディエゴ・マラドーナ元選手死去の記憶を完全に忘れ去らせるほどの時間が割かれたのである。
しかし今回は一歩踏み込んで、筆者は自動車の世界から、フェラーリがイタリア人の関心から遠ざかっている理由を検証してみたい。
本国イタリアにおけるフェラーリの販売台数は微々たるものである。2020年11月の登録台数は40台。日本における同月の104台からすると、2分の1以下だ(データ参照:ANFIAおよびJAIA)。
だからといって、イタリア人がフェラーリを嫌いになったわけではない。自動車登場以前の19世紀末から、高級品は自ら使うのではなく創造して輸出し、別の意味で自分たちの生活を充実させることが、彼らに息づいた伝統である。
郷土愛あふれるイタリア人にとって、フェラーリが自国の技術とデザインを語るうえで誇らしいプロダクトであることは不変だ。
地震被災地への支援や新型コロナにおける人工呼吸器部品の供給なども評価されている。フェラーリが大学と連携して行っている研修制度に毎年多くの学生が応募するのも、その証左のひとつだ。
以下は、それを踏まえての説明である。
イタリア人の興味が薄れた理由
第1はフォーミュラワンレース、つまりF1の不振である。イタリア人のF1に対する関心が冷めたのは、テレビの視聴者数に明確に表れている。
2000年代初頭のイタリアにおいて、F1の一戦あたりのテレビ視聴者は1400万世帯を超えていた。
かつて筆者がイタリアに移り住んだ1990年代末、週末にイタリアの住宅街を歩けば、ナイフやフォークが皿にぶつかる音とともにF1中継の音が聞こえてきたものだ。
そしてF1決勝翌日となる週明けには、一見自動車に関心がないような人までF1の話をしていたものである。筆者の知人で主婦のアンナ・マリアでさえ毎月曜日、日本人の筆者を見かけると「タクーマ・サトー(佐藤琢磨選手のこと)!」などと言っていた。
ところが2007年には、約700万世帯にまで減少した。そこに2009年に始まったスクーデリア・フェラーリの不振も輪をかけた。
2018シーズンには、長年F1を予選も含めて地上波で全戦放映してきた公営放送局「RAI」が放映権を手放し、代わりにペイテレビ「スカイ」が放映権を獲得した。
アルファ・ロメオのF1復帰も、人気を盛り返させるには至らなかった。
視聴世帯数は低下を続け、2018年には300万台となり、2020年に行われた最初の7戦の平均は224万台にすぎなかった(データ参照:P300IT)。つまり20年間で6分の1以下に減ってしまったことになる。
事実、近年ではF1の話題を持ち出すイタリア人に会うことはまれになった。F1熱の希薄化は、つまりフェラーリへの関心の希薄化へとつながった。そうした空気を反映して、メディアはフェラーリのCEOが辞任してもほとんど報道しなかったのである。
第2は、企業としてのフェラーリ自身のイタリア離れだ。2015年、フェラーリはアムステルダムに持ち株会社を新設したうえで、登記上の本社を移転している。事実、今日の正式な社名は、オランダで株式会社を意味する「N.V.」を付加した「Ferrari N.V.」である。
同様にオランダに本社を移したフィアット・クライスラー・オートモービルズ(FCA)に続くものだった。煩雑を極めるイタリアの、税制を含めた法制度を回避すべく、敏腕財務マンであったマルキオンネ元CEOが敢行した、ウルトラC的手段であった。
すべてのイタリア人が意識しているわけではないが、国外の法人となり、外国人がトップに就任するようになった国際企業に、以前ほどの思い入れはなくなっているのだ。
参考までにフェラーリ関係者に聞いたところ、アムステルダムにはきちんと常駐の社員がいるという。
求められるのはカリスマ性?
イタリア人のフェラーリ離れの第3の理由は、経営トップのカリスマ性の欠如であろう。
フェラーリは2020年1月、戦略コンサルティング会社のブランド・ファイナンスによる相対的ブランド力を測定した調査「最も強力なブランド500」で、ディズニーなどを抑えて2年連続の首位に輝いている。同じ調査によると、フェラーリのブランド価値は91億ドル(約9464億円)に相当するという。
ただし、イタリアにおけるCEOの知名度に関して言えば、今回辞任したルイス・カミレーリ氏は、かつて彼と同じ地位にあったルカ=コルデーロ・ディ・モンテゼーモロ氏(1947年生まれ)には遠く及ばなかった。
モンテゼーモロ氏は、イタリアでスターに準ずる存在であったといってよい。ジョン・エルカン会長の祖父にあたるジョヴァンニ・アニエッリ氏同様、女性週刊誌までもがそのプライベートをつぶさに報じた。テレビのバラエティーショーにチャンネルを合わせれば、モンテゼーモロ氏のそっくりさんがレギュラー出演していた。
筆者の記憶をたどれば、モーターショーにおけるモンテゼーモロ氏の英語スピーチは、明らかにイタリア人アクセントであった。しかし棒読みではなく、出席者たちの目を常に見て語りかけるという意欲にあふれていた。囲み取材においては、他の欧州ジャーナリストと異なり、懇意の間柄ではない筆者の質問にも真面目に答えてくれたことを記憶している。
2015年、モンテゼーモロ氏がフェラーリを去ることになったとき、多くのテレビチャンネルは、彼のF1監督時代からの歴史フィルムまで引っ張り出して詳しく報じた。
ポピュラーカーには当てはまらないが、高級ブランドの場合、トップのスター性は、時にブランドのバリュー向上にもつながる。それはかつてのAppleのスティーブ・ジョブス氏や今日のテスラとイーロン・マスク氏を見れば明らかだ。それが決して正しいこととは言わないが、仮にプロダクトに未完成な部分があっても、経営者のキャラクターによって容認されてしまうようなパワーを持っている。
しかし、モンテゼーモロ氏が醸し出していたフェラーリのトップにおけるスター性が、後任のマルキオンネ氏とカミレーリ氏では希薄になってしまった。
個人のキャラクターを重んじる、イタリア人の大半が感情移入するには、遠い存在になってしまったのである。
後継者の大穴は彼だ!
折しもライバルのランボルギーニでは12月1日、ステファン・ヴィンケルマン氏(1964年生まれ)が、約4年ぶりに会長兼CEOとして復帰を果たした。同じフォルクスワーゲン グループのブガッティの会長も続投する。
2005年から2016年にかけてもCEOを務めていた同氏はドイツ生まれであることもあり、一般にはモンテゼーモロ氏ほどの知名度は獲得していない。
しかし自動車ファンの世界では、モンテゼーモロ氏とともにイタリア製スーパースポーツカーブランドを代表する2大スターだった。手ごわい相手が帰ってきた。
欧州の経済メディアは、早くもカミレーリ氏の後継者候補として、いくつかの名前を示唆している。
かつてスクーデリア・フェラーリの代表を務め、ヴィンケルマン氏の前任としてランボルギーニCEOの職にあったステファノ・ドメニカリ氏は、当初の予定どおりF1の運営団体「フォーミュラワン・グループ」に移籍するとして、フェラーリの次期CEO候補からは外れているらしい。
彼らが名前を挙げているのは、ボーダフォン・グループ元CEOのヴィットリオ・コラオ氏(1961年生まれ)やAppleの前デザインダイレクター、ジョナサン=ポール・アイブ氏(1967年生まれ)だ。
本当にこの2人が候補だとしたら、フェラーリが堅実なエグゼクティブをとるか、カリスマ的クリエイターをとるか、かなりエキサイティングな選択といえる。
それらを追うように12月12日、イタリアの『イル・メッサッジェーロ』紙は、FCAでCEOを務めているマイク・マンリー氏(1964年生まれ)が有力と伝えた。2021年第1四半期に予定されている、FCAとグループPSAの経営統合後の企業グループであるステランティスのCEOは、すでに現グループPSAのカルロス・タバレス氏に内定しているから、マンリー氏に向け、彼のプライドも重んじた代替ポストということにもなる。
いずれにせよ、ジョン・エルカン会長率いるアニエッリ家の投資会社で、フェラーリ株の24%を握るエグゾールが、過去と同様、CEO決定に力を及ぼすことは間違いない。
いっぽう、筆者が考える“大穴”としては、モンテゼーモロ氏の返り咲き、もしくはジョン・エルカン会長の弟で2019年まで社外取締役を務め、今日のイタリアを代表するファッショニスタでもあるラポ・エルカン氏(1977年生まれ)だ。派手さでは誰にも負けない2人、ではある。
(文=大矢アキオ<Akio Lorenzo OYA>/写真=Akio Lorenzo OYA、フェラーリ、ランボルギーニ/編集=藤沢 勝)

大矢 アキオ
Akio Lorenzo OYA 在イタリアジャーナリスト/コラムニスト。日本の音大でバイオリンを専攻、大学院で芸術学、イタリアの大学院で文化史を修める。日本を代表するイタリア文化コメンテーターとしてシエナに在住。NHKのイタリア語およびフランス語テキストや、デザイン誌等で執筆活動を展開。NHK『ラジオ深夜便』では、24年間にわたってリポーターを務めている。『ザ・スピリット・オブ・ランボルギーニ』(光人社)、『メトロとトランでパリめぐり』(コスミック出版)など著書・訳書多数。近著は『シトロエン2CV、DSを手掛けた自動車デザイナー ベルトーニのデザイン活動の軌跡』(三樹書房)。イタリア自動車歴史協会会員。
-
第944回:こんな自動車生活は最後かもしれない ―ある修理工場で考えたこと― 2026.1.15 いつもお世話になっている“街のクルマ屋さん”で、「シトロエン・メアリ」をさかなにクルマ談議に花が咲く。そんな生活を楽しめるのも、今が最後かもしれない。クルマを取り巻く環境の変化に感じた一抹の寂しさを、イタリア在住の大矢アキオが語る。
-
第943回:スバルとマツダ、イタリアでの意外なステータス感 2026.1.8 日本では、数ある自動車メーカーのひとつといった感覚のスバルとマツダだが、実はイタリアでは、根強いファンを抱える“ひとつ上のブランド”となっていた! 現地在住の大矢アキオが、イタリアにおけるスバルとマツダのブランド力を語る。
-
第942回:「デメオ劇場」は続いていた! 前ルノーCEOの功績と近況 2025.12.25 長年にわたり欧州の自動車メーカーで辣腕(らつわん)を振るい、2025年9月に高級ブランドグループのCEOに転身したルカ・デメオ氏。読者諸氏のあいだでも親しまれていたであろう重鎮の近況を、ルノー時代の功績とともに、欧州在住の大矢アキオ氏が解説する。
-
第941回:イタルデザインが米企業の傘下に! トリノ激動の一年を振り返る 2025.12.18 デザイン開発会社のイタルデザインが、米IT企業の傘下に! 歴史ある企業やブランドの売却・買収に、フィアットによるミラフィオーリの改修開始と、2025年も大いに揺れ動いたトリノ。“自動車の街”の今と未来を、イタリア在住の大矢アキオが語る。
-
第940回:宮川秀之氏を悼む ―在イタリア日本人の誇るべき先達― 2025.12.11 イタリアを拠点に実業家として活躍し、かのイタルデザインの設立にも貢献した宮川秀之氏が逝去。日本とイタリアの架け橋となり、美しいイタリアンデザインを日本に広めた故人の功績を、イタリア在住の大矢アキオが懐かしい思い出とともに振り返る。
-
![クルマの乗り味の“味”って何だ?]() NEW
NEW
クルマの乗り味の“味”って何だ?
2026.1.20あの多田哲哉のクルマQ&A「乗り味」という言葉があるように、クルマの運転感覚は“味”で表現されることがある。では、車両開発者はその味をどう解釈して、どんなプロセスで理想を実現しているのか? 元トヨタのエンジニア、多田哲哉さんに聞いた。 -
![プジョー208 GTハイブリッド(FF/6AT)【試乗記】]() NEW
NEW
プジョー208 GTハイブリッド(FF/6AT)【試乗記】
2026.1.20試乗記「プジョー208」にマイルドハイブリッド車の「GTハイブリッド」が登場。仕組みとしては先に上陸を果たしたステランティス グループの各車と同じだが、小さなボディーに合わせてパワーが絞られているのが興味深いところだ。果たしてその乗り味は? -
![ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】]()
ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】
2026.1.19試乗記ベントレーのラグジュアリークーペ「コンチネンタルGT」のなかでも、ウェルビーイングにこだわったという「アズール」に試乗。控えめ(?)な680PSのハイブリッドがかなえる走りは、快適で満ち足りていて、ラグジュアリーカーの本分を感じさせるものだった。 -
![第327回:髪もクルマもナイスファイト!]()
第327回:髪もクルマもナイスファイト!
2026.1.19カーマニア人間国宝への道清水草一の話題の連載。日産の新型「ルークス」で夜の首都高に出撃した。しっかりしたシャシーとターボエンジンのパワフルな走りに感心していると、前方にスーパーカーの姿を発見。今夜の獲物は「フェラーリ・ローマ」だ! -
![日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!]()
日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!
2026.1.19デイリーコラムアメリカからの外圧による制度変更で、北米生産モデルの国内導入を決めたトヨタ。同様に、今後日本での販売が期待できる「海外生産の日本車」には、どんなものがあるだろうか? 清水草一が検証してみた。 -
![フェラーリ12チリンドリ(後編)]()
フェラーリ12チリンドリ(後編)
2026.1.18思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「フェラーリ12チリンドリ」に試乗。前編では伝家の宝刀であるV12エンジンを絶賛した山野。後編ではコンビを組むシャシーの印象を余すところなく聞いてみた。