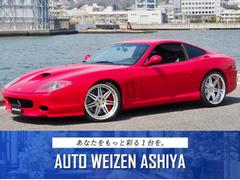フェラーリF8スパイダー(MR/7AT)
異次元のプロムナードカー 2021.02.02 試乗記 フェラーリから「F8トリブート」のオープントップバージョンにあたる「F8スパイダー」が登場。ミドシップフェラーリならではの圧倒的なパフォーマンスと、オープンエアモータリングの心地よさを併せ持つ、希有(けう)な一台の魅力に触れた。跳ね馬に見るミドシップオープンの系譜
そもそもレースフィールドから市販車へとフィードバックされた、ピュアスポーツの理想的パッケージ。そんなミドシップレイアウトにオープンドライブのお楽しみを組み合わせたモデルが世に出始めたのは1970年前後のことだ。1世紀以上に及ぶ自動車史の尺度でみれば、今日的でハイカラなぜいたくの表現ということになるだろうか。
フェラーリで言えば初の量産ミドシップとなった「ディーノ206/246」シリーズにタルガトップの「GTS」が加わったのは1971年のこと。その実質的後継モデルともいえる「308/328」世代、そして「348/F355」世代と、このタルガトップスタイルは受け継がれた。が、並行して348/F355世代ではピラーレスのフルオープンを併売。こちらは「スパイダー」を名乗ることで差別化されていた。
その後、ボディー構造に剛性の確保がしやすく上屋の自由度が高いアルミスペースフレーム形式を採るようになったこともあり、「360/F430」世代ではオープンモデルをフルオープンスタイルのスパイダーに一本化。そして「458/488」世代のスパイダーは、それまでのホロ屋根からメタルトップを格納するスタイルへと進化した。
そしてこのF8スパイダーもメタルトップを継承している。開閉方式も同様で、2分割された天板が反転しながら重なり、コンパクトに束ねられながらトノカバーの内に収まっていく。所要時間は開閉ともに約14秒。そして約45km/h以内であれば走行中での開閉も可能だ。
「F8トリブート」と違うところ、同じところ
クーペモデルのF8トリブートはスリット付きの樹脂ウィンドウを組み合わせたファストバックスタイルに「F40」との連続性を感じるが、F8スパイダーの側はヘッドレスト背後のロールオーバーバーから後端へと連なる2つのバットレス(梁<はり>)が、F355までのミドシップフェラーリを象徴するトンネルバック&フラットデッキのスタイルを思い起こさせる。デザイン的なすみ分けは458や488の代に対して、より明瞭で巧みになった。
また、F8トリブートではクーリング能力の向上とともに、Sダクトやブロウンスポイラーなどの新しい空力要素を取り入れて、猛烈なパフォーマンスを御する重要なファクターをデザインと両立させている。F8スパイダーでは前述の通り車体後半の形状が異なるものの、冷却や空力のセクションへと効率的に導風する形状が織り込まれており、オープン化によるドライバビリティーへの影響はないという。
実際、F8トリブートに対しての実用面での差異は、ほぼほぼ無視できるレベルだろう。トンネルバックスタイルの影響で斜め後方視界がさらに厳しくなる点は致し方ないが、あとは我慢するようなことはない。Sダクトの影響で、フロントトランクの容量は488世代に対して30リッター減っているが、シート背後には相変わらずジャケットや手荷物などを置けるスペースが確保されている。想定されるライバルの使い勝手を知るに、そつのなさはさすがにセグメントリーダーの風格だ。
動力性能も快適性もクーペと同等
F8スパイダーのアーキテクチャーは458時代からの流れをくんでおり、コックピット環境は最新の「SF90ストラダーレ」や「ローマ」に対して1世代古い。ディスプレイの解像度も粗く、表示の切り替えも物理スイッチを介して階層を掘り返す程度のものだ。
センターに構えるレッドゾーン8000rpmのタコメーターも物理針を使ったものだし、デジタルが主流になりつつある昨今ではいささか古風にみえてくる。が、だからイイと思うのは僕だけではないはずだ。純然たる内燃機の終えんが近づくほどに、オッさんはこういうクラシックなディテールへの未練を吐露するようになっていくのだろう。
ルーフシステムのおかげでF8トリブートよりも70kg重いF8スパイダーだが、それでも先代の488スパイダーに比べると20kgほど軽量化が施されているという。720PS/770N・mという猛烈な火力はその重量増をあっさり黙殺し、0-100km/h加速は2.9秒、最高速は340km/hと、動力性能を示す数値はF8トリブートと変わらない。もちろんV8ミドシップスポーツとしては最速級だ。
日常域での快適性についても、F8トリブートとの差異は感じられない。クルマに任せて走る限り、エンジンの回転数は2500rpmに及ばない領域でも十分に流れに乗ることができるため、キャビンは至って平穏だ。メカノイズや排気音も淡々と刻まれ、必要以上にうなることはない。耳につくものといえば、時折タイヤが巻き上げる小石や砂がホイールハウスをたたく音くらいのものだろうか。大がかりなトノカバーや2分割されたトップなどから、きしみやガタツキが漏れてこないのもお見事だ。ともあれ、「屋根を開ければ七難隠す」ともやゆされるオープンカーにありがちなネガの類いはまったくみえてこない。日々乗っていれば多くの時間がそうなるだろうクローズドの状態でも、F8スパイダーはクーペとしての振る舞いを完璧に演じている。
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
公道での振る舞いはその一面にすぎない
一方で、オープンカーに期待する気持ちよさという点においては、「あけすけ」というほどにはいかない。ディフレクターを兼ねるリアウインドウを降ろせば低速域でも気持ちよく風がキャビンに流れるが、視界的には前方や上方はともあれ、側方や頭の後ろには大きなバットレスがもたらす圧迫感がつきまとう。ただ、開ければタルガトップ以上フルオープン未満の開放感というのは、まさにこのルーフシステムの狙い通りということになるのだろう。このくらいの囲まれ感があったほうが、アクセルを踏むにも気持ち的に安心できる、という見方もできる。
大げさでなくそう思うほど、このクルマの爆速ぶりはしゃれにならない。踏むたびに歯を食いしばるほどの加速力に驚かされれば、巧みなボディーコントロールデバイスの連携もあって、踏めば踏むほどにアペックスへと食らいついていくコーナリングも異次元だ。公道では到底その限界を垣間見ることはできず、F8トリブートとの重量や剛性の差はクローズドコースでなければ感じられないと断言できる。
フェラーリのオープンカーといえば走りは二の次で見せびらかしにはうってつけ、頂点クラスのプロムナード物件……と、そんなイメージを多くの人は抱くのではないだろうか。このクルマにも当然そういう側面はあるだろう。加えて、458/488スパイダーの中古車流通価格が高値超安定なこともあり、その費用対効果からF8スパイダーはかなりの争奪戦になっているとも聞く。
が、このクルマの真価は現在のスーパースポーツの頂点級ともいえるパフォーマンスを、望外の多用途性と両立できていることにある。街なかをズルズル引き回しながらその片面だけを堪能して終わるのはなんとももったいない話だ。幸運にも手に入れることができた方には、ぜひもう一つの顔をのぞきに、クローズドコースへと赴いてほしい。
(文=渡辺敏史/写真=荒川正幸/編集=堀田剛資)
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
テスト車のデータ
フェラーリF8スパイダー
ボディーサイズ:全長×全幅×全高=4611×1979×1206mm
ホイールベース:2650mm
車重:1640kg
駆動方式:MR
エンジン:3.9リッターV8 DOHC 32バルブ ツインターボ
トランスミッション:7段AT
最高出力:720PS(530kW)/8000rpm
最大トルク:770N・m(78.5kgf・m)/3250rpm
タイヤ:(前)245/35ZR20 95Y XL/(後)305/30ZR20 103Y XL(ミシュラン・パイロットスーパースポーツ)
燃費:--km/リッター
価格:3657万円/テスト車=万円
オプション装備:ボディーカラー<ビアンコ セルビノ>/鍛造ホイール<グリージョ コルサ マット>/カラードブレーキキャリパー<アルミニウム>/チタニウムホイールボルト/スクーデリアフェラーリ フェンダーエンブレム/カーボンファイバーボンネット Sダクト/カーボンファイバー エアスプリッター/カーボンファイバー リアブートトリム/カーボンファイバー エンジンカバー/カーボンファイバー トランクカバー/リアパーキングカメラ/フロントパーキングセンサー/チタニウムエキゾーストパイプ/インテリアカラー<クオイオ>/カラードステッチ<グリージョ キアーロ>/カラード ロゴ付きカーペット<ヌオーヴォ クオイオ>/フル電動シート/ヘッドレストの跳ね馬刺しゅう<ライトグレー>/カーボンファイバー ドアハンドル/カラー レヴカウンター<イエロー>/カーボンファイバー ドライブゾーン+LED/カーボンファイバー レーシングパドル/カーボンファイバー ダッシュボード/カーボンファイバー センターブリッジ/パッセンジャーディスプレイ/Hi-Fiオーディオ
テスト車の年式:2020年型
テスト開始時の走行距離:4372km
テスト形態:ロードインプレッション
走行状態:市街地(--)/高速道路(--)/山岳路(--)
テスト距離:--km
使用燃料:--リッター(ハイオクガソリン)
参考燃費:--km/リッター

渡辺 敏史
自動車評論家。中古車に新車、国産車に輸入車、チューニングカーから未来の乗り物まで、どんなボールも打ち返す縦横無尽の自動車ライター。二輪・四輪誌の編集に携わった後でフリーランスとして独立。海外の取材にも積極的で、今日も空港カレーに舌鼓を打ちつつ、世界中を飛び回る。
-
BYDシールAWD(4WD)【試乗記】 2026.1.17 BYDのBEVサルーン「シール」の機能アップデートモデルが登場。強化のポイント自体はそれほど多くないが、4WDモデルの「シールAWD」は新たに電子制御式の可変ダンパーを装備したというから見逃せない。さまざまなシーンでの乗り心地をチェックした。
-
マツダCX-60 XDドライブエディション ナッパレザーパッケージ(4WD/8AT)【試乗記】 2026.1.14 「マツダCX-60」に新グレードの「XDドライブエディション ナッパレザーパッケージ」が登場。スポーティーさと力強さ、上質さを追求したというその中身を精査するとともに、国内デビューから3年を経た“ラージ商品群第1弾”の成熟度をチェックした。
-
カワサキKLX230シェルパS(6MT)【レビュー】 2026.1.13 その出来には“セロー乗り”も太鼓判!? カワサキのトレイルバイク「KLX230シェルパ」に、ローダウン仕様の「シェルパS」が登場。安心の足つき性で間口を広げた一台だが、実際に走らせてみると、ストリートでも楽しめるオールラウンダーに仕上がっていた。
-
メルセデス・ベンツC220dラグジュアリー(FR/9AT)【試乗記】 2026.1.12 輸入車における定番の人気モデル「メルセデス・ベンツCクラス」。モデルライフ中にも年次改良で進化し続けるこのクルマの、現在の実力はいかほどか? ディーゼルエンジンと充実装備が魅力のグレード「C220dラグジュアリー」で確かめた。
-
日産ルークス ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション(FF/CVT)【試乗記】 2026.1.10 日産の軽スーパーハイトワゴン「ルークス」がフルモデルチェンジ。「見えない危険が……」のテレビCMでお茶の間をにぎわせているが、走る、曲がる、止まるをはじめとしたクルマ全体としての仕上がりはどうか。最上級グレードをテストした。
-
![ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】]() NEW
NEW
ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】
2026.1.19試乗記ベントレーのラグジュアリークーペ「コンチネンタルGT」のなかでも、ウェルビーイングにこだわったという「アズール」に試乗。控えめ(?)な680PSのハイブリッドがかなえる走りは、快適で満ち足りていて、ラグジュアリーカーの本分を感じさせるものだった。 -
![第327回:髪もクルマもナイスファイト!]() NEW
NEW
第327回:髪もクルマもナイスファイト!
2026.1.19カーマニア人間国宝への道清水草一の話題の連載。日産の新型「ルークス」で夜の首都高に出撃した。しっかりしたシャシーとターボエンジンのパワフルな走りに感心していると、前方にスーパーカーの姿を発見。今夜の獲物は「フェラーリ・ローマ」だ! -
![日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!]() NEW
NEW
日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!
2026.1.19デイリーコラムアメリカからの外圧による制度変更で、北米生産モデルの国内導入を決めたトヨタ。同様に、今後日本での販売が期待できる「海外生産の日本車」には、どんなものがあるだろうか? 清水草一が検証してみた。 -
![フェラーリ12チリンドリ(後編)]()
フェラーリ12チリンドリ(後編)
2026.1.18思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「フェラーリ12チリンドリ」に試乗。前編では伝家の宝刀であるV12エンジンを絶賛した山野。後編ではコンビを組むシャシーの印象を余すところなく聞いてみた。 -
![BYDシールAWD(4WD)【試乗記】]()
BYDシールAWD(4WD)【試乗記】
2026.1.17試乗記BYDのBEVサルーン「シール」の機能アップデートモデルが登場。強化のポイント自体はそれほど多くないが、4WDモデルの「シールAWD」は新たに電子制御式の可変ダンパーを装備したというから見逃せない。さまざまなシーンでの乗り心地をチェックした。 -
![新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る]()
新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る
2026.1.16デイリーコラム英国のモーターサイクル史にあまたの逸話を残してきた名門、ノートンが、いよいよ再始動! その数奇な歴史を振り返るとともに、ミラノで発表された4台の次世代モデルを通して、彼らが思い描く未来像に迫った。