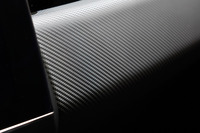第597回:外装デザインのリーダーを直撃取材! デザインにみる新型「ルノー・ルーテシア」のキモ
2019.11.01 エディターから一言 拡大 拡大 |
第46回東京モーターショーにおいて、日本でもいよいよ公開された新型「ルノー・ルーテシア」。このクルマは、好評を博した従来モデルから何を受け継ぎ、何を刷新したのか? デザインに見るポイントを、モーターショーに合わせて来日したキーマンに聞いた。
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
あまたのメーカーを渡り歩いてルノーへ
新型ルーテシアが日本初公開された今回の東京モーターショー。その開幕に合わせて来日したアンソニー・ロー(Anthony LO)氏は、ルノーの“エクステリアデザイン担当バイスプレジデント”の肩書をもつ。バイスプレジデントを直訳すると副社長だが、ルノーでは“理事”に相当する役職のようだ。
――公表されているプロフィールによると、ローさんは香港でお生まれになって、イギリスのロイヤル・カレッジ・オブ・アート(国立ロンドン美術大学)を卒業した後、まずはロータスに入社されたとか……。
はい、1987年にロータスに入社して、1990年にアウディに移籍しました。それからメルセデス・ベンツの東京デザインスタジオで7年ほど仕事してから、GMヨーロッパに移りました。GMではサーブやオペルのアドバンストデザインを担当しました。
ヴァン・デン・アッカーが主導した組織改革
――ローさんがルノーに招かれたのは2010年4月とのことですから、そのときはすでにデザイン部門のトップは現在のローレンス・ヴァン・デン・アッカー(ルノー・コーポレートデザイン担当常務)さんだったわけですね。
私が声をかけられた当時のルノーは、フランスのスタンダードからよりグローバルなブランドに脱皮しようとしていました。私のボスであるヴァン・デン・アッカーは2009年5月にルノーにやって来て、デザイン部門の組織を変えようとしていました。私の場合、いろいろな会社で働いた経験や国際的なプロフィールが評価されたのだと思います。
――現在のルノーデザインの組織は以前とは異なるわけですか?
以前はひとつの商品企画に対して3~4名の担当デザイナーでチームを結成して、専属で数年かけてデザインをつくり上げていました。ですが、現在のルノーデザインではコンセプトカーから実際の商品、しかも「メガーヌ」やルーテシアなどの乗用車と「カングー」のような商用車も分け隔てなく、多くのデザイナーが手がけるようになりました。そのなかで、私はルノー全車のエクステリアデザインを統括する立場にいるわけです。
大事なのは「ルーテシア」に見えること
――さて、いよいよ日本でも実車が公開された新型ルーテシアですが、第一印象は従来の4代目ルーテシア(ルーテシア4)の正常進化に見えます。
新型ルーテシアの開発プロジェクトを開始するにあたり、われわれはまずユーザーやマーケットの声を集めました。そこで共通して評価いただいたのは、とりわけエクステリアデザインでした。このときに得られたフィードバックを簡単にまとめると、ルーテシア4が選ばれた理由でもっとも多かったのがエクステリアデザインであり、逆に選ばれなかった一番の理由はインテリアのデザインや質感だった……というものです。
――それゆえにエクステリアデザインは正常進化。それにしても、新型ルーテシアは実際にはすべてが新しいのに、われわれ素人には、なぜルーテシアにしか見えないのでしょうか?
新型ルーテシアのエクステリアでルーテシア4を踏襲している最大のポイントはシルエットです。具体的には肉感的なフロントフェンダーやサイドビュー、そして筋肉質な印象を与えるリアのフォルムです。それとサイドウィンドウグラフィックにもルーテシアらしさを感じていただけるはずです。
このように、エクステリアデザインは“ルーテシアに見えること”を大きなテーマとしましたが、逆にルーテシア4から大きく変わったのは商品としてのストラテジーです。簡単にいうと、新型ルーテシアは“モアプレミアム”なクルマとして、すべてを“アップマーケット(=上級移行)”することを目指しました。
これはグレードにもよるのですが、各部のメッキをツヤが控えめのサテンクロームにして、ヘッドライトもフルLEDを基本としました。さらに今回の東京モーターショーに出展しているR.S.ラインでいうと、フロントバンパーのデザインも非常に高級感あるものになっています。
背景にあるBセグメントの“上級移行”
――そんなエクステリアとは対照的に、インテリアデザインは大きく変わっています。
先ほども申し上げたように、ルーテシア4では好評だったエクステリアに対して、インテリアはあまり評価いただけませんでした。ですので、新型ルーテシアのデザイン的な方向としては、エクステリアは正常進化としながらもよりプレミアムに……そしてインテリアはデザインから大きく変えることにしたのです。
さらにいうと、新しいインテリアデザインでは、まず大きな縦型ディスプレイを装備することが最初から決まっていて、これをいかにデザインに融合させるかが最大の課題となりました。
――確かにBセグメントに不似合い(?)なほど立派なディスプレイだけでなく、インテリアの質感は飛躍的に向上していますね。
ルーテシアのようなBセグメント車にアップマーケットが求められるようになった理由はいくつかあります。ひとつはもちろん、現在ルーテシアや他社Bセグメントに乗っているユーザーに“もっといいもの”を提供するためですが、もうひとつの大きな理由に、日本だけでなく欧州でもダウンサイズ需要が増えていることがあります。
たとえば、今までメガーヌに乗っていたユーザーは、従来のルーテシアにはどうしても物足りなさを感じていました。新型ルーテシアが機能・装備・質感のすべてでクラスを超えて、史上最高のルーテシアになったのは、そんな理由もあるのです。
(文=佐野弘宗/写真=峰 昌宏、ルノー、webCG/編集=堀田剛資)

佐野 弘宗
自動車ライター。自動車専門誌の編集を経て独立。新型車の試乗はもちろん、自動車エンジニアや商品企画担当者への取材経験の豊富さにも定評がある。国内外を問わず多様なジャンルのクルマに精通するが、個人的な嗜好は完全にフランス車偏重。
-
第858回:レースの技術を市販車に! 日産が「オーラNISMO RSコンセプト」で見せた本気 2026.1.15 日産が「東京オートサロン2026」で発表した「オーラNISMO RSコンセプト」。このクルマはただのコンセプトカーではなく、実際のレースで得た技術を市販車にフィードバックするための“検証車”だった! 新しい挑戦に込めた気概を、NISMOの開発責任者が語る。
-
第857回:ドイツの自動車業界は大丈夫? エンジニア多田哲哉が、現地再訪で大いにショックを受けたこと 2026.1.14 かつてトヨタの技術者としてさまざまな車両を開発してきた多田哲哉さん。現役時代の思い出が詰まったドイツに再び足を運んでみると、そこには予想もしなかった変化が……。自動車先進国の今をリポートする。
-
第856回:「断トツ」の氷上性能が進化 冬の北海道でブリヂストンの最新スタッドレスタイヤ「ブリザックWZ-1」を試す 2025.12.19 2025年7月に登場したブリヂストンの「ブリザックWZ-1」は、降雪地域で圧倒的な支持を得てきた「VRX3」の後継となるプレミアムスタッドレスタイヤ。「エンライトン」と呼ばれる新たな設計基盤技術を用いて進化したその実力を確かめるべく、冬の北海道・旭川に飛んだ。
-
第855回:タフ&ラグジュアリーを体現 「ディフェンダー」が集う“非日常”の週末 2025.11.26 「ディフェンダー」のオーナーとファンが集う祭典「DESTINATION DEFENDER」。非日常的なオフロード走行体験や、オーナー同士の絆を深めるアクティビティーなど、ブランドの哲学「タフ&ラグジュアリー」を体現したイベントを報告する。
-
第854回:ハーレーダビッドソンでライディングを学べ! 「スキルライダートレーニング」体験記 2025.11.21 アメリカの名門バイクメーカー、ハーレーダビッドソンが、日本でライディングレッスンを開講! その体験取材を通し、ハーレーに特化したプログラムと少人数による講習のありがたみを実感した。これでアナタも、アメリカンクルーザーを自由自在に操れる!?
-
![ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】]() NEW
NEW
ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】
2026.1.19試乗記ベントレーのラグジュアリークーペ「コンチネンタルGT」のなかでも、ウェルビーイングにこだわったという「アズール」に試乗。控えめ(?)な680PSのハイブリッドがかなえる走りは、快適で満ち足りていて、ラグジュアリーカーの本分を感じさせるものだった。 -
![第327回:髪もクルマもナイスファイト!]() NEW
NEW
第327回:髪もクルマもナイスファイト!
2026.1.19カーマニア人間国宝への道清水草一の話題の連載。日産の新型「ルークス」で夜の首都高に出撃した。しっかりしたシャシーとターボエンジンのパワフルな走りに感心していると、前方にスーパーカーの姿を発見。今夜の獲物は「フェラーリ・ローマ」だ! -
![日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!]() NEW
NEW
日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!
2026.1.19デイリーコラムアメリカからの外圧による制度変更で、北米生産モデルの国内導入を決めたトヨタ。同様に、今後日本での販売が期待できる「海外生産の日本車」には、どんなものがあるだろうか? 清水草一が検証してみた。 -
![フェラーリ12チリンドリ(後編)]()
フェラーリ12チリンドリ(後編)
2026.1.18思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「フェラーリ12チリンドリ」に試乗。前編では伝家の宝刀であるV12エンジンを絶賛した山野。後編ではコンビを組むシャシーの印象を余すところなく聞いてみた。 -
![BYDシールAWD(4WD)【試乗記】]()
BYDシールAWD(4WD)【試乗記】
2026.1.17試乗記BYDのBEVサルーン「シール」の機能アップデートモデルが登場。強化のポイント自体はそれほど多くないが、4WDモデルの「シールAWD」は新たに電子制御式の可変ダンパーを装備したというから見逃せない。さまざまなシーンでの乗り心地をチェックした。 -
![新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る]()
新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る
2026.1.16デイリーコラム英国のモーターサイクル史にあまたの逸話を残してきた名門、ノートンが、いよいよ再始動! その数奇な歴史を振り返るとともに、ミラノで発表された4台の次世代モデルを通して、彼らが思い描く未来像に迫った。