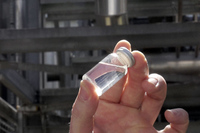大容量バッテリーすなわち正義ではない 短距離EVに見る“地球に優しいクルマ”の在り方とは?
2020.10.19 デイリーコラム航続距離の短いEVに抱く疑問
いささか旧聞に属するのだが、今年(2020年)8月末に栃木の本田技術研究所で「ホンダe」に関する記者説明会に出席した。そこで実車をじっくりと見て、短時間ではあるが走らせて、開発者の話を聞き、これまでホンダeについて疑問に思っていたいくつかのことが氷解した。
一番の疑問は、何といっても電池容量が35.5kWhと小さいため、欧州WLTPモードで220km(国内WLTCモードでは283km)と航続距離が短いことだろう。かの地では、同じ3万ユーロ程度の価格で独フォルクスワーゲン初のEV(電気自動車)専用車「ID.3」のベーシックモデルが買える。こちらの航続距離は欧州WLTPモードで330kmと、ホンダeの1.5倍もあるのだ。これについて、ホンダの開発者の回答は次のようなものだった。
現行のEVは、航続距離と充電時間(エンジン車は給油時間)という点で、エンジン車にはかなわない。無理に張り合おうとして電池を大量に積めば、重く、高価なクルマになってしまう。だからエンジン車と同じ土俵で競争するのはやめて、都市内を移動するのに最適なコミューターを追求した――。
言葉は違っていたかもしれないが、少なくとも筆者はそのように解釈した。
開発者の考え方はよく分かるし、ちょっと懐かしい感じのするデザインや、軽自動車よりも小回りの利く運転感覚などに非常に好感を抱いたのだが、航続距離が国内WLTCモードで283kmということは、実用航続距離は200kmを切るだろう。そうするとファーストカーとしては厳しいし、セカンドカーとしては451万~495万円という価格は高いよなあ、というありきたりな感想になってしまう。
生産段階におけるEVの環境負荷を考える
そう思っていたら、10月8日にはマツダが「MX-30」の国内発売を発表した。残念ながら国内ではマイルドハイブリッドの「e-SKYACTIV G」を積む仕様が先行し、注目のEV仕様の発売は2021年1月にずれこむ。しかし、EV仕様しかない欧州では9月からすでにデリバリーが始まっており、10月初旬の時点で5000台以上の受注を得ているという。
こちらもバッテリー容量は35.5kWhと、くしくもホンダeと同じで、航続距離は車体が大きいぶん少し短く、欧州WLTPモードで約200kmだ。マツダがMX-30でバッテリー容量を抑えた理由として挙げたのがLCA(ライフサイクルアセスメント)だ。つまりクルマの使用段階だけでなく、製造段階から廃棄の段階までトータルで考えた場合のCO2排出量削減を考えた結果だという。バッテリーは製造段階で大量のエネルギーを消費するため、車両製造段階でのCO2の排出量はエンジン車の2倍以上になるというのがマツダの試算結果だ。
ではそのぶんのCO2は、どのくらい走行すれば相殺されるのか。マツダの試算では、MX-30のEV仕様を同等性能のディーゼルエンジン車と比較すると、16万km走行した段階で、両車のCO2排出量はほぼ同等になるという。もしMX-30よりも大きなバッテリーを積めば、そのぶん製造段階でのCO2排出量が増え、16万km以上走らないとEVのトータルCO2排出量はディーゼル車より少なくならないということになる。それって本当だろうか? そもそも発電時に排出されるCO2は国によって異なるので、地域による違いもあるはずだ。そう思い、あらためて根拠となる論文『Estimation of CO2 Emissions of Internal Combustion Engine Vehicle and Battery Electric Vehicle Using LCA』を見てみると、各国におけるEVとエンジン車のCO2排出量が試算されていた。
国や市場によって異なるEV導入の効果
まず、この論文では16万kmでバッテリーを交換することを想定しているので、そこでトータルCO2排出量が増加してしまう。ただしバッテリー交換を前提にしなくても、EVのトータルCO2排出量は意外と多いのだ。例えば欧州の場合、約11万km走行してようやくディーゼル車とEVのトータルCO2がほぼ等しくなるし、日本でも11万5000km走らないと両者は等しくならない。
発電時のCO2発生量の多い中国では、ディーゼル車より燃費の悪いガソリン車とEVの比較でも、両者のトータルCO2排出量が等しくなるのは約12万km走行した後である。ただし、クルマの平均燃費が低く、ディーゼル乗用車がほとんどない米国では、約6.1万kmの走行でEVとガソリン車のトータルCO2が等しくなる。つまりEV導入の効果が一番大きいのは米国ということになる。
逆に日本は、ハイブリッド車が普及していることや軽自動車が多いなどの理由でガソリン車の平均燃費がよいから、対ガソリン車であってもディーゼル車とほぼ同等の11.5万km走らないと、EVの優位性が出てこない。こうして見てくると、マツダの試算を前提にする限り、現在の発電事情ではEVは必ずしもエコとは言い切れないし、ましてやMX-30やホンダeよりも多くのバッテリーを積んでいるEVは、相当な距離を走らないとエンジン車に対する優位性が出てこないだろう。
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
デンキ以外の次世代環境技術にも目を向けるべき
米国のテスラや、欧州の高級ブランドでは、MX-30やホンダeの2倍以上のバッテリーを積む高級EVを商品化している。それらは一見エコのようだが、バッテリー製造時のCO2排出量を考えると、単純にエコとは言い切れない代物ということになる。もちろん、それは比較の問題で、かつての大排気量V12エンジンを積んだ高級車に比べればエコなのかもしれない。しかし少なくとも「CO2排出量ゼロでクリーン」というイメージは改めたほうがいい。
ホンダは2050年にカーボンニュートラルを目指すという新しい方針を掲げた。その過程で、いずれはエンジンはその役割を終えることになるだろう。しかしクルマのEV化によるカーボンニュートラルは、“カーボンニュートラルな発電の実現”を前提としている。それまでの過程においては、トータルCO2という観点で見れば、ハイブリッド車やディーゼル車もEVにそれほど劣るものではない。そもそもEVが高価格で普及しなければ、CO2の削減にもつながらない。
じゃあ、どうすればいいんだということになるが、筆者が期待しているのは燃料のカーボンニュートラル化である。これはe-Fuelとして独アウディが研究しており、最近では日本の完成車メーカーも研究を始めている。要は太陽光発電などの電力で燃料を合成しようというものだ。これならいまのエンジン車の利便性を手放すことなくカーボンフリー化できる。現在は化石燃料に比べてずっとコストが高いので実用的ではないのだが、太陽光発電の低コスト化が急ピッチで進む現在、あながち夢物語とも言い切れない。近い未来、高級車は高価な燃料を使うエンジン車、われわれ一般庶民はEV……などという時代がくるのかもしれない。
(文=鶴原吉郎<オートインサイト>/写真=神村 聖、アウディ、フォルクスワーゲン、Newspress、webCG/編集=堀田剛資)

鶴原 吉郎
オートインサイト代表/技術ジャーナリスト・編集者。自動車メーカーへの就職を目指して某私立大学工学部機械学科に入学したものの、尊敬する担当教授の「自動車メーカーなんかやめとけ」の一言であっさり方向を転換し、技術系出版社に入社。30年近く技術専門誌の記者として経験を積んで独立。現在はフリーの技術ジャーナリストとして活動している。クルマのミライに思いをはせつつも、好きなのは「フィアット126」「フィアット・パンダ(初代)」「メッサーシュミットKR200」「BMWイセッタ」「スバル360」「マツダR360クーペ」など、もっぱら古い小さなクルマ。
-
待望の7人乗りMPV「ルノー・グランカングー」を大解剖 ライバルにはない魅力はあるか?NEW 2026.1.30 いよいよ日本に導入された、ロングボディー・3列シートの「ルノー・グランカングー」。満を持して登場した真打ちは、競合する国産ミニバンや7人乗りの輸入MPVに対し、どのような特徴があり、どんな人におススメなのか? 取材会で実車に触れた印象を報告する。
-
「スバルPerformance-B STIコンセプト」の市販化はズバリ2027年!? 2026.1.29 スバルが「東京オートサロン2026」でスーパー耐久シリーズ2026の参戦車両を発表。そのプロフィールは「スバルPerformance-B STIコンセプト」そのものだ。同モデルの市販化はあるのか。スバリストが願望を込めつつ予想する。
-
クワッドモーター搭載で過去にないパフォーマンス BMWが示したBEV版「M3」の青写真 2026.1.28 BMW Mが近い将来に市場投入を図る初のピュア電気自動車の骨子を発表した。車種は明かされていないものの、「BMW Mノイエクラッセ」と呼ばれており、同時に公開された写真が小型セダンであることから、おそらく次期型「M3」と思われる。その技術的特徴を紹介する。
-
春は反則金祭り!? 2026年4月に始まる「自転車の青切符導入」を考える 2026.1.26 2026年4月から、自転車を対象とした交通反則通告制度(青切符)が導入され、違反者には反則金が科されるようになる。なぜこうした事態になったのか、実情について自動車ライターの工藤貴宏が語る。
-
「K-OPEN」や競技用「ミラ イース」の開発者を直撃! 東京オートサロンで感じたダイハツの心意気 2026.1.23 「東京オートサロン2026」に、ターボエンジン+5段MTの「ミラ イース」や「K-OPEN」のプロトタイプを出展したダイハツ。両車の開発者が語った開発秘話や市販化の狙いとは? 「走る楽しさをみんなのものに」に本気で取り組む、ダイハツの心意気に触れた。
-
![待望の7人乗りMPV「ルノー・グランカングー」を大解剖 ライバルにはない魅力はあるか?]() NEW
NEW
待望の7人乗りMPV「ルノー・グランカングー」を大解剖 ライバルにはない魅力はあるか?
2026.1.30デイリーコラムいよいよ日本に導入された、ロングボディー・3列シートの「ルノー・グランカングー」。満を持して登場した真打ちは、競合する国産ミニバンや7人乗りの輸入MPVに対し、どのような特徴があり、どんな人におススメなのか? 取材会で実車に触れた印象を報告する。 -
![第946回:欧州に「277万円以下」のクルマなし! キューバ化を覚悟した冬]()
第946回:欧州に「277万円以下」のクルマなし! キューバ化を覚悟した冬
2026.1.29マッキナ あらモーダ!欧州でお値段1万5000ユーロ未満の大衆車が壊滅状態に! 自動車の価格高騰はなぜ起き、そしていつまで続くのか? 一般の自動車ユーザーは、この嵐をいかにしてやり過ごそうとしているのか? イタリア在住の大矢アキオがリポートする。 -
![第286回:才人監督が描くディストピアのデスゲーム 『ランニング・マン』]()
第286回:才人監督が描くディストピアのデスゲーム 『ランニング・マン』
2026.1.29読んでますカー、観てますカー「アルピーヌA290」で追っ手のハンターから逃げ延びろ! スティーブン・キングが50年前に予見した未来は、まさに現在の状況そのもの。分断とフェイクが支配する現実を鋭くえぐった最新型デスゲーム映画。 -
![「スバルPerformance-B STIコンセプト」の市販化はズバリ2027年⁉]()
「スバルPerformance-B STIコンセプト」の市販化はズバリ2027年⁉
2026.1.29デイリーコラムスバルが「東京オートサロン2026」でスーパー耐久シリーズ2026の参戦車両を発表。そのプロフィールは「スバルPerformance-B STIコンセプト」そのものだ。同モデルの市販化はあるのか。スバリストが願望を込めつつ予想する。 -
![スズキ・ワゴンR ZL(FF/5MT)【試乗記】]()
スズキ・ワゴンR ZL(FF/5MT)【試乗記】
2026.1.28試乗記スズキの「ワゴンR」がマイナーチェンジ。デザインを変更しただけでなく、予防安全装備もアップデート。工場設備を刷新してドライバビリティーまで強化しているというから見逃せない。今や希少な5段MTモデルを試す。 -
![クワッドモーター搭載で過去にないパフォーマンス BMWが示したBEV版「M3」の青写真]()
クワッドモーター搭載で過去にないパフォーマンス BMWが示したBEV版「M3」の青写真
2026.1.28デイリーコラムBMW Mが近い将来に市場投入を図る初のピュア電気自動車の骨子を発表した。車種は明かされていないものの、「BMW Mノイエクラッセ」と呼ばれており、同時に公開された写真が小型セダンであることから、おそらく次期型「M3」と思われる。その技術的特徴を紹介する。