第45回:『トリノの風薫る』プリンス・スカイラインスポーツ(1962-63)(その4)
2006.09.13 これっきりですカー第45回:『トリノの風薫る』プリンス・スカイラインスポーツ(1962-63)(その4)
 拡大 拡大
|
 拡大 拡大
|
 拡大 拡大
|
■2年弱で60台
1960 年11月のトリノショーでワールドプレミアを果たしたクーペとコンバーチブル、2台のアレマーノ製プロトタイプは、翌61年に日本に上陸。3月に報道関係者向けのお披露目を済ませた後、翌4月には東京・千駄ケ谷の東京体育館で大がかりなショー仕立ての発表会を実施、一般公開された。
プロトタイプと同時にボディの木型も到着し、さらに7月にはイタリアでの約2年間におよぶデザイン・スタディを終えた井上猛氏が4人のベテラン板金職人を伴って帰国。彼らによって本場イタリアの板金技術が伝授され、その年秋の第8回全日本自動車ショーにプリンスで製作されたクーペとコンバーチブルが出展された。
ちなみにこの年のショーでは、前年までとは打って変わって各社一斉にスポーツ指向およびイタリア風デザインのモデルを出展して話題となった。が、それらは図らずも本場仕込みのスカイラインスポーツの美しさ、完成度の高さを実証する役回りを演じることとなってしまったのだった。
トリノでのデビューから約1年半後の62年4月、スカイラインスポーツはクーペ185万円、コンバーチブル195万円という高価格でついに発売された。
といわれてもピンとこないかもしれないが、当時もっとも高価だった国産乗用車、それはベースとなったグロリアなのだが、それですら115万円だったといえば、その突出ぶりが少しは伝わるだろうか。現在の貨幣価値に換算するのは難しいが、今日の国産最高級セダンであるセルシオやシーマの上級グレードが700万円以上であることを考えると、1000万円を超えることは間違いないと思う。
 拡大 拡大
|
 拡大 拡大
|
シャシーは流用とはいうものの、ボディは手叩きによるハンドメイド、内外装の艤装類もほとんどすべてが専用品、シートは本革張りという内容からすればその高価格も致し方なかったのだろう。
しかしその高コストがネックとなって、当初予定していたといわれる限定250台には遠く及ばず、約60台がつくられたのみで翌63年には生産中止されてしまった。「約60台」というのは、総生産台数60台という説と58台という説があるからだが、いずれにしてもコンバーチブルはうち25台と伝えられている。「プリンス」のブランドイメージ向上には大いに貢献したスカイラインスポーツだが、この生産台数では明らかに商業的には失敗だったはずである。
60 年代における日本の自動車技術の進化は、世界に追い付き追い越せとばかり、まさに日進月歩の勢いだった。技術面におけるリーダー的存在だったプリンスでいえば、スカイラインスポーツ発売から半年を経た62年10月にはベースカーだったグロリアがフルモデルチェンジされて新世代となり、翌63年6月にはそのグロリアに国産初の直6SOHCエンジンを積んだ高性能版の「スーパー6」が加わっていた。
その結果、わずか1年前に市販化されたばかりのスカイラインスポーツが急速に旧態化してしまった感は否めず、コスト高に加えてこれまた短命に終わった理由のひとつに数えることができるだろう。
 拡大 拡大
|
 拡大 拡大
|
 拡大 拡大
|
■一大トレンドの火付け役
63年には日本初の本格的なレースである第1回日本グランプリが鈴鹿サーキットで開かれ、プリンスからもスカイラインおよびスカイラインスポーツが参戦した。しかしレギュレーションを遵守してほとんどノーマル状態でエントリーしたため、いずれも惨敗を喫してしまった。その雪辱を果たすため、翌64年には「スカイラインGT」、さらに65年には国産初のプロトタイプスポーツである「R380」を開発するなど、プリンスは急速にスポーツづいていく。
そのいっぽうで、スカイラインスポーツで学んだイタリアン・デザインのモデルが開発されるようなことは、残念ながらなかった。だが、前述したようなプロトタイプスポーツ、あるいは御料車であるロイヤルのボディ製作などにカロッツェリア直伝のテクニックが活かされたであろうことは、まず間違いないであろう。
だがイタリアン・デザイン導入のパイオニアだったスカイラインスポーツは、プリンス社内よりむしろ国産他社に与えた影響のほうが大きかった。
スカイラインスポーツの登場後、プリンスとミケロッティのコラボレーションに続けとばかり、日産はピニンファリーナ(2代目ブルーバード/同セドリック)、ダイハツはヴィニャーレ(コンパーノ)、日野はミケロッティ(コンテッサ1300)、マツダはベルトーネ(初代ルーチェ)、いすゞはギア(117クーペ/フローリアン)の門戸を叩き、デザインを依頼。60年代を通じて「トリノ詣で」が日本のカーデザインにおける一大トレンドとなり、それは日本車史を語る上でけっして外せないターニングポイントとなった。
生産台数わずか60台に過ぎず、後継車種も現れなかった、スカイライン史上における異端児ともいえるスカイラインスポーツだが、こう考えると後世に残したものはけっして小さくない。言うなれば日本車のデザイン史におけるエポックメイキングな存在であり、つまりは偉大なる「これっきりですカー」だったといえるのではないだろうか。
なお、現存するスカイラインスポーツの数は定かではないが、筆者の知るだけでも10台以上は残っている。生産台数に対する残存率からみれば、日本車としてはかなり高く、その数字にも規格外のスペシャルな高級車だったことが現れている。(おわり)
(文=田沼 哲/2005年11月)
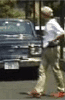
田沼 哲
NAVI(エンスー新聞)でもお馴染みの自動車風俗ライター(エッチな風俗ではない)。 クルマのみならず、昭和30~40年代の映画、音楽にも詳しい。
-
第53回:「これっきりモデル」in カローラ・ヒストリー〜その4「謎のスプリンター」〜 2006.11.23 トヨタ・スプリンター1200デラックス/1400ハイデラックス(1970-71)■カローラからの独立1970年5月、カローラが初めて迎えたフルモデルチェンジに際して、68年に初代カローラのクーペ版「カローラ・スプリンター」として登場したスプリンターは、新たに「トヨタ・スプリンター」の名を与えられてカローラ・シリーズから独立。同時にカローラ・シリーズにはボディを共有する「カローラ・クーペ」が誕生した。基本的に同じボディとはいえ、カローラ・セダンとほとんど同じおとなしい顔つきのカローラ・クーペに対して、独自のグリルを持つスプリンターは、よりスポーティで若者向けのムードを放っていた。バリエーションは、「カローラ・クーペ」「スプリンター」ともに高性能版の「1200SL」とおとなしい「1200デラックス」の2グレード。エンジンは初代から受け継いだ直4OHV1166ccで、「SL」にはツインキャブを備えて最高出力77ps/6000rpmを発生する3K-B型を搭載。「デラックス」用のシングルキャブユニットはカローラとスプリンターで若干チューンが異なり、カローラ版は68ps/6000rpm(3K型)だが、スプリンター版は圧縮比が高められており73ps/6600rpm(3K-D型)を発生した。また、前輪ブレーキも双方の「SL」と「スプリンター・デラックス」にはディスクが与えられるのに対して、「カローラ・クーペ・デラックス」ではドラムとなっていた。つまり外観同様、中身も「スプリンター」のほうがよりスポーティな味付けとなっていたのである。しかしながら、どういうわけだか「スプリンター1200デラックス」に限って、そのインパネには当時としても時代遅れで地味な印象の、角形(横長)のスピードメーターが鎮座していたのだ。
-
第52回:「これっきりモデル」in カローラ・ヒストリー〜その3「唯一のハードトップ・レビン」〜 2006.11.15 トヨタ・カローラ・ハードトップ1600レビン(1974-75)■レビンとトレノが別ボディに1974年4月、カローラ/スプリンターはフルモデルチェンジして3代目となった。ボディは2代目よりひとまわり大きくなり、カローラには2/4ドアセダンと2ドアハードトップ、スプリンターには4ドアセダンと2ドアクーペが用意されていた。このうち4ドアセダンは従来どおり、カローラ、スプリンターともに基本的なボディは共通で、グリルやリアエンドなどの意匠を変えて両車の差別化を図っていた。だが「レビン」や「トレノ」を擁する2ドアクーペモデルには、新たに両ブランドで異なるボディが採用されたのである。カローラはセンターピラーのない2ドアハードトップクーペ、スプリンターはピラー付きの2ドアクーペだったのだが、単にピラーの有無ということではなくまったく別のボディであり、インパネなど内装のデザインも異なっていた。しかしシャシーはまったく共通で、「レビン」(型式名TE37)および「トレノ」(同TE47)についていえば、直4DOHC1.6リッターの2T-G/2T-GR(レギュラー仕様)型エンジンはじめパワートレインは先代から踏襲していた。ボディが大型化したこと、および双方とも先代ほど簡素でなくなったこともあって車重はレビン930kg、トレノ925kgと先代より60〜70kg前後重くなった。
-
第51回:「これっきりモデル」in カローラ・ヒストリー〜その2「狼の皮を被った羊(後編)」〜 2006.11.10 トヨタ・カローラ・レビンJ1600/スプリンター・トレノJ1600(1973-74)■違いはエンブレムのみ1972年3月のレビン/トレノのデビューから半年に満たない同年8月、それらを含めたカローラ/スプリンターシリーズはマイナーチェンジを受けた。さらに翌73年4月にも小規模な変更が施されたが、この際にそれまで同シリーズには存在しなかった、最高出力105ps/6000rpm、最大トルク14.0kgm/4200rpmを発生する直4OHV1.6リッターツインキャブの2T-B型エンジンを積んだモデルが3車種追加された。うち2車種は「1600SL」と「1600SR」で、これらはグレード名から想像されるとおり既存の「1400SL」「1400SR」のエンジン拡大版である。残り1車種には「レビンJ1600/トレノJ1600」という名称が付けられていたが、これらは「レビン/トレノ」のボディに、DOHCの2T-Gに代えてOHVの2T-B型エンジンを搭載したモデルだった。なお、「レビンJ1600/トレノJ1600」の「J」は「Junior(ジュニア)」の略ではないか言われているが、公式には明らかにされていない。トランクリッド上の「Levin」または「Trueno」のエンブレムに追加された「J」の文字を除いては、外から眺めた限りでは「レビン/トレノ」とまったく変わらない「レビンJ/トレノJ」。だがカタログを眺めていくと、エンジンとエンブレムのほかにも「レビン/トレノ」との違いが2点見つかった。
-
第50回:「これっきりモデル」in カローラ・ヒストリー〜その1「狼の皮を被った羊(前編)」〜 2006.11.6 誕生40周年を迎えた2006年10月に、10代目に進化したトヨタ・カローラ。それを記念した特別編として、今回は往年のカローラおよびその兄弟車だったスプリンター・シリーズに存在した「これっきりモデル」について紹介しよう。かなりマニアックな、「重箱の隅」的な話題と思われるので、読まれる際は覚悟のほどを……。トヨタ・カローラ・レビンJ1600/スプリンター・トレノJ1600(1973-74)■スパルタンな走りのモデル型式名TE27から、通称「27(ニイナナ)レビン/トレノ」と呼ばれる、初代「カローラ・レビン1600/スプリンター・トレノ1600」。英語で稲妻を意味する「LEVIN」、いっぽう「TRUENO」はスペイン語で雷鳴と、パンチの効いた車名を冠した両車は、2代目カローラ/スプリンター・クーペのコンパクトなボディに、セリカ/カリーナ1600GT用の1.6リッターDOHCエンジンをブチ込み、オーバーフェンダーで武装した硬派のモデルとして、1972年の登場から30余年を経た今なお、愛好家の熱い支持を受けている。「日本の絶版名車」のような企画に必ずといっていいほど登場する「27レビン/トレノ」のベースとなったのは、それらが誕生する以前のカローラ/スプリンターシリーズの最強モデルだった「クーペ1400SR」。SRとは「スポーツ&ラリー」の略で、カローラ/スプリンター・クーペのボディに、ツインキャブを装着して最高出力95ps/6000rpm、最大トルク12.3kgm/4000rpmを発生する直4OHV1407ccエンジンを搭載したスポーティグレードだった。ちなみにカローラ/スプリンター・クーペには、1400SRと同じエンジンを搭載した「1400SL」というモデルも存在していた。「SL」は「スポーツ&ラクシュリー」の略なのだが、このSLに比べるとSRは装備が簡素で、より硬い足まわりを持った、スパルタンな走り重視のモデルだったのである。
-
第49回:『唯一無二』日野コンマース(1960-62)(その4) 2006.9.13 新しいコンセプトのトランスポーターとして、1960年2月に発売された日野コンマース。だがそのセールスははかばかしくなかった。
-
![右も左もスライドドアばかり ヒンジドアの軽自動車ならではのメリットはあるのか?]() NEW
NEW
右も左もスライドドアばかり ヒンジドアの軽自動車ならではのメリットはあるのか?
2026.2.25デイリーコラム軽自動車の売れ筋が「ホンダN-BOX」のようなスーパーハイトワゴンであるのはご承知のとおりだが、かつての主流だった「スズキ・ワゴンR」のような車型に復権の余地はないか。ヒンジドアのメリットなど、(やや強引ながら)優れている点を探ってみた。 -
![第950回:小林彰太郎氏の霊言アゲイン あの世から業界を憂う]() NEW
NEW
第950回:小林彰太郎氏の霊言アゲイン あの世から業界を憂う
2026.2.25マッキナ あらモーダ!かつて『SUPER CG』の編集者だった大矢アキオが、『CAR GRAPHIC』初代編集長である小林彰太郎との交霊に挑戦! 日本の自動車ジャーナリズムの草分けでもある天国の上司に、昨今の日本の、世界の自動車業界事情を報告する。 -
![ルノー・グランカングー クルール(FF/7AT)【試乗記】]() NEW
NEW
ルノー・グランカングー クルール(FF/7AT)【試乗記】
2026.2.25試乗記「ルノー・グランカングー」がついに日本上陸。長さ5m近くに達するロングボディーには3列目シートが追加され、7人乗車が可能に。さらに2・3列目のシートは1脚ずつ取り外しができるなど、極めて使いでのあるMPVだ。ドライブとシートアレンジをじっくり楽しんでみた。 -
![第862回:北極圏の氷上コースでマクラーレンの走りを堪能 「Pure McLaren Arctic Experience」に参加して]() NEW
NEW
第862回:北極圏の氷上コースでマクラーレンの走りを堪能 「Pure McLaren Arctic Experience」に参加して
2026.2.25エディターから一言マクラーレンがフィンランド北部で「Pure McLaren Arctic Experience」を開催。ほかでは得られない、北極圏のドライビングエクスペリエンスならではの特別な体験とは? 氷上の広大な特設コースで、スーパースポーツ「アルトゥーラ」の秘めた実力に触れた。 -
![ボルボEX30クロスカントリー ウルトラ ツインモーター パフォーマンス(4WD)【試乗記】]()
ボルボEX30クロスカントリー ウルトラ ツインモーター パフォーマンス(4WD)【試乗記】
2026.2.24試乗記ボルボの電気自動車「EX30クロスカントリー」に冬の新潟・妙高高原で試乗。アウトドアテイストが盛り込まれたエクステリアデザインとツインモーターからなる四輪駆動パワートレイン、そして引き上げられた車高が織りなす走りを報告する。 -
![エンジニアが「車検・点検時に注意すべき」と思う点は?]()
エンジニアが「車検・点検時に注意すべき」と思う点は?
2026.2.24あの多田哲哉のクルマQ&Aすっかりディーラー任せにしている車検・点検について、ユーザーが自ら意識し、注視しておくべきチェックポイントはあるだろうか? 長年トヨタで車両開発を取りまとめてきた多田哲哉さんに意見を聞いた。
















