第28回:しらふで語る昔話ほど痛々しいものはない
2018.10.13 バイパーほったの ヘビの毒にやられまして 拡大 拡大 |
ネタに困ったときは“自分語り”で乗り切るに限る! もろもろのトラブルを乗り越え、ついに平穏な日々(?)を勝ち取ったwebCGほったと「ダッジ・バイパー」だが、おかげで連載のネタが枯渇……。とりあえずお茶を濁すため、ぺーぺー編集がバイパー購入に至るおのが半生(黒歴史)を振り返る。
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
快調なのも困りもの
ステアリングの“右流れ”が解消して以来、わが家のバイパーはすこぶる快調である(エアコン除く)。持ち主に「四季報かよ」と悪態をつかせた過去などどこ吹く風。走る・曲がる・止まる系のトラブルはもとからそんなになかったし、リモコンキーを含む電装系のあれこれも従順……とは言わないまでも、皆そこそこに素直である。過日のバッテリートラブルは、まあバイパーの責任ではないのでノーカンでしょう。
ちなみに、ラゲッジルームの雨漏りについては、最近は気にしないで出かけるようにしている。使わなくなった手ぬぐい類を突っ込んでおけばどうにかなるし、雨の日用のクルマを別途所有できるほど、わが家にゆとりはないのだ。
そんなわけで、ここ最近は武蔵野にて平穏な日々を送っている記者とバイパーだが、そうなると問題なのがこの連載。人生初の代休で行った伊豆・稲取ツアーでは何も起こらず、楽しみにしていた秋のAUTO-Xも台風24号で延期。故障もねえ。イベントもねえ。日常ネタもそんなにねえ。気分は吉 幾三だ。
編集部で日々数字とにらめっこしている企画チームの折戸などは、「稲取でキンメダイ食った話でもして、お茶濁しとけばどうすか?」などと軽く言うが、男一人で天城越えとか、書く方も読む方もイタいだけだろう。だいたいアンタ、それ読みたいか?
仕方ないので過去の記録メモ……走行履歴や燃費、諸経費などをテキトーにまとめたWordやExcel……などを掘り返して眺めていたら、なにやらバイパー購入までの回顧録のような文書が現れた。なんでこんなもんが? と首をかしげたが、すぐに思い当たった。モータージャーナリストの清水草一氏が、記者を取材するとかしないとか言っていたのだった。
幻と消えた“ヤケド必至”の企画
『webCG』のなかでも、こんな辺ぴなエッセイまで読まれている皆さまならご存じだろうが、清水氏は当サイトにて、人気連載「カーマニア人間国宝への道」を続けている。過日めでたく100回を迎え、小休止を経て連載を再開した同エッセイだが、実は幻の回があるのだ。
内容は、「モテないカーマニア選手権」の絶対王者であるワタクシの過去を掘り返すというヤケド必至のシロモノで、実施直前に「いや、ウチそういうお店じゃないんで」という編集長こんどーの冷静なひと言により立ち消えとなった。で、なんで前頁のようなメモが残されていたかというと、真面目なことに、インタビューに備えて自分が用意していたのだ。
天城越えと回顧録、どっちの方が需要がないか。食用に適さないのはどちらも同じだが、まだ後者の方が料理のしようがある(気がする)ので、今回はそれをお題とさせていただく。読者諸兄姉の皆さま、お覚悟あれ。
さてさて。先日バイパーのバッテリーをあげたJ氏を筆頭に、最近、旧友と顔を合わせる機会の多い記者なのだが、そのたびに口にされるのが、「おのれ、そんなクルマ好きだったっけ?」という問いである。正直に言うと、そんなに興味なかった。そもそもわれらの学生時代には、自動車趣味なんてモノはすでに下火。周囲にクルマの話をする者など一人もいなかったのだ。唯一話題に上がっていたコンテンツといえばシミュレーションゲーム『グランツーリスモ』くらいのものだが、VR元年と称される2018年においてなお、現世(うつしよ)に引きこもる記者のこと。当然ながら、当時も食指は動かなかった。
それじゃあなににかまけていたのかというと、当時の自分は航空機、それも戦間期から戦中にかけてのレシプロ機にとにかく執心だった。
カッコイイとはどういうことよ?
皆さんは『紅の豚』という映画をご存じだろうか? かの宮崎 駿が今なお「あんな自己満映画つくるんじゃなかった」と嘆く、1992年封切りの傑作である。作中で描かれた登場人物のカッコよさに、飛行艇と航空機用エンジンの存在感に、ガキンチョだった記者はすっかりハマった。主人公と赤いサボイアとの、マンマユート団とダボハゼ号との一筋縄ではいかない関係性に心打たれ、将来自分もあんなものを傍に置きたいと思った。
しかしである。ここ日本において、このテの飛行機は模型を愛(め)でる以外に楽しみようのないシロモノだ。桁外れの金持ちでもなければ個人所有はできないし、よしんば持てたとしても、気の向いた時に気軽に飛ばすことも、自宅のガレージでながめることもできない。映画では自由のメタファーとして使い古された飛行機だが、実は相当に自由から縁遠い乗り物だったのだ。そしてそもそも、記者は高所恐怖症だった。
そんなわけで、レシプロ機に対する憧憬(しょうけい)はおいといて、自由の体現と行き場のない物欲をどうにかできるアテはないかとウロウロしていた折、「そういえば」と思い当たったのが、そこいらを走り回るクルマとバイクだった。
かように変則的なルートでこのかいわいに足を踏み入れた記者である。しかも実家のマイカーは、タウンエース→ブルーバード→ローレル→ウイングロードという節操のなさ。ジドーシャの審美眼なんぞ育まれようはずもなく、また知識もスッカラカンだった。最初に手に入れたのは1995年式の「ローバー・ミニ」だが、それとて当時の職場の上司が、「これで売れなきゃ廃車にする」とヤフオクに出していたものをはかなんで引き受けただけだ。それでも初マイカーがミニというのはなかなかにいい着地点で、記者は悪趣味にカスタムされたインジェクションの個体を、10年にわたり持ち続けた。
中古車物件サイトで存在を知る
その間、「バイクだともう少し安く遊べるかも」と思った記者は普通&大型二輪の免許を取得。「BSA A65サンダーボルト」(1968年)のボバーカスタムをヤフオクでゲットして大ヤケドしたり、「よりによってその年式のその車種かよ」(詳しくはキャプションで)な1998年式「トライアンフ・サンダーバードスポーツ」を手に入れて一人悦に浸ったりしていた。
……ここまで読んできた読者諸兄姉の中には、「いや、いつになったらバイパー出てくるのよ?」と思われた方もおられるでしょう。ご安心ください。私もそう思ってました。
そもそも、記者がバイパーなんてどマイナーなクルマの存在を知ったのは、まだ某輸入中古車メディアで“でっち”をしていたころである。同メディアの物件サイトにて、排気量の大きい順で物件をソートしたら、「セブン」や「スープラ」の親玉みたいなのがどーんと上位を占めていたのだ。ちなみに先述のゲーム『グランツーリスモ』だと、結構な人気車種というか重要なポジションでバイパーが出てくるのだとか(伝聞)。そんなわけで、実を言うとワタクシなぞより同世代のゲーマーの方が、バイパーの事を先に知っていて、かつ詳しかったりした。
いずれにせよ、当時は「さっすがアメリカ。2シーターで8リッターV10とか、おばかなクルマがあったもんだな」としか思わなかった。すでにミニを入手しており、「他のクルマを買う」なんて考えの入り込む余地が頭にもサイフにもなかったからだ。気になりだしたのは10年後で、要するにミニがいよいよどうしようもなくなった時。「次のクルマどうすんべ」と考えていた頭の隅に、先述の“おばかなクルマ”が引っかかったのである。
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
立ちはだかる「ローバー・ミニ」の壁
クルマ好きなら大抵そうだと思うのだが、この時、記者はさまざまな車種を候補に挙げては、現実→理想のライン上にプロットし、“具体的な検討”(すなわち妄想)を膨らませていた。車種としては、現実路線の筆頭がJA11型「スズキ・ジムニー」と先代「スズキ・エスクード」、そして理想と現実の折衷案として、60系の「トヨタ・ランドクルーザー」や最終の「いすゞ・ビッグホーン」「ポルシェ944ターボ」などがあり、完全理想路線として「マーコス1600GT」「TVRビクセン」、そしてダッジ・バイパーがあった。ちなみに、永遠のあこがれは「シェルビー・コブラ デイトナクーペ」と、1969年式「フォード・マスタングBOSS 429」である。
このラインナップを開陳した時、編集部の大沢青年は「あんまりクルマにコダワリないんですね」(冷笑)と述べていたが、言っては悪いが考察が甘い。甘すぎ。赤福より甘え。実際、現実路線の2台ですら選択理由を挙げたら大辞林が埋まるほどである(詳しくは写真キャプションで)。ジャンルによって選択肢を狭めるのをよしとせず、また生産国やメーカーといった“ブランド”に興味がなかったというだけで、ここに挙げた車種はいずれも、記者にとって珠玉の名車だった。
などと言うと「だったらどれを選んでもよかったんだ。楽なクルマ選びだったね~」となりそうだが、そうは問屋が卸さない。どのクルマを俎上(そじょう)に上げ、それらがもたらすカーライフに思いをはせても、最後にはこんな言葉が頭をよぎったのである。
「確かに魅力的だけどさ、これならミニを直して乗り続けてても、一緒だったんじゃないの?」
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
アナタの、ワタシの『月の爆撃機』
結局のところ、かような妄想による取捨選択の果てに残ったのがバイパーだったのだと思う。ミニとはかけ離れているとか、かぶるところがないというよりは、走りも燃費もトラブルの類いも、こやつだけはおよそ想像がつかなかったのだ。
それにこの珍奇なクルマは、『紅の豚』で洗礼を受けた記者のココロにブッ刺さる要素を、山ほど抱えていた。長大なノーズにデカいエンジンをタテに押し込んだ姿は、まさに水冷のレシプロ機そのもの。手作り感あふれるボディーワーク(笑)も、日常生活に占める存在のわずらわしさも、ちょうど劇中に現れる飛行艇を思わせた。
だいたいね、自然吸気の8リッターV10ですよ奥さん。性急過ぎる世相を思うに、こんなクルマにわれら貧乏人が乗れる時代なんて、恐らく今が最後だ。ビビっている場合ではなかったのである。……まあ、このへんはちょっとこじつけではあるのだけど。
こうしてバイパーを選んだ理由を挙げ連ねてみると、つくづく記者にとってクルマというのは自己満足なのだわと思う。というか、いいクルマに乗ることがモテや尊敬といった現世御利益を伴わなくなった今日び、クルマにこだわる唯一の理由って、結局それなんじゃないの?
言ってみれば、ワタシにとっての、アナタにとっての『月の爆撃機』。……なんて臭い台詞でしめようと思ったら、企画チーム折戸に「意味分かんないっす」とつっ込まれた。マジで? 俺らの世代だと“ブルハ”は義務教育だぜ? JASRACに金払うのがイヤなので歌詞は載せませんが、気になった人はゼヒ検索してみてください。世知辛い世の中なんだし、一人ひとつぐらい、こういうモノを持っていたってバチはあたらないと思う。
(webCG ほった)
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
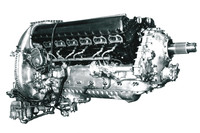 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |

堀田 剛資
猫とバイクと文庫本、そして東京多摩地区をこよなく愛するwebCG編集者。好きな言葉は反骨、嫌いな言葉は権威主義。今日もダッジとトライアンフで、奥多摩かいわいをお散歩する。
-
【番外編】バイパー、事故に遭う ―東京の片隅で垣間見た現代ニッポンの縮図― 2025.8.26 インバウンドでにぎわう令和の日本で、webCG編集部員と「ダッジ・バイパー」を襲ったささやかな悲劇とは? 「まさか自分が(笑)」なんて油断しているところに襲ってくるのが事故というもの。読者諸氏の皆さんも、運転には気をつけましょうね。
-
【番外編】バイパー、能登へ行く 2025.1.9 排気量8リッターのアメリカンマッスルカー「ダッジ・バイパー」で目指すは深秋の日本海。その旅程で記者が覚えた、AIやデンキに対する考えとは? 最後の目的地である能登半島の突端で思ったこととは? webCG編集部員が、時代遅れの怪物と中部・北陸を駆ける。
-
第47回:114万9019円の愉悦 2022.12.21 限りある石油資源をむさぼり、今日も生ガスをばらまいて走るwebCG編集部員の「ダッジ・バイパー」。今年に入り、ずっと不調だった毒ヘビが、このほど整備から帰ってきた。どこを直し、どう変わったのか? どれくらい諭吉が飛んだのか!? 赤裸々にリポートする。
-
第46回:クルマを買い替えようとして、結局やめた話 2022.10.3 アメリカの暴れん坊「ダッジ・バイパー」に振り回されてはや6年。webCGほったの心に、ついに魔が差す? 読者諸兄姉の皆さまは、どんなタイミングでクルマの買い替えを考えますか。お金ですか? トラブルですか? 記者の場合はこうでした。
-
第45回:頼みの綱の民間療法 2022.5.20 漏るわ、滑るわ、雨とはいささか相性がよくないwebCG編集部員の「ダッジ・バイパー」。加えて電装系が気まぐれなのも頭痛の種だが、これら2つの悪癖に同時に襲われたら、持ち主はどんな窮地に立たされるのか? 春時雨の下で起きた事件の顛末をリポートする。
-
![ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】]() NEW
NEW
ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】
2026.1.19試乗記ベントレーのラグジュアリークーペ「コンチネンタルGT」のなかでも、ウェルビーイングにこだわったという「アズール」に試乗。控えめ(?)な680PSのハイブリッドがかなえる走りは、快適で満ち足りていて、ラグジュアリーカーの本分を感じさせるものだった。 -
![第327回:髪もクルマもナイスファイト!]() NEW
NEW
第327回:髪もクルマもナイスファイト!
2026.1.19カーマニア人間国宝への道清水草一の話題の連載。日産の新型「ルークス」で夜の首都高に出撃した。しっかりしたシャシーとターボエンジンのパワフルな走りに感心していると、前方にスーパーカーの姿を発見。今夜の獲物は「フェラーリ・ローマ」だ! -
![日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!]() NEW
NEW
日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!
2026.1.19デイリーコラムアメリカからの外圧による制度変更で、北米生産モデルの国内導入を決めたトヨタ。同様に、今後日本での販売が期待できる「海外生産の日本車」には、どんなものがあるだろうか? 清水草一が検証してみた。 -
![フェラーリ12チリンドリ(後編)]()
フェラーリ12チリンドリ(後編)
2026.1.18思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「フェラーリ12チリンドリ」に試乗。前編では伝家の宝刀であるV12エンジンを絶賛した山野。後編ではコンビを組むシャシーの印象を余すところなく聞いてみた。 -
![BYDシールAWD(4WD)【試乗記】]()
BYDシールAWD(4WD)【試乗記】
2026.1.17試乗記BYDのBEVサルーン「シール」の機能アップデートモデルが登場。強化のポイント自体はそれほど多くないが、4WDモデルの「シールAWD」は新たに電子制御式の可変ダンパーを装備したというから見逃せない。さまざまなシーンでの乗り心地をチェックした。 -
![新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る]()
新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る
2026.1.16デイリーコラム英国のモーターサイクル史にあまたの逸話を残してきた名門、ノートンが、いよいよ再始動! その数奇な歴史を振り返るとともに、ミラノで発表された4台の次世代モデルを通して、彼らが思い描く未来像に迫った。





















































