マツダが中期経営計画をアップデート 3段階のフェーズでEV本格導入へ
2022.11.22 自動車ニュース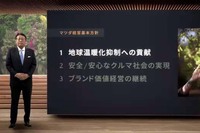 拡大 拡大 |
マツダは2022年11月22日、中期経営計画のアップデートと2030年に向けた経営の基本方針を発表した。
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
今回の発表は、2021年6月に告知された「2030年に向けた新たな技術・商品の開発方針」に続くもの。同社は以下の3点を基本方針としたうえで経営に取り組んでいくという。
- 地域特性と環境ニーズに適した電動化戦略で、地球温暖化抑制という社会課題の解決に貢献する。
- 人を深く知り、人とクルマの関係性を解き明かす研究を進め、安全・安心なクルマ社会の実現に貢献する。
- ブランド価値経営を貫き、マツダらしい独自価値をご提供し、お客さまに支持され続ける。
これら基本方針の具体策として、以下4つの取り組みを進めることもアナウンスされた。
(1)カーボンニュートラルに向けた取り組み
2050年のカーボンニュートラルに向け、2035年にグローバル自社工場のカーボンニュートラルを中間目標に掲げ、省エネ、再エネ、カーボンニュートラル燃料の活用を進める。
(2)電動化戦略
2030年までに、段階的に電動化に対応。2030年時点のグローバルでの新車販売におけるEV比率は、25%から40%になることを想定している。
(3)人とITの共創(きょうそう)によるマツダ独自の価値創造
人を深く研究し、人体や脳のメカニズムを理解・モデル化することで、高度運転支援技術の開発を加速。2040年をめどに自動車技術で対策可能なものについて、自社の新車が原因となる「死亡事故ゼロ」を目指す。AIやITを使いこなせる“デジタル人材”への投資も進める。
(4)原価低減活動とサプライチェーンの強靱(きょうじん)化
バリューチェーンとサプライチェーン全体を見渡し、ムダ・ムラ・ムリを徹底排除。原価低減力と減産抵抗力を強化する。バリューチェーンにおいてはユーザーに共感・満足してもらえる価値を一括して開発。サプライチェーンについてはモノが流れるスピードを速める。
このうち2番目の電動化戦略については、2030年までのスパンを以下3つのフェーズに分けたうえで実現を目指す。
- 第1フェーズ(2022~2024年):既存資産であるマルチ電動化技術を活用し、魅力的な商品と環境負荷の低減を両立。
- 第2フェーズ(2025~2027年):新しいハイブリッドシステムを展開するとともに、電動化が先行する中国市場にEV専用車を投入。期間の後半では、グローバルでEVを先行導入していく。
- 第3フェーズ(2028~2030年):EV専用車の本格導入を進めるとともに、電池生産への投資などを視野に入れていく。
またマツダは電動化戦略の一環として、電動駆動ユニットの開発・生産において専門的な知見を有する今仙電機製作所、オンド、中央化成品、広島アルミニウム工業、ヒロテック、富田電機、ロームとの協業も発表。小型・高性能・高効率な電動駆動ユニットの開発を進めるとともに地域経済の持続的な発展、ひいては2050年のサプライチェーン全体でのカーボンニュートラルを目指すとしている。
(webCG)

















































