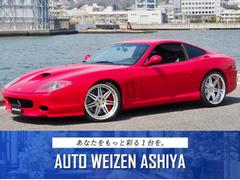第5回:フェラーリF40
スーパーカー時代の集大成 2017.03.30 スーパーカークロニクル 1970年代から80年代にかけて隆盛を誇ったスーパーカーの時代は、サーキットと高速道路を最高のレベルで疾駆(しっく)するスーパースポーツカーの出現によって終わる。その最終章を飾るのが、この「フェラーリF40」である。アンバランスさこそが最大の魅力
1960年代半ばに誕生した「ランボルギーニ・ミウラ」は、50~60年代の美しきスポーツカー時代に別れを告げるクルマ、すなわちスーパーカー時代の始まりを告げる節目のクルマだった。
そして、それからおよそ20年後の80年代半ば。フェラーリはグループBレース参戦を目的に「288GTO」を限定生産する。これをベースに、フェラーリ社創立40周年を記念して発売されたのがフェラーリF40であった。そしてこのF40は、70~80年代のスーパーカー時代に別れを告げ、21世紀につながるスーパースポーツカー時代の幕開けを告げる鐘でもあったと思う。
「308GT」シリーズの骨格をベースに特別仕立てされた288GTOは、結局、モータースポーツシーンに登場することなく、そういう意味では“悲劇のコレクターズアイテム”となる。それでもフェラーリ社は、その黎明(れいめい)期によくあったように、否、その頃を懐かしむように、レース×公道のミクスチュアを諦めることはなかったのだ。エンツォ・フェラーリが最後にゴーサインを出した市販車という事実にも、F40誕生に向けた原動力のありかがうかがえる。
F40はスーパーカー時代の集大成であるとともに、未来への期待と希望を内包していた。モノコック+サブフレームのミドシップレイアウトそのものは70年代スーパーカーの常とう手段である。「ディーノ」に始まったピニンファリーナのレオナルド・フィオラバンティの最終作であるスタイリングもまた、真横から見ればいかにもスーパーカー時代のフェラーリそのものであり、ロングノーズ/スモールキャビン/ハイデッキはイタリアンベルリネッタの真骨頂でもあった。
F40では、そのフィオラバンティ・シルエットに決して新しくない手法でエアロデバイスが追加されている。それはあたかもスーパーカー世代に並行して興隆したシルエットフォーミュラ(グループ5)のようであり、それゆえところどころに美的センスには不誠実なライン構成があって、逆につかみどころのない機能美をこのクルマに与えるに至った。
そんな、言ってみれば古いスタイリング&パッケージングにも関わらず、F40に後のスーパースポーツカー時代へと連なる未来を感じるのは、このクルマにカーボンファイバーやケブラー、アルミニウムといった、“当世流行り”の軽量素材がふんだんに使用されているからだ。
外身は古くて中身は新しい。パフォーマンスはエキセントリックながらターボ全盛時代のレーシングカーそのもので超一級。そのアンバランスさこそが時代の節目の証明であり、多くのファンを魅了してやまない要素と言っていいだろう。
“今”につながる衝撃の加速
F40の登場を境に、古式ゆかしきスーパーカーは徐々にその姿を消してゆき、まるで自動車の黎明期と同じように、サーキットと高速道路を平然と最高レベルで行き来するようなスーパースポーツカーが続々と現れることとなる。「マクラーレンF1」などは、さしずめその頂点と言うべきである。
とまれ、F40にはオーナーをして“次に欲しいクルマもF40”と言わしめるに十分な魅力が詰まっている。今でも思い出すのが、「F50」のデビューを兼ねた第1回フォルツァ・フェラーリのワンシーンだ。大雨のなか開催されたデモランで、全日本級のドライバーが各種フェラーリをゆっくりと走らせるなか、水しぶきを上げて狂気の走りをみせる、「F40GT」も追いつけないノーマルF40の姿があった。駆っていたのは、ニキ・ラウダである。
あらためて取材車両を眺めてみよう。ブレーキ強化のためホイールが変更されている以外は、ほとんどノーマル仕様である。何度見ても、後ろからみた幅の広さにはたじろいでしまう。そして、乗る前から神経質になってしまうほど、ノーズが長く、車体が低い。真正面や真横、といった具合に正対するよりも、ちょっと斜めに振って眺めた方が格好よく見えるスタイルである。
軽いドアはとても閉めづらい。CFRP(炭素強化プラスチック)タブに触れないよう、苦労して室内に潜り込む。インテリアはスパルタンのひと言。男の仕事場、というと女性オーナーに叱られそうだが、そういう修飾語しか思いつかない。
キーをひねり、脇のスターターボタンを押すと、「ランチアLC2」由来の3リッターV8ツインターボエンジンが、一瞬猛々(たけだけ)しく目覚めた。クラッチもハンドルもそれなりに重い。やはり、これは男の仕事だ。
路面が荒れていた。ターボを回さないよう、低回転でゆっくり走りだす。ターボさえ利かせなければ、ただの3リッターV8だ。危険もない。トルクのなさにイライラしながら街をクルーズし、体がクルマに慣れ、タイヤが路面に慣れ、エンジンが暖まるのを待つ。これは、70年代スーパーカーの所作に近い。そう、ターボの危険以外は……。
準備が整った。高速道路でターボパワーを解放した。車体がふわりと浮くような、前方の目に見えぬ何かからいきなりたぐり寄せられるような劇的に軽い加速は、未来、すなわち21世紀の今を、確かに向いているように思えた。
(文=西川 淳/写真=小林俊樹/編集=竹下元太郎)
※初出『webCG Premium』(GALAPAGOS向けコンテンツ)2011年春号(2011年4月1日ダウンロード販売開始)。再公開に当たり一部加筆・修正しました。
車両データ
フェラーリF40
ボディーサイズ:全長×全幅×全高=4358×1970×1124mm
ホイールベース:2450mm
車重:1100kg(乾燥重量)
駆動方式:MR
エンジン:3リッターV8 DOHC 32バルブ ツインターボ
トランスミッション:5段MT
最高出力:478ps(352kW)/7000rpm
最大トルク:58.8kgm(577Nm)/4000rpm
タイヤ:(前)245/40ZR17/(後)335/35ZR17

西川 淳
永遠のスーパーカー少年を自負する、京都在住の自動車ライター。精密機械工学部出身で、産業から経済、歴史、文化、工学まで俯瞰(ふかん)して自動車を眺めることを理想とする。得意なジャンルは、高額車やスポーツカー、輸入車、クラシックカーといった趣味の領域。
-
第6回:ランチア・ストラトス 2017.3.30 「ストラトス」の鮮烈なスタイリングは、いまなお見る者から言葉を奪うほどのインパクトがある。しかしこのデザインは、見せるためのものではなく、ラリーを戦うために研ぎ澄まされたものであることを忘れてはならない。
-
第4回:ポルシェ911カレラRS 2.7 2017.3.30 本来、「ポルシェ911」をスーパーカーの仲間に入れるべきではないだろう。しかしブームの真っただ中、「ロータス・ヨーロッパ」の宿敵として描かれた「ナナサンカレラ」だけは別だ。グループ4のホモロゲーションモデルの実力は、40年以上たった今もなお鮮烈だ。
-
第3回:ロータス・ヨーロッパ スペシャル 2017.3.29 スーパーカーとは何だろうか。排気量と価格で判断したら、「ロータス・ヨーロッパ」をそう呼ぶのはためらわれる。しかしヨーロッパはまちがいなくスーパーだった。この軽やかさ! レースとの絆は、同時代のフェラーリよりも濃いかもしれない。
-
第2回:ディーノ246GT 2017.3.29 スーパーカーブームには数々の伝説がついてまわった。「ディーノ」をフェラーリと呼ばないワケもそのひとつ。そしてディーノと「ヨーロッパ」の一体どちらがナンバーワンハンドリングマシンなのか? ということも、ボクらにとっては重大な関心事だった。
-
第1回:ランボルギーニ・カウンタックLP500S“ウルフ・カウンタック” 2017.3.29 スーパーカーブームの主役は「カウンタック」。そのまた頂点に君臨したのが、当時「LP500S」と呼ばれたこの“ウルフ・カウンタック”である。現オーナーの元でオリジナル状態に戻された“赤いオオカミ”が、三十余年のときを超えて、いま再び咆哮する!
-
![フェラーリ12チリンドリ(後編)]() NEW
NEW
フェラーリ12チリンドリ(後編)
2026.1.18思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「フェラーリ12チリンドリ」に試乗。前編では伝家の宝刀であるV12エンジンを絶賛した山野。後編ではコンビを組むシャシーの印象を余すところなく聞いてみた。 -
![BYDシールAWD(4WD)【試乗記】]()
BYDシールAWD(4WD)【試乗記】
2026.1.17試乗記BYDのBEVサルーン「シール」の機能アップデートモデルが登場。強化のポイント自体はそれほど多くないが、4WDモデルの「シールAWD」は新たに電子制御式の可変ダンパーを装備したというから見逃せない。さまざまなシーンでの乗り心地をチェックした。 -
![新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る]()
新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る
2026.1.16デイリーコラム英国のモーターサイクル史にあまたの逸話を残してきた名門、ノートンが、いよいよ再始動! その数奇な歴史を振り返るとともに、ミラノで発表された4台の次世代モデルを通して、彼らが思い描く未来像に迫った。 -
![第858回:レースの技術を市販車に! 日産が「オーラNISMO RSコンセプト」で見せた本気]()
第858回:レースの技術を市販車に! 日産が「オーラNISMO RSコンセプト」で見せた本気
2026.1.15エディターから一言日産が「東京オートサロン2026」で発表した「オーラNISMO RSコンセプト」。このクルマはただのコンセプトカーではなく、実際のレースで得た技術を市販車にフィードバックするための“検証車”だった! 新しい挑戦に込めた気概を、NISMOの開発責任者が語る。 -
![ルノー・グランカングー クルール]()
ルノー・グランカングー クルール
2026.1.15画像・写真3列7座の新型マルチパーパスビークル「ルノー・グランカングー クルール」が、2026年2月5日に発売される。それに先駆けて公開された実車の外装・内装を、豊富な写真で紹介する。 -
![市街地でハンズオフ運転が可能な市販車の登場まであと1年 日産の取り組みを再確認する]()
市街地でハンズオフ運転が可能な市販車の登場まであと1年 日産の取り組みを再確認する
2026.1.15デイリーコラム日産自動車は2027年に発売する車両に、市街地でハンズフリー走行が行える次世代「ProPILOT(プロパイロット)」を搭載する。その発売まであと1年。革新的な新技術を搭載する市販車の登場は、われわれにどんなメリットをもたらすのか。あらためて考えてみた。