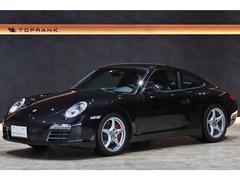はじまりは「930」から 「ポルシェ911ターボ」が歩んだ50年
2024.09.04 デイリーコラムターボ時代の幕開け
1973年9月13日。IAAフランクフルトモーターショーでは、ポルシェスタンドに展示された「911」のプロトタイプがとりわけ大きな注目を浴びていた。大きく張り出したリアフェンダーと巨大なリアウイングが異彩を放ち、3リッターエンジンにはターボチャージャーを備えて最高出力260PSを発生。最高速は250km/hと説明されていた。
また、BMWのスタンドでは「2002ターボ」と命名されたモデルが公開されていた。この2つの“ターボ”が登場したことから、振り返ってみれば、同年のIAAはターボ時代の幕開けを告げるショーであったといえよう。
本稿では生誕50周年を迎えた「911ターボ」(当初は「930ターボ」とも称していた)が登場した経緯と、その周辺に的を絞って記してみることにした。
ポルシェは「356」の生産開始以来、レースを車両開発の場として重要視していたが、ターボチャージング技術も例外ではなかった。発端はパワーアップのための有効な手段としてのターボであったが、近年では、二酸化炭素削減という社会の要求に沿うための、省エネルギーと高出力を両立させる技術としてターボが活用されている。ポルシェにとって“ターボ”は重要なアイコンであり、たとえ電気自動車であっても、それがハイパワーモデルの名称として使われていることはご承知のとおりだ。
内燃機関の出力向上には過給が有力な手法であることは、エンジン黎明(れいめい)期に明らかにされ、第2次世界大戦前に機械的駆動の過給器(スーパーチャージャー)の実用化が始まった。過給技術の実用化を果たした研究者のひとりがフェルディナント・ポルシェ博士で、ダイムラー在籍時の1923年に「メルセデス2リッターコンプレッサー車」の開発に成功している。初代ポルシェ博士による過給器研究と、1973年に登場した911ターボとの間には、もちろん直接的な関係はない。だが、ポルシェによる過給技術の研究を追うと、過給は家系案件であったのではとも思えてくる。
レースでターボの技術を蓄積
排ガスのエネルギーを用いたターボチャージャーは、スイス人技術者によって1905年に特許が取得された技術であり、ディーゼルエンジンに採用されたのち、レシプロガソリンエンジンでは航空機の分野で急速に普及が進んだ。この研究ではアメリカが先行し、第2次大戦で用いた航空機エンジンに備えられて有効性が証明された。量産型ガソリン車の分野でもアメリカが早く、1962モデルイヤーにゼネラルモーターズが放った「オールズモビル・カトラスF-87ジェットファイア」に、初めてターボ装着エンジンが搭載された。
ポルシェがターボカーの市販化に向けての行動を起こしたのは1969年のことだった。2リッターフラット6のターボ仕様を開発し、911と「914-6」に搭載する計画だったが、市販化は時期尚早だと断念している。その後も研究開発は続けられ、レーシングエンジンのターボ化によって経験を積んでいった。
それがレーシングスポーツカーの「917」をベースにしたマシンによる、1971年からのCan-Am選手権シリーズレースへの挑戦であった。排気量無制限の規定のもとで大排気量のアメリカンV8によって争われることを考慮して、917の5リッターフラット12エンジンにターボを装着。1972年には9戦中7勝。1973年には、5.4リッターで1150PSを発生する「917/30」を投入すると、常勝だったマクラーレンはなすすべもなく、ポルシェは全9戦を全勝してシーズンを完全制覇した。
こうしてターボ技術のノウハウを熟知したポルシェは、911のターボ化を決断すると、そのレース活動と911ターボの市販化に向けて熟成を急いだ。実際のところ、サーキットにおける911の優位は台頭するライバルの前に揺らぎつつあることは明らかであり、性能向上の手だてとしてターボチャージングは最適であった。
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
パワフルなだけではなかった911ターボ
1973年のIAAから約1年後の1974年10月に開催されたパリサロンで911ターボの量産仕様を発表したが、そのプレスリリースでは、「洗練されたパワー」と「他にはないスポーティーさ」をうたっていた。
搭載されたエンジン(930/50型)は、「カレラ3.0」用の2994ccユニットをベースとし、最大ブースト圧0.8barと6.5:1の圧縮比から、カレラ3.0より60PS、ノーマルの「911 2.7」より95PS高い、260PS/5500rpmを発生した。人々を驚かせたのは、最大トルクが35.0kgf・m/4000rpm(カレラ3.0は26.0kgf・m/4200rpm)と強大であったことで、パワフルでありながら、静粛な高速ツーリングを可能とし、内装はノーマルモデルに比べて格段に豪華なしつらえとなって、ひとクラス上のモデルへと成長した。
結果的に、エンジンのターボ化によって、新エンジン開発と比べて、コストを掛けずとも飛躍的な高性能が手に入ることを実証してみせた。そしてこの様子を注視していた世界各国のメーカーは、ターボによる高性能エンジン開発に舵を切っていくことになる。各国でターボ車開発が盛んになると、タービンなど高温かつ高回転に耐えなければならない金属材料や潤滑技術が進歩し、燃焼技術の研究も加速していった。
だが、発売に向けて熟成を急ぐポルシェの前には暗雲が立ちこめることになった。1973年10月に第4次中東戦争が発生し、オイルショックが世界中にまん延していったからである。これによって全世界で原油の消費削減が急務となり、燃費のよさがクルマ購入の優先選択基準になった。それまで非現実的な最高速競争に舞い上がっていたスーパースポーツカーの市場は一気に崩壊していった。こうした環境のなかで、省エネルギーを見据えながら、1974年10月に911ターボの市販が始まったのである。
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
空冷時代に450PSにまで到達
ここで、ポルシェによる911ターボモデルの変遷を簡単に振り返ってみたい。3リッターターボの生産は1974年9月(市販開始は10月)から1977年8月まで続くと、1977年9月にはインタークーラーを備えたうえで排気量を3.3リッターに拡大、300PSと42.0kgf・mとなった。1990年12月には3.6リッターに進化し、1992年にはより強力な360PSの3.6リッター型が登場した。空冷期最後の「993」ではツインターボを採用して408PSと540N・mに高められ、同時に燃費の向上も図られ、1995年には排出物質が世界で最も少ない自動車エンジンと評された。さらに1996年モデルでは430PSに高めるキットが登場、1998年モデルでは450PSに引き上げられ、空冷時代のロードカーとして最もパワフルなターボフラット6となった。
こうした排気量拡大と出力向上を可能にした要因のひとつに、オリジナルの901型空冷エンジンの基本設計の巧みさがある。911デビュー当時には、2リッター(80×66mm)から130PSを発生していたが、その基本レイアウトを大規模に変更せずに、各部に加えられたきめの細かい改変の積み重ねによって、究極的には3.6リッター(100×76.4mm)の排気量(NAでは3.8リッター)と、450PSにまで高められ、それに応えて(耐えて)いる。
ハンス・トマラのもとでエンジン設計に従事したクラウス・フォン・リュッカートは、ターボ装着や、ここまでの性能向上は予想だにしていなかっただろうが、いかに出力向上に留意した基本設計をおこなっていたかが、このパワーアップの歩みから想像できよう。
996型から登場した水冷型フラット6では、言うまでもなく設計の当初からターボチャージングは折り込み済みであり、排気量を抑えながらターボを備えることで高性能と省燃費を両立させたエンジンが、現在の911のパワーユニットになっていることはご承知のとおりだ。
(文=伊東和彦<Kazuhiko ITO/Mobi-curators Labo.>/写真=ポルシェアーカイブス、BMWアーカイブス/編集=藤沢 勝)

伊東 和彦
-
待望の7人乗りMPV「ルノー・グランカングー」を大解剖 ライバルにはない魅力はあるか? 2026.1.30 いよいよ日本に導入された、ロングボディー・3列シートの「ルノー・グランカングー」。満を持して登場した真打ちは、競合する国産ミニバンや7人乗りの輸入MPVに対し、どのような特徴があり、どんな人におススメなのか? 取材会で実車に触れた印象を報告する。
-
「スバルPerformance-B STIコンセプト」の市販化はズバリ2027年!? 2026.1.29 スバルが「東京オートサロン2026」でスーパー耐久シリーズ2026の参戦車両を発表。そのプロフィールは「スバルPerformance-B STIコンセプト」そのものだ。同モデルの市販化はあるのか。スバリストが願望を込めつつ予想する。
-
クワッドモーター搭載で過去にないパフォーマンス BMWが示したBEV版「M3」の青写真 2026.1.28 BMW Mが近い将来に市場投入を図る初のピュア電気自動車の骨子を発表した。車種は明かされていないものの、「BMW Mノイエクラッセ」と呼ばれており、同時に公開された写真が小型セダンであることから、おそらく次期型「M3」と思われる。その技術的特徴を紹介する。
-
春は反則金祭り!? 2026年4月に始まる「自転車の青切符導入」を考える 2026.1.26 2026年4月から、自転車を対象とした交通反則通告制度(青切符)が導入され、違反者には反則金が科されるようになる。なぜこうした事態になったのか、実情について自動車ライターの工藤貴宏が語る。
-
「K-OPEN」や競技用「ミラ イース」の開発者を直撃! 東京オートサロンで感じたダイハツの心意気 2026.1.23 「東京オートサロン2026」に、ターボエンジン+5段MTの「ミラ イース」や「K-OPEN」のプロトタイプを出展したダイハツ。両車の開発者が語った開発秘話や市販化の狙いとは? 「走る楽しさをみんなのものに」に本気で取り組む、ダイハツの心意気に触れた。
-
![レクサスRZ550e“Fスポーツ”(4WD)【試乗記】]() NEW
NEW
レクサスRZ550e“Fスポーツ”(4WD)【試乗記】
2026.1.31試乗記レクサスの電気自動車「RZ」が大型アップデートを敢行。特に今回連れ出した「RZ550e“Fスポーツ”」は「ステアバイワイヤ」と「インタラクティブマニュアルドライブ」の2大新機軸を採用し、性能とともに個性も強化している。ワインディングロードでの印象を報告する。 -
![「スズキGSX-8T/GSX-8TT」発表会の会場から]() NEW
NEW
「スズキGSX-8T/GSX-8TT」発表会の会場から
2026.1.30画像・写真スズキが新型モーターサイクル「GSX-8T/GSX-8TT」をいよいよ日本で発売。イタリアのデザインセンターが手がけた新型のネオクラシックモデルは、スズキに新しい風を吹き込むか? タイムレスなデザインと高次元の走りを標榜する一台を、写真で紹介する。 -
![あの多田哲哉の自動車放談――トヨタ・クラウン エステートRS編]() NEW
NEW
あの多田哲哉の自動車放談――トヨタ・クラウン エステートRS編
2026.1.30webCG Movies「クラウン」らしからぬデザインや4車種展開などで話題になった、新世代のトヨタ・クラウン。そのうちの一台「クラウン エステート」に試乗した、元トヨタの車両開発者、多田哲哉さんの感想は? -
![待望の7人乗りMPV「ルノー・グランカングー」を大解剖 ライバルにはない魅力はあるか?]()
待望の7人乗りMPV「ルノー・グランカングー」を大解剖 ライバルにはない魅力はあるか?
2026.1.30デイリーコラムいよいよ日本に導入された、ロングボディー・3列シートの「ルノー・グランカングー」。満を持して登場した真打ちは、競合する国産ミニバンや7人乗りの輸入MPVに対し、どのような特徴があり、どんな人におススメなのか? 取材会で実車に触れた印象を報告する。 -
![第946回:欧州に「277万円以下」のクルマなし! キューバ化を覚悟した冬]()
第946回:欧州に「277万円以下」のクルマなし! キューバ化を覚悟した冬
2026.1.29マッキナ あらモーダ!欧州でお値段1万5000ユーロ未満の大衆車が壊滅状態に! 自動車の価格高騰はなぜ起き、そしていつまで続くのか? 一般の自動車ユーザーは、この嵐をいかにしてやり過ごそうとしているのか? イタリア在住の大矢アキオがリポートする。 -
![第286回:才人監督が描くディストピアのデスゲーム 『ランニング・マン』]()
第286回:才人監督が描くディストピアのデスゲーム 『ランニング・マン』
2026.1.29読んでますカー、観てますカー「アルピーヌA290」で追っ手のハンターから逃げ延びろ! スティーブン・キングが50年前に予見した未来は、まさに現在の状況そのもの。分断とフェイクが支配する現実を鋭くえぐった最新型デスゲーム映画。