第880回:トリビア満載! 「フィアットの家」訪問記
2024.10.10 マッキナ あらモーダ!屋上で歴史を振り返る
2024年で創立125年を迎えたフィアットが、創業の地トリノに新たな展示スペース「カーザ・フィアット(Casa Fiat:フィアットの家)」をオープンした。2024年7月11日のことである。
カーザ・フィアットは、旧フィアット・リンゴット工場ビルの屋上にある既存施設「アニェッリ絵画館」の1フロアを用いている。スペース的には、「フィアット500」にテーマを絞って2021年に開設された「カーザ500」を改装したものである。
展示は創立以来の歴史を10年ごとに区切り、写真やオーディオビジュアル資料で解説している。
なかでも焦点が当てられているもののひとつが、施設が入っているリンゴット・ビルの歴史だ。1910年代に建築家ジャコモ・マッテ-トゥルッコによって設計されたこの5階建て巨大工場は、20世紀イタリア建築遺産のひとつである。イタリア未来派芸術運動を主導したフィリッポ・トンマーゾ・マリネッティや、建築家ル・コルビュジエも絶賛した。その後、1990年代にレンツォ・ピアノによって商業/オフィスビルにリニューアルされ、今日に至っている。
同時に、フィアットと社会とのつながりも詳しく紹介されている。例として、フィアットは福利厚生施設として“夏の家”を早くも1930年代に建設。社員の子どもたちを対象に、夏季学校を実施している。
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
歴史を包み隠さず
フロアのスペースは限られているが、展示はパネルだけでなく、引き出しや扉を開けると現れる仕掛けも導入されていて、来館者が発見する体験を増幅させる。フィアット製の自動車に関する歴史だけでなく、トリビア的なものにも関心のある人なら、少なくとも1時間は飽きずに滞在できそうだ。
目を楽しませてくれるのは、イタリアの戦後高度成長期に制作されたフィアットの広告コレクションである。同時期に同社が手がけていた洗濯機や冷蔵庫の広告もあるのだが、さらに興味深いものが紹介されている。
一例は1978年にフィアットが開発した装置「トーテム」だ。トーテム(TOTEM)とはTotal Energy Moduleの略で、なんと量産型「フィアット127」のエンジンを使用した据え置き型汎用(はんよう)ジェネレーターである。発電機として電力を供給するとともに、排熱を暖房や水の温めに利用して家庭や事業所に供給する。エンジンに使用する燃料には、家畜の排せつ物から生成したガスを用いる。これにより、一種の資源循環システムを形成する構想だった。別の資料を参照すると、一部では実用に供されたが、大規模な普及には至らなかったようだ。
また1972年「フィアットX1_23」といった、当時としては極めて斬新な電気自動車のプロトタイプもパネルで紹介されている。しかしながら、このように時代を先駆けていたアイデアの数々も、後年には断絶してしまった。そのため、今日の目からすると、どこか挽歌(ばんか)にしか映らないのが至極残念である。
評価すべきは、同社による過去の歴史文献でもそうだったように、他社ではデリケートな話題として避けられやすい内容についても紹介している点だ。例えば“ドゥーチェ(統帥)”ことベニート・ムッソリーニが演説のためリンゴットを訪れ、演壇でジョヴァンニ・アニェッリ(1世)と並んでいる写真、1970年代の工場従業員による激しい労働運動の資料、といったものも展示されていた。
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
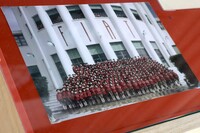 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
幻の日本人デザイナー作品も
1970年代の部にも興味深いパネル資料を見つけた。1972年にニューヨーク近代美術館(MoMA)で開催された「イタリア 新しい国内風景」に関するものだ。筆者が補足すれば、同展はイタリア工業デザインが学術的な観点で世界に認められたものとして、伝説の展覧会と位置づけられている。
解説によれば、展覧会の企画にあたって監修者は、フィアットを含むイタリア主要企業数社に協力を打診した。その結果、各企業が 10 万ドルを寄付。フィアットは移動手段に特化したセクションを設けることになり、マルコ・ザヌーゾ、アルベルト・ロッセッリ、 マリオ・ベリーニという、そうそうたるデザイナーにプロトタイプの製作を委嘱した。ロッセッリがデザインしたのは「モビリティーと拡張性」という 2 つの基本原則に従ったモービルホームで、移動時の専有面積が10平方メートルなのに対して、拡張すると最大28平方メートルまで広がった。このデザインには日本人デザイナー、細江勲夫が協力したことが明記されている。
細江氏は東京生まれのプロダクトデザイナーである。1967年に渡伊し、前述のロッセッリに師事した。数々の家具や照明機器を手がけて活躍しており、プロトタイプの観光バス「オルランディ・スパーツィオ」のプロトタイプでは、1979年に有名なデザイン賞「コンパッソ・ドーロ」を受賞している。1980年代には自動車誌『カーグラフィック』にもエッセイを寄稿していたが、惜しくも2015年に他界している。
細江氏は1942年生まれであるから、1972年といえば30歳ということになる。師匠との共作とはいえ、フィアットは若き外国人デザイナーに天下のMoMA進出の機会を与えたことになる。
参考までに、今回紹介したカーザ・フィアットの上階にある「アニェッリ絵画館(ピナコテカ・アニェッリ)」は、フィアットの創業3代目であるジョヴァンニ・アニェッリ(1921-2003)と夫人のマレッラが生前収集した絵画・彫刻コレクションから25点を厳選したものである。
デザイン振興に対する高い意識と、美術に関する見識で、フィアットおよびアニェッリ家は、たびたびイタリア文化の支援者となってきた。曲解すれば、かつて筆者が買ったフィアット車2台の車両代金の一部も、回りまわってこのように使われていたと考えると、決して悪い気はしないのである。
今日、フィアットの流れを継いだステランティスの筆頭株主は、依然アニェッリ家の持ち株会社である。とはいえ、もはやアムステルダムを本社所在地とする国際企業となり、世代も変わった。そうしたなかでも、デザイン・芸術のパトロン的精神が、将来も何らかのかたちで継承されることを願ってやまない。
【アニェッリ絵画館(Pinacoteca Agnelli)】
- 住所 Via Nizza, 230/103 10126 Torino
- 営業時間 11時~21時
- 定休日 毎週月曜日
- 入場料 「カーザ・フィアット」および「フィアット・カフェ500」の入場は無料、絵画館および全エリアは10ユーロ(高齢者割引あり)、テストコース跡「ピスタ500」は2ユーロ
(文=大矢アキオ ロレンツォ<Akio Lorenzo OYA>/写真=Akio Lorenzo OYA、Pinacoteca Agnelli/編集=堀田剛資)

大矢 アキオ
Akio Lorenzo OYA 在イタリアジャーナリスト/コラムニスト。日本の音大でバイオリンを専攻、大学院で芸術学、イタリアの大学院で文化史を修める。日本を代表するイタリア文化コメンテーターとしてシエナに在住。NHKのイタリア語およびフランス語テキストや、デザイン誌等で執筆活動を展開。NHK『ラジオ深夜便』では、24年間にわたってリポーターを務めている。『ザ・スピリット・オブ・ランボルギーニ』(光人社)、『メトロとトランでパリめぐり』(コスミック出版)など著書・訳書多数。近著は『シトロエン2CV、DSを手掛けた自動車デザイナー ベルトーニのデザイン活動の軌跡』(三樹書房)。イタリア自動車歴史協会会員。
-
第947回:秒殺で当確? 新型「ルノー・クリオ」が販売店にやってきた! 2026.2.5 欧州で圧巻の人気を誇る「ルノー・クリオ(日本名:ルーテシア)」がついにフルモデルチェンジ! 待望の新型は市場でどう受け止められているのか? イタリア在住の大矢アキオが、地元のディーラーにやってきた一台をつぶさにチェック。その印象を語った。
-
第946回:欧州に「277万円以下」のクルマなし! キューバ化を覚悟した冬 2026.1.29 欧州でお値段1万5000ユーロ未満の大衆車が壊滅状態に! 自動車の価格高騰はなぜ起き、そしていつまで続くのか? 一般の自動車ユーザーは、この嵐をいかにしてやり過ごそうとしているのか? イタリア在住の大矢アキオがリポートする。
-
第945回:「時速286キロの香り」とは? 109回目のピッティ・イマージネ・ウオモから 2026.1.22 イタリア在住の大矢アキオが、フィレンツェで開催される紳士モード見本市「ピッティ・イマージネ・ウオモ」をリポート。アルファ・ロメオとの思い出を込めたという香水から、人と人とをつなぐ媒体、文化としての自動車に思いをはせた。
-
第944回:こんな自動車生活は最後かもしれない ―ある修理工場で考えたこと― 2026.1.15 いつもお世話になっている“街のクルマ屋さん”で、「シトロエン・メアリ」をさかなにクルマ談議に花が咲く。そんな生活を楽しめるのも、今が最後かもしれない。クルマを取り巻く環境の変化に感じた一抹の寂しさを、イタリア在住の大矢アキオが語る。
-
第943回:スバルとマツダ、イタリアでの意外なステータス感 2026.1.8 日本では、数ある自動車メーカーのひとつといった感覚のスバルとマツダだが、実はイタリアでは、根強いファンを抱える“ひとつ上のブランド”となっていた! 現地在住の大矢アキオが、イタリアにおけるスバルとマツダのブランド力を語る。
-
![ガス代は下落しハイブリッド好調 では“燃費の相場”はどうなっている?]() NEW
NEW
ガス代は下落しハイブリッド好調 では“燃費の相場”はどうなっている?
2026.2.9デイリーコラム暫定税率は廃止となり、高止まりしていた燃料代は下落。一方でBEV化の速度は下がり、ハイブリッド車需要が高まっている。では、2026年現在の燃費はいかほどか? 自動車購入時の目安になるであろう“燃費の相場”について考える。 -
![日産キャラバン グランドプレミアムGX MYROOM(FR/7AT)【試乗記】]() NEW
NEW
日産キャラバン グランドプレミアムGX MYROOM(FR/7AT)【試乗記】
2026.2.9試乗記「日産キャラバン」がマイナーチェンジでアダプティブクルーズコントロールを搭載。こうした先進運転支援システムとは無縁だった商用ワンボックスへの採用だけに、これは事件だ。キャンパー仕様の「MYROOM」でその性能をチェックした。 -
![トヨタ・カローラ クロス“GRスポーツ”(前編)]()
トヨタ・カローラ クロス“GRスポーツ”(前編)
2026.2.8思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「トヨタ・カローラ クロス“GRスポーツ”」に試乗。人気の都市型SUVに、GRのデザイン要素と走りの味つけを加味した特別なモデルだ。箱根のワインディングロードでの印象を聞いた。 -
![無限N-ONE e:/シビック タイプR Gr.B/シビック タイプR Gr.A/プレリュード【試乗記】]()
無限N-ONE e:/シビック タイプR Gr.B/シビック タイプR Gr.A/プレリュード【試乗記】
2026.2.7試乗記モータースポーツのフィールドで培った技術やノウハウを、カスタマイズパーツに注ぎ込むM-TEC。無限ブランドで知られる同社が手がけた最新のコンプリートカーやカスタマイズカーのステアリングを握り、磨き込まれた刺激的でスポーティーな走りを味わった。 -
![インディアン・チーフ ヴィンテージ(6MT)【海外試乗記】]()
インディアン・チーフ ヴィンテージ(6MT)【海外試乗記】
2026.2.6試乗記アメリカの老舗、インディアンの基幹モデル「チーフ」シリーズに、新機種「チーフ ヴィンテージ」が登場。このマシンが、同社のラインナップのなかでも特別な存在とされている理由とは? ミッドセンチュリーの空気を全身で体現した一台に、米ロサンゼルスで触れた。 -
![ホンダの「Hマーク」がいよいよ刷新! ブランドロゴ刷新の経緯とホンダのねらい]()
ホンダの「Hマーク」がいよいよ刷新! ブランドロゴ刷新の経緯とホンダのねらい
2026.2.6デイリーコラム長く親しまれたホンダ四輪車のロゴ、通称「Hマーク」がついに刷新!? 当初は「新しい電気自動車用」とされていた新Hマークは、どのようにして“四輪事業全体の象徴”となるに至ったのか? 新ロゴの適用拡大に至る経緯と、そこに宿るホンダの覚悟を解説する。



















































