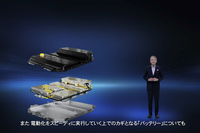第22回:とにもかくにもスピード重視! 中国におけるホンダの電動化戦略を読み解く(後編)
2021.11.02 カーテク未来招来 拡大 拡大 |
ホンダが中国における電動化戦略を発表。中国独自のEV(電気自動車)プラットフォームを採用し、向こう5年で10車種を投入するという。しかしホンダは、北米では2020年代後半に新開発のEVプラットフォーム「e:アーキテクチャー」を投入することになっていたはず。なぜホンダのEV戦略は“中国”と“それ以外”で分かれることになったのか。
 拡大 拡大 |
この戦略は非効率では?
前回のコラムでは、ホンダが向こう5年でEVラインナップを大幅に拡充すること、そのために2種類の中国専用EVプラットフォームを導入することを説明したところで終わった。しかし大きな“謎”は、ホンダがなぜ中国独自のEVプラットフォームの投入を決断したかである。
あらためてホンダのEV戦略をおさらいすると、米国でまず2024年にGM製のプラットフォームを使った新型SUV「プロローグ」を発売し、その後、同じプラットフォームのEVをアキュラブランドからも投入することを表明している。そして2020年代後半に、独自開発のEVプラットフォーム「e:アーキテクチャー」を使用したモデルを、米国を皮切りにグローバルに展開する計画だ。つまり、2020年代の前半はGMのEVプラットフォームを使うことでしのぎ、その間に独自のEVを開発しようという戦略である。
しかし中国では、それより前にマーケット独自の新しいEVプラットフォーム「e:NアーキテクチャーF」と「e:NアーキテクチャーW」を開発・投入し、向こう5年で10車種を展開するとしている。世界の完成車メーカーが、グローバルで統一したEVプラットフォームを採用する方針であることを考えると、ホンダが“中国”と“それ以外”で異なるプラットフォームを展開するのは、無駄な投資という印象が否めない。
2つの環境規制とクレジットの重圧
なぜホンダはe:アーキテクチャーの完成まで待てなかったのか? 背景にあるのは“クレジットの重圧”だ。
ここで言うクレジットとは何か? 現在、中国の自動車市場には2つの環境規制がある。販売車両の平均燃費を一定以上の水準にすることを義務づける燃費規制と、販売規模に応じて一定以上の“新エネルギー車(NEV)”、具体的にはEVやプラグインハイブリッド車、燃料電池車の販売を義務づけるNEV規制だ。これらを達成できなければ、前者については燃費基準をクリアしている企業から、後者については指定台数以上のNEVを販売している企業から、基準の未達成分をもとに算出される“クレジット”を購入しなければならない。
ホンダの中国合弁会社である東風ホンダと広州ホンダは、ともに燃費規制もNEV規制もクリアできておらず、2020年に支払ったクレジット購入額は、例えば『日経ビジネス』の記事「中国のEVクレジット規制、日系メーカーの負担は1200億円相当に」から推定すると、合計で約500億円にのぼる。
日系の現地合弁メーカーは総じて両規制をクリアできていないのだが、なかでもホンダ系2社の支払額は突出している。同記事では日系メーカーが支払うクレジット購入額の合計を約1200億円と推定しているが、その半分近くをホンダ系の2社が払っている計算だ。EVの投入は、平均燃費の引き下げとNEV規制達成の両方に貢献する。ホンダは他の日系メーカーと比べても、はるかに切実にEV投入の必要に迫られているのだ。
 拡大 拡大 |
新型EVが「ヴェゼル」にそっくりな理由
こうした目で今回のホンダの発表動画を見ると、「e:NS1」と「e:NP1」に採用される「e:NアーキテクチャーF」のフロア形状は、前席下が盛り上がっている。
両モデルと“デザインがよく似た”現行型「ヴェゼル」は、基本骨格に先代のプラットフォームを改良して用いており、燃料タンクを前席下に置くセンタータンクレイアウトも受け継いでいる。今回の発表動画を見ると、e:NアーキテクチャーFのフロア形状は、前席下が盛り上がったセンタータンクレイアウトの特徴をそのまま受け継いでおり、ベース車となった(と思われる)ヴェゼルの基本骨格を、かなりの部分踏襲していることがうかがえる。
e:NS1とe:NP1は、中国におけるホンダブランドのEV第1弾となるモデルだが、ホンダはこれ以前にも、広州ホンダの自主ブランドEVとして「理念VE-1」を、また東風ホンダの自主ブランドEVとして「X-NV」を、それぞれ2019年に発売している。理念VE-1もX-NVも先代ヴェゼルをベースとしたEVであり、e:NS1とe:NP1の開発にその経験が生かされるのは間違いない。言い換えれば、ホンダにとって最速で開発が可能だったEVが今回のe:NS1とe:NP1だったといえる。
「e:NアーキテクチャーW」の資源はどこから?
一方、今回発表された3車種のコンセプトカーに使われるe:NアーキテクチャーWはどうか。とにかくスピード重視で開発する必要があるプラットフォームだから、やはり“ありもの”を活用するのではないか。そう考えてまず疑ったのは「ホンダe」のプラットフォームである。というのも、ホンダeは後輪駆動であり、やはり後輪駆動を基本とするe:NアーキテクチャーWとパワートレインを流用しやすいと思ったからだ。
3車種のコンセプトカーは、写真を見ると分かるようにe:NS1やe:NP1より車体がひと回り大きい。恐らくDセグメントくらいのサイズはありそうだ。これに対してホンダeはAセグメントのコンパクトカーだ。車体サイズが違いすぎるのでプラットフォームそのものの流用は難しいだろう。一方で、駆動モーターの最高出力は100kWと113kWであり、「マツダMX-30 EVタイプ」の107kWに比肩する。多少の出力アップを図れば、使えないこともないのではないか?
しかし、今回の発表で公開されたe:NアーキテクチャーWの駆動モーターの外観を見ると、ホンダeのそれとは似ても似つかぬ形状をしている。ついでに言えばサスペンション形式も大きく異なっており、ほぼ別物だと判断せざるを得なかった。
次に考えたのが、ホンダが2019年に公開した「次世代EV用パワートレインシステムのコンセプトモデル」の駆動モーターだ。これはホンダeに続くEVのパワートレインとして、電池パックなどとともにお披露目されたものだ。しかし、今回のe:NアーキテクチャーWの動画と比べると、やはりモーターの形状は全く違っていた。
開発のスピードを優先しつつ社内の資産を活用しないとなれば、答えはひとつしかない。外部企業の活用である。
外部企業のE-Axleを活用か
EV用モーターに関しては、ホンダは日立製作所と関係が深く、両社は合弁で自動車部品メーカーの日立Astemoを設立している。さらにさかのぼると、ホンダは2017年に同社の前身である日立オートモティブシステムズとの共同出資で、EV用モーターの開発・製造を手がける日立オートモティブ電動機システムズ(現日立Astemo電動機システムズ)を設立している。日立Astemo電動機システムズは、2020年12月から中国でEV向けモーターを製造しているというので、同社が開発し、中国で生産するモーターを搭載するというのが、e:NアーキテクチャーWに関する最も可能性の高いシナリオといえそうだ。
モーターと並んでEVの重要な構成要素である電池については、世界最大のEV用電池メーカーであるCATLを軸に調達するようだ。しかし、電池やモーターといったクルマに占めるコスト比率の高い部品を外部から調達していては、利益率が低くなるのは避けられない。折しもトヨタ自動車は2021年10月18日、米国において2030年までにEV用を含む車載用電池の現地生産に、約3800億円を投資すると発表した。これまで外部から購入していた電池の内製化を図る動きで、この流れには他社も続くことだろう。ホンダも、今回は緊急避難的に外部からの購入でしのいだとしても、2020年代後半登場予定のe:アーキテクチャーからは駆動モーターを内製化するだろうし、ゆくゆくは電池の内製化にも踏み切るだろうというのが筆者の予測だ。
ホンダはこれまでも、ハイブリッド車の開発や燃料電池車の開発でトヨタ自動車に後れを取りつつも、猛スピードでキャッチアップしてきた実績がある。追いかけるのが得意なホンダの本領が、これからEVでも発揮されることを期待したい。
(文=鶴原吉郎<オートインサイト>/写真=本田技研工業/編集=堀田剛資)
 拡大 拡大 |

鶴原 吉郎
オートインサイト代表/技術ジャーナリスト・編集者。自動車メーカーへの就職を目指して某私立大学工学部機械学科に入学したものの、尊敬する担当教授の「自動車メーカーなんかやめとけ」の一言であっさり方向を転換し、技術系出版社に入社。30年近く技術専門誌の記者として経験を積んで独立。現在はフリーの技術ジャーナリストとして活動している。クルマのミライに思いをはせつつも、好きなのは「フィアット126」「フィアット・パンダ(初代)」「メッサーシュミットKR200」「BMWイセッタ」「スバル360」「マツダR360クーペ」など、もっぱら古い小さなクルマ。
-
第50回:歴代モデルに一気乗り! 「シビック」の歴史は日本のカーテクの歴史だった(後編) 2022.9.20 今年で誕生50周年を迎える「ホンダ・シビック」の歴代モデルに一挙試乗! クルマの端々に見られる、自動車技術の進化の歴史と世相の変化の“しるし”とは? 半世紀の伝統を誇る大衆車の足跡を、技術ジャーナリストが語る。
-
第49回:歴代モデルに一気乗り! 「シビック」の歴史は日本のカーテクの歴史だった(前編) 2022.9.6 今年で誕生50周年を迎える「ホンダ・シビック」の歴代モデルに試乗! 各車のドライブフィールからは、半世紀にわたる進化の歴史が感じられた。私生活でもシビックに縁のあった技術ジャーナリストが、シビックのメカニズムの変遷をたどる。
-
第48回:その恩恵は価格にも! 新型「トヨタ・クラウン」が国際商品に変貌した必然 2022.8.23 プラットフォームの共有と大胆なグローバル展開により、先代比で77万円もの値下げを実現!? 新型「トヨタ・クラウン」の大変身がもたらす恩恵とは? “合理的でまっとう”な経営判断を実践できる、トヨタならではの強みを探った。
-
第47回:用意周到な計画に脱帽 新型「クラウン クロスオーバー」に見るトヨタの“クルマづくり”戦略 2022.8.9 意外性あふれるトピックで注目を集めている新型「トヨタ・クラウン」シリーズ。その第1弾となる「クラウン クロスオーバー」をじっくりと観察すると、そのプラットフォームやパワートレインから、したたかで用意周到なトヨタの戦略が見て取れた。
-
第46回:“走る喜び”も電気でブースト 「シビックe:HEV」が示した新しい体験と価値 2022.7.26 スポーティーな走りとエンジンサウンドでドライバーを高揚させるハイブリッド車(HV)。「ホンダ・シビックe:HEV」には、既存のHVにはない新しい提案が、多数盛り込まれていた。若者にも好評だというシビックに追加されたHVを、技術ジャーナリストが試す。
-
![市街地でハンズオフ運転が可能な市販車の登場まであと1年 日産の取り組みを再確認する]() NEW
NEW
市街地でハンズオフ運転が可能な市販車の登場まであと1年 日産の取り組みを再確認する
2026.1.15デイリーコラム日産自動車は2027年に発売する車両に、市街地でハンズフリー走行が行える次世代「ProPILOT(プロパイロット)」を搭載する。その発売まであと1年。革新的な新技術を搭載する市販車の登場は、われわれにどんなメリットをもたらすのか。あらためて考えてみた。 -
![ホンダ・プレリュード(前編)]() NEW
NEW
ホンダ・プレリュード(前編)
2026.1.15あの多田哲哉の自動車放談トヨタでさまざまな車両を開発してきた多田哲哉さんが今回試乗するのは、24年ぶりに復活した「ホンダ・プレリュード」。話題のスペシャルティーカーを、クルマづくりのプロの視点で熱く語る。 -
![第944回:こんな自動車生活は最後かもしれない ―ある修理工場で考えたこと―]() NEW
NEW
第944回:こんな自動車生活は最後かもしれない ―ある修理工場で考えたこと―
2026.1.15マッキナ あらモーダ!いつもお世話になっている“街のクルマ屋さん”で、「シトロエン・メアリ」をさかなにクルマ談議に花が咲く。そんな生活を楽しめるのも、今が最後かもしれない。クルマを取り巻く環境の変化に感じた一抹の寂しさを、イタリア在住の大矢アキオが語る。 -
![第857回:ドイツの自動車業界は大丈夫? エンジニア多田哲哉が、現地再訪で大いにショックを受けたこと]()
第857回:ドイツの自動車業界は大丈夫? エンジニア多田哲哉が、現地再訪で大いにショックを受けたこと
2026.1.14エディターから一言かつてトヨタの技術者としてさまざまな車両を開発してきた多田哲哉さん。現役時代の思い出が詰まったドイツに再び足を運んでみると、そこには予想もしなかった変化が……。自動車先進国の今をリポートする。 -
![マツダCX-60 XDドライブエディション ナッパレザーパッケージ(4WD/8AT)【試乗記】]()
マツダCX-60 XDドライブエディション ナッパレザーパッケージ(4WD/8AT)【試乗記】
2026.1.14試乗記「マツダCX-60」に新グレードの「XDドライブエディション ナッパレザーパッケージ」が登場。スポーティーさと力強さ、上質さを追求したというその中身を精査するとともに、国内デビューから3年を経た“ラージ商品群第1弾”の成熟度をチェックした。 -
![30年の取材歴で初めてのケースも 2025年の旧車イベントで出会った激レア車]()
30年の取材歴で初めてのケースも 2025年の旧車イベントで出会った激レア車
2026.1.14デイリーコラム基本的に旧車イベントに展示されるのは希少なクルマばかりだが、取材を続けていると時折「これは!」という個体に遭遇する。30年超の取材歴を誇る沼田 亨が、2025年の後半に出会った特別なモデルを紹介する。