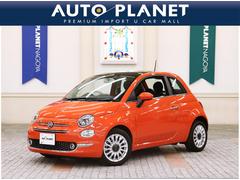フィアット500ツインエア スポーツプラス(FF/5MT)【試乗記】
MTバンザイ! 2012.07.08 試乗記 フィアット500ツインエア スポーツプラス(FF/5MT)……240万円
高いエコ性能と愛らしい“音振”で人気(!?)の「フィアット500」ツインエアユニット搭載車に、5MT仕様が登場した。手ずから操る2気筒エンジン、その運転体験とは?
250台の限定モデル
“MT派”が思わずガッツポーズしたくなる、そんな「フィアット500」が登場した。これまでも1.2リッターモデルには5MTの「フィアット500 1.2スポーツ」が用意されていたが、0.9リッター直列2気筒ターボ「ツインエア」では、シングルクラッチタイプの2ペダルMT「デュアロジック」しか選べなかったのだ。
もちろん、オートマチックのデュアロジックがあるからこそ、フィアット500は日本でもこれだけ広く受け入れられたわけである。そう思うと、この2ペダルMTの果たした役割はとても大きい。それは重々承知している。
しかし、MTの操作が苦にならない、あるいはMTが好きという少数派は、シフトアップ時に生じる空走感にいらだちを覚え、「ああ、これでMTだったらなぁ」と深くため息をついていたに違いない。
そういう私もMT派の端くれだから、250台の限定販売とはいえ、5MTの「500ツインエア スポーツプラス」を導入したインポーターに、とにかく「あっぱれ、よくやった!」と言いたいのだ。それでは順番に、その内容を見ていくことにしよう。
プラス20万円の中身
500ツインエア スポーツプラスの価格は235万円。限定ではないカタログモデルの「500ツインエア ポップ」が215万円だから、ちょうど20万円アップの計算である。“イタリアデビュー5周年記念モデル”という位置付けだけに、充実の装備が自慢である。
まず目を引くのは、ピアノブラックにペイントされたルーフとリアルーフスポイラー。流行のマットブラック仕上げの16インチアルミホイールとともに、ちっこくてかわいい500をスポーティーに彩っている。
ドアハンドルに加えて、テールゲートやフロントのモールディングがチタンマット仕上げになるのもこのクルマならでは。インテリアも、やはり鈍く光るグレーのデコラティブパネルや、ブラックとシルバーのシートを持ち込むなど、スポーティーな雰囲気づくりに積極的だ。
さらに、フロントフォグランプが付き、通常6万8000円のメンテナンスプログラム「イージーケア」が無償となるというのだから、20万円のエクストラを払っても、十分に元が取れる内容である。
早速、運転席に陣取り、アクセル、ブレーキ、クラッチのペダル配置にあまり違和感のないことを確認。輸入コンパクトの右ハンドル/マニュアル車では、往々にしてペダルが左にオフセットしていて運転しにくいことがあるものだが、このクルマの場合は特に気にならない。
アイドリングストップとの相性もバッチリ
エンジンをスタートさせると、ツインエアエンジン特有のポコポコという音と、それに伴う振動がキャビンに伝わってくる。どこか懐かしい雰囲気に浸りながら、クラッチをつないで走りだすと、1速のギア比が低いおかげで、発進はもたつかずに済む。
反面、気を抜くとあっという間にエンジンが回転を上げ、メーターのサインがシフトアップを催促してくる。「そうそう、マニュアルだった」と肝に銘じ、早めのシフトアップを心がける。すると500ツインエア スポーツプラスは、小気味よくスムーズにスピードを上げていった。
街中を流すくらいなら、せいぜい2500rpmまで回せば十分な加速が得られるツインエアエンジン。カタログを見ると、14.8kgmの最大トルクを1900rpmで発生するというが、感覚的には2500rpmを超えたあたりからトルクが盛り上がる印象で、追い越しや高速の合流では高回転に頼ることになる。
もちろん、0.9リッターといっても、数字よりはるかに力強い加速を示すのは、デュアロジックの500ツインエア ポップですでに証明済みだ。
5MTはアイドリングストップとの相性もいい。クルマが停止し、ギアをニュートラルに入れてクラッチペダルから足を離すとエンジンが自動的にストップ。逆に、クラッチを踏み込めばエンジンが再始動する。
これがオートマチックだと、ブレーキを緩めたときにエンジンがスタートする。クラッチ操作が省かれて発進の準備が素早く整うだけに、クルマが動き出すまでのごくわずかなタイムラグに、かえってイライラさせられるクルマは少なくないのである。そういう意味でも、このMTはイライラの解消に一役買っているわけだ。
唯一、気になったのは乗り心地だった。500ツインエア ポップの175/65R14から195/45R16に2インチアップされたシューズのせいで、路面によってはバネ下がバタつき、動きに粗さが目立った。とはいっても、十分受け入れられるレベルであり、このクルマの魅力をスポイルするほどではない。
というわけで、MT派にとっては見逃せない500ツインエア スポーツプラス。今回は限定モデルだが、ぜひ通常のカタログモデルへの昇格も検討してほしい。そのときは、タイヤのインチアップは控えめに。また、個人的には、「500C」に5MTを設定してもらえたら、もう言うことはない。
(文=生方聡/写真=小林俊樹)

生方 聡
モータージャーナリスト。1964年生まれ。大学卒業後、外資系IT企業に就職したが、クルマに携わる仕事に就く夢が諦めきれず、1992年から『CAR GRAPHIC』記者として、あたらしいキャリアをスタート。現在はフリーのライターとして試乗記やレースリポートなどを寄稿。愛車は「フォルクスワーゲンID.4」。
-
BYDシールAWD(4WD)【試乗記】 2026.1.17 BYDのBEVサルーン「シール」の機能アップデートモデルが登場。強化のポイント自体はそれほど多くないが、4WDモデルの「シールAWD」は新たに電子制御式の可変ダンパーを装備したというから見逃せない。さまざまなシーンでの乗り心地をチェックした。
-
マツダCX-60 XDドライブエディション ナッパレザーパッケージ(4WD/8AT)【試乗記】 2026.1.14 「マツダCX-60」に新グレードの「XDドライブエディション ナッパレザーパッケージ」が登場。スポーティーさと力強さ、上質さを追求したというその中身を精査するとともに、国内デビューから3年を経た“ラージ商品群第1弾”の成熟度をチェックした。
-
カワサキKLX230シェルパS(6MT)【レビュー】 2026.1.13 その出来には“セロー乗り”も太鼓判!? カワサキのトレイルバイク「KLX230シェルパ」に、ローダウン仕様の「シェルパS」が登場。安心の足つき性で間口を広げた一台だが、実際に走らせてみると、ストリートでも楽しめるオールラウンダーに仕上がっていた。
-
メルセデス・ベンツC220dラグジュアリー(FR/9AT)【試乗記】 2026.1.12 輸入車における定番の人気モデル「メルセデス・ベンツCクラス」。モデルライフ中にも年次改良で進化し続けるこのクルマの、現在の実力はいかほどか? ディーゼルエンジンと充実装備が魅力のグレード「C220dラグジュアリー」で確かめた。
-
日産ルークス ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション(FF/CVT)【試乗記】 2026.1.10 日産の軽スーパーハイトワゴン「ルークス」がフルモデルチェンジ。「見えない危険が……」のテレビCMでお茶の間をにぎわせているが、走る、曲がる、止まるをはじめとしたクルマ全体としての仕上がりはどうか。最上級グレードをテストした。
-
![フェラーリ12チリンドリ(後編)]() NEW
NEW
フェラーリ12チリンドリ(後編)
2026.1.18思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「フェラーリ12チリンドリ」に試乗。前編では伝家の宝刀であるV12エンジンを絶賛した山野。後編ではコンビを組むシャシーの印象を余すところなく聞いてみた。 -
![BYDシールAWD(4WD)【試乗記】]()
BYDシールAWD(4WD)【試乗記】
2026.1.17試乗記BYDのBEVサルーン「シール」の機能アップデートモデルが登場。強化のポイント自体はそれほど多くないが、4WDモデルの「シールAWD」は新たに電子制御式の可変ダンパーを装備したというから見逃せない。さまざまなシーンでの乗り心地をチェックした。 -
![新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る]()
新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る
2026.1.16デイリーコラム英国のモーターサイクル史にあまたの逸話を残してきた名門、ノートンが、いよいよ再始動! その数奇な歴史を振り返るとともに、ミラノで発表された4台の次世代モデルを通して、彼らが思い描く未来像に迫った。 -
![第858回:レースの技術を市販車に! 日産が「オーラNISMO RSコンセプト」で見せた本気]()
第858回:レースの技術を市販車に! 日産が「オーラNISMO RSコンセプト」で見せた本気
2026.1.15エディターから一言日産が「東京オートサロン2026」で発表した「オーラNISMO RSコンセプト」。このクルマはただのコンセプトカーではなく、実際のレースで得た技術を市販車にフィードバックするための“検証車”だった! 新しい挑戦に込めた気概を、NISMOの開発責任者が語る。 -
![ルノー・グランカングー クルール]()
ルノー・グランカングー クルール
2026.1.15画像・写真3列7座の新型マルチパーパスビークル「ルノー・グランカングー クルール」が、2026年2月5日に発売される。それに先駆けて公開された実車の外装・内装を、豊富な写真で紹介する。 -
![市街地でハンズオフ運転が可能な市販車の登場まであと1年 日産の取り組みを再確認する]()
市街地でハンズオフ運転が可能な市販車の登場まであと1年 日産の取り組みを再確認する
2026.1.15デイリーコラム日産自動車は2027年に発売する車両に、市街地でハンズフリー走行が行える次世代「ProPILOT(プロパイロット)」を搭載する。その発売まであと1年。革新的な新技術を搭載する市販車の登場は、われわれにどんなメリットをもたらすのか。あらためて考えてみた。