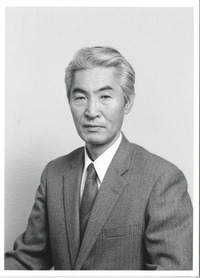第76回:軽自動車群雄割拠の時代
“国民車構想”が育んだ日本のミニマルカー
2020.06.04
自動車ヒストリー
人々の生活を支える“足”として、今やなくてはならない存在となった軽自動車。わが国独自のミニマルカーは、どのような発展を遂げてきたのか? 日本にモータリゼーションをもたらした名車「スバル360」の誕生に至る歴史を振り返る。
スクーターと“原付き”から始まった戦後の自動車づくり
「ツウテン」「テルヤン」「クノマック」「ニッケイタロー」「くろがねベビー」……。これらはすべて、1950年代に販売されていた軽自動車の名前である。日本のモータリゼーション前夜、庶民にも手の届きそうなクルマが町の小さな工場で産声をあげ、自動車産業の場で覇を唱えようとする者があちこちに現れ始めていた。
第2次大戦後、焦土となった日本では交通のインフラも壊滅状態だった。二輪、四輪ともに、エンジンで走る乗り物は軍への供出で姿を消してしまっていたのである。進駐軍のジープは走り回っていたが、庶民の移動手段は貧弱だった。あらゆる物資が不足するなか、戦時中に飛行機をつくっていた会社がスクーターの製造を始める。金属部品などの資材や工作機械を持っていたため、それを利用して民生用の製品をつくることができたのだ。旧中島飛行機が「ラビット」を、三菱が「シルバーピジョン」を発売し、手軽な足として人気を得た。
ホンダは旧陸軍の無線機用発電機のエンジンを自転車に取り付け、エンジン駆動で走る二輪車を発売する。“バタバタ”と呼ばれて親しまれ、同様の製品をつくる中小メーカーが次々と現れた。ホンダはエンジンを自社開発するようになり、オートバイメーカーとして成長していく。
一方、四輪自動車の生産はGHQによって禁止されていた。民需用トラックを皮切りに少しずつ規制は解かれていったものの、戦争によって技術の進歩は滞り、生産設備も十分ではなかった。トヨタやダットサンなど、戦前からある自動車会社が生産を始めたトラックはとても高価で、零細業者が買えるような価格ではない。商売に使う運搬器具は、リアカーやサイドカーに頼るほかなかったのである。
1948年になると、小型自動車の規格が制定される。翌年には軽自動車枠が設定されるが、それは全長2.8m、全幅1m、全高2m、排気量は4ストローク150cc、2ストローク100ccというもので、想定されているのは二輪車だけだった。1950年に三輪および四輪の規格が設定され、その翌年に改正された規定が日本の自動車産業の初期設定となった。全長3m、全幅1.3m、全高2m、排気量は4ストローク360cc、2ストローク250ccである。
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
商用三輪トラックのミゼットが大人気に
1951年、日本初の軽四輪乗用車が誕生する。戦前に名古屋でオート三輪の「ヂャイアント号」を作っていた中野嘉四郎が開発した、「オートサンダル」である。中日本工業製の4ストローク348cc単気筒エンジンに、ディスク摺動(しゅうどう)方式という一種のオートマチックトランスミッションを組み合わせていた。出力は5馬力ほどで、スピードは40km/hそこそこだったとみられる。まさに簡便なサンダルといった趣のクルマだったが、価格は約30万円だった。50万円出せばダットサンのトラックが買えたので、決して安いとはいえない。それでも需要はあって、改良を加えながら1954年までに約200台が生産された。
このほかにも、全国でさまざまな軽自動車が誕生するが、そのほとんどは商用車だった。自動車は運転して楽しむためのものではなく、荷物を運ぶ実用的なツールだったのだ。商売に使うのだから、コストパフォーマンスが優れていなければならない。その点で有利なのが、三輪自動車だった。戦前から三輪トラックをつくっていた東洋工業(現マツダ)やダイハツは、いち早く実用的な商用車の生産を始めた。
三輪であれば、前輪が一輪なので複雑な操舵機構を必要としない。オートバイに荷台を取り付けただけの簡易な三輪車も多くつくられた。軽自動車の規格でつくられたオート三輪では、「ダイハツ・ミゼット」がヒット作となった。1957年に発売された初代モデル「DK」型は全長2535mm、全幅1200mmという小さなサイズで1人乗り。ドアは備わらない。シートの上部に幌(ほろ)を装着し、バーハンドルで操舵する。2ストローク単気筒249ccのエンジンで、カタログでは最高速度65km/hをうたっていた。
1959年のフルモデルチェンジで登場した「MP」型は、ドアが装着されてルーフはスチール製も選べるようになる。2名乗車で丸ハンドルが採用され、自動車らしさが増した。乗用車的に使われる場合も多く、東南アジアにはタクシー用途で輸出もされた。1972年まで生産される長寿モデルとなったのである。
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
いち早く排気量拡大に対応したスズライト
1955年に軽自動車の規格が見直され、2ストロークエンジンでも排気量が360ccまで拡大された。自動織機会社からオートバイ製造に進出していたスズキが、いち早くこの規定に沿って開発したのが「スズライト」である。2ストロークの2気筒360ccエンジンは15馬力を発生し、12馬力程度だった4ストロークエンジンに対してアドバンテージを築いた。前輪駆動を採用したのも先進的で、車内空間を広くとることができた。ただ、セダンの売れ行きは好調とはいえず、ライトバンのみに生産が絞られることとなった。
1958年、日本車の歴史に大きな足跡を刻む軽自動車が登場した。富士重工業(現スバル)の「スバル360」である。スクーターを製造していた三鷹工場と太田工場も含め、分割されていた旧中島飛行機が1955年に再合同して富士重工業となり、航空機や自動車の生産を始めていた。
開発を主導した百瀬晋六は、中島飛行機で設計部に勤務し、軍用機のターボチャージャーなどを担当していた。戦争が終わって会社から与えられた仕事は、バスボディーの設計である。百瀬は航空機の技術を生かしてモノコックボディーのバスをつくり、市場での評価を高めていた。その経験を生かし、百瀬に乗用車を開発するよう命が下る。「P-1」と名付けられた小型車は3年足らずで試作車製作にこぎつけ、高い完成度で関係者を驚嘆させた。
「スバル1500」という仮の名前も与えられたが、乗用車の生産・販売を手がけたことのない富士重工業はリスクを恐れて市販化を断念する。百瀬には、代わりに軽乗用車の開発が託された。まずは小さなサイズのクルマでスタートすべきだと、会社は考えたのだ。1955年に通商産業省の策定した“国民車構想”が明らかになっており、政策としてミニマムな乗用車の生産が求められていたことも追い風になった。
日本にモータリゼーションをもたらしたスバル360
百瀬は、軽自動車であっても大人4人がゆったり乗れるようにしようと考えた。エンジンをリアに積んで後輪を駆動するRR方式を採用し、プロペラシャフトを不要にすることで車内空間を広くとる。軽量化も重視し、得意のモノコック構造を使ってボディー全体で剛性を確保した。広い空間と剛性向上に有利であることから、スタイリングは丸みを帯びたものとなった。
リーフやコイルといったスプリングを用いず、棒状のトーションバーでサスペンションを構成したのも、軽量化とスペース効率を考えてのことだった。エンジンは2ストローク2気筒で、リアに横置きする。効率的なパッケージングを追求して1958年に発表された「スバル360」は、当時の軽自動車の水準をはるかに超えるものとなった。車両重量は385kgで、500kg以上のクルマも珍しくなかった中では際立った軽さといえる。軽量ボディーは動力性能にも好影響を及ぼし、最高速度は83km/hとされた。無理なく4名乗車が可能なことも、人々を驚かせた。
かわいらしい見た目から、“てんとう虫”という愛称で呼ばれた。“かぶと虫”こと「フォルクスワーゲン・ビートル」からの連想である。価格は42万5000円で、後のコストダウンで36万円にまで下がっている。性能から考えれば安かったが、大卒の初任給が1万4000円程度だった時代であり、簡単に買える金額ではなかった。それでも人々は、マイカーの夢がかなう可能性を初めて信じることができたのだ。
1960年代に入ると、「マツダ・キャロル」や「ホンダN360」など、魅力的な軽自動車が続々と誕生する。それでもスバル360の人気は根強く、1970年まで生産が続けられた。その後、軽自動車の規格は1976年に排気量が550ccに引き上げられ、1990年に660ccになった。限られた空間の中で小さなエンジンを生かすクルマづくりはその後も日本独自の進化を遂げ、今日では新車販売数のうち約4割を占めるに至っている。
(文=webCG/イラスト=日野浦剛)
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |
 拡大 拡大 |

鈴木 真人
名古屋出身。女性誌編集者、自動車雑誌『NAVI』の編集長を経て、現在はフリーライターとして活躍中。初めて買ったクルマが「アルファ・ロメオ1600ジュニア」で、以後「ホンダS600」、「ダフ44」などを乗り継ぎ、新車購入経験はなし。好きな小説家は、ドストエフスキー、埴谷雄高。好きな映画監督は、タルコフスキー、小津安二郎。
-
第105回:資本主義のうねりを生んだ「T型フォード」
20世紀の社会を変えた大量生産と大量消費 2021.7.21 世界初の大量生産車となり、累計で1500万台以上が販売された「T型フォード」。このクルマとヘンリー・フォードが世にもたらしたのは、モータリゼーションだけではなかった。自動車を軸にした社会の変革と、資本主義の萌芽(ほうが)を振り返る。 -
第104回:世界を制覇した“普通のクルマ”
トヨタを支える「カローラ」の開発思想 2021.7.7 日本の大衆車から世界のベストセラーへと成長を遂げた「トヨタ・カローラ」。ライバルとの販売争いを制し、累計販売台数4000万台という記録を打ち立てたその強さの秘密とは? トヨタの飛躍を支え続けた、“小さな巨人”の歴史を振り返る。 -
第103回:アメリカ車の黄金期
繁栄が増進させた大衆の欲望 2021.6.23 巨大なボディーにきらびやかなメッキパーツ、そそり立つテールフィンが、見るものの心を奪った1950年代のアメリカ車。デトロイトの黄金期はいかにして訪れ、そして去っていったのか。自動車が、大国アメリカの豊かさを象徴した時代を振り返る。 -
第102回:「シトロエンDS」の衝撃
先進技術と前衛的デザインが示した自動車の未来 2021.6.9 自動車史に名を残す傑作として名高い「シトロエンDS」。量販モデルでありながら、革新的な技術と前衛的なデザインが取り入れられたこのクルマは、どのような経緯で誕生したのか? 技術主導のメーカーが生んだ、希有(けう)な名車の歴史を振り返る。 -
第101回:スーパーカーの熱狂
子供たちが夢中になった“未来のクルマ” 2021.5.26 エキゾチックなスタイリングと浮世離れしたスペックにより、クルマ好きを熱狂させたスーパーカー。日本を席巻した一大ブームは、いかにして襲来し、去っていったのか。「カウンタック」をはじめとした、ブームの中核を担ったモデルとともに当時を振り返る。
-
![ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】]() NEW
NEW
ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】
2026.1.19試乗記ベントレーのラグジュアリークーペ「コンチネンタルGT」のなかでも、ウェルビーイングにこだわったという「アズール」に試乗。控えめ(?)な680PSのハイブリッドがかなえる走りは、快適で満ち足りていて、ラグジュアリーカーの本分を感じさせるものだった。 -
![第327回:髪もクルマもナイスファイト!]() NEW
NEW
第327回:髪もクルマもナイスファイト!
2026.1.19カーマニア人間国宝への道清水草一の話題の連載。日産の新型「ルークス」で夜の首都高に出撃した。しっかりしたシャシーとターボエンジンのパワフルな走りに感心していると、前方にスーパーカーの姿を発見。今夜の獲物は「フェラーリ・ローマ」だ! -
![日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!]() NEW
NEW
日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!
2026.1.19デイリーコラムアメリカからの外圧による制度変更で、北米生産モデルの国内導入を決めたトヨタ。同様に、今後日本での販売が期待できる「海外生産の日本車」には、どんなものがあるだろうか? 清水草一が検証してみた。 -
![フェラーリ12チリンドリ(後編)]()
フェラーリ12チリンドリ(後編)
2026.1.18思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「フェラーリ12チリンドリ」に試乗。前編では伝家の宝刀であるV12エンジンを絶賛した山野。後編ではコンビを組むシャシーの印象を余すところなく聞いてみた。 -
![BYDシールAWD(4WD)【試乗記】]()
BYDシールAWD(4WD)【試乗記】
2026.1.17試乗記BYDのBEVサルーン「シール」の機能アップデートモデルが登場。強化のポイント自体はそれほど多くないが、4WDモデルの「シールAWD」は新たに電子制御式の可変ダンパーを装備したというから見逃せない。さまざまなシーンでの乗り心地をチェックした。 -
![新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る]()
新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る
2026.1.16デイリーコラム英国のモーターサイクル史にあまたの逸話を残してきた名門、ノートンが、いよいよ再始動! その数奇な歴史を振り返るとともに、ミラノで発表された4台の次世代モデルを通して、彼らが思い描く未来像に迫った。